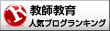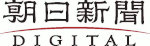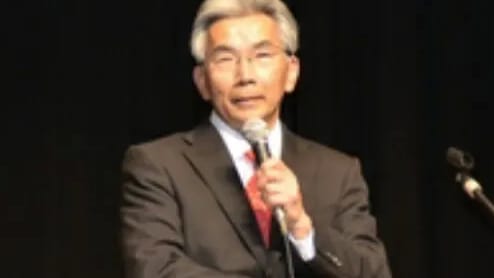
予測がつかなくなったトランプの迷走と安倍外交の危うさ
2019-05-11
二正面作戦だけでも同時に出来ないと言われているのに、いまや三正面作戦だ。
つまり、トランプ大統領の米国は、北朝鮮とイランに加え、中国に対しても対決辞さずの強硬姿勢に出ている。
外交の常識では考えられない強硬さだ。
なぜトランプ大統領は急にここまで強行姿勢を取るようになったのか。
それはロシア疑惑が晴れないからだ。
強がりとは裏腹に、モラー特別検査官の報告書がトランプ大統領を追いつめつつあるからだ。
ついにロシア疑惑を疑う世論のほうが、疑わない世論を上回るようになった。
トランプ大統領の唯一の救いは、支持率が上昇していることだ。
逆にいえば、支持率が下がれば、たちどころに危うくなる。
そして、二年後の大統領選を控え、もし少しでも劣勢が伝えられるようになれば、再選が危うくなるばかりでなく、任期中の失脚すらあり得る。
それだけは何としてでも避けたい違いない。
つまり、これからのトランプ大統領の最優先課題は、大統領選に向けた優勢を保ち続けることだ。
だからトランプ大統領の外交は、ますます予測不能な危ういものとなるだろう。
そんなトランプ大統領に従属するしかない安倍・菅政権の外交は危うい。
大げさにいうわけではないが、日本外交は戦後最大の試練の中にあるということだ。
安倍外交は大ピンチなのだ。
しかし、それを迎え撃つ野党には安倍外交に代る外交はない。
安倍外交の矛盾や二枚舌を批判する事は出来ても、どうすればいいかを示せない。
ここでもまた野党は安倍一強を指をくわえて見ているだけである。
いまこそ新党憲法9条外交なのである(了)

森・プーチン会談でも持ち出されていた米軍基地問題の衝撃
2019-05-11
河野・ラブロフ外相会談が行われ、あらためて北方領土問題の解決の難しさが浮き彫りになった。
まだこんな不毛な交渉をやっているのか、と言う思いだ。
しかし私がここで書くのはその事ではない。
安倍北方領土外交が決定的に頓挫したのは、プーチン大統領が北方領土に米軍基地を置かないと確約できるのか、という究極の問いかけをしたからだった。
この問いかけを最初に受けたのは谷内正太郎安全保障局長だった。
元外務官僚の谷内は、パブロフの犬のごとく、それは出来ない、とあっさりと答えたばっかりに、ロシア側はこれではダメだとなった。
もし安倍首相がトランプとの信頼関係をうまく使ってトランプを説得し、よし、それでは米軍基地を置かないことにする、とプーチン大統領に約束出来ていれば、あるいは状況は全く違っていたものになっていたかもしれないが、今となってはすべて後の祭りだ。
ところがである。
この北方領土に米軍基地を置くか置かないかという懸案は、2001年のプーチン大統領と森喜朗首相との間でも、プーチン大統領から持ちかけられていたというのだ。
「ヨシ、島を渡した後、米国が基地をつくらないといえるのか」と懸念を伝えたというのだ。
きょう5月11日の日経新聞がそのことを教えてくれた。
その時、プーチン大統領は、「ヨシ、これを見てくれ」と地球儀を上から示し、「ここが北極、そしてここがアラスカでここが米国。米国はこんなにもロシアのすぐ目の前にある脅威だ」と言ったというのだ。
20年近くも前に、すでにプーチン大統領は同じ問題を提起していたのだ。
それにもかかわらず、外務省は北方領土返還交渉におけるこの最大の問題について正面から議論することなく、安倍首相はあの時の森首相と同じように、日本を信じてもらうしかないと、あいまいな返事しか言えなかったのだ。
しかも、プーチン大統領は森喜朗が好きだから交渉を続けてきたが、ウクライナ問題の制裁に賛成した安倍首相にプーチン大統領は激怒したというのだ。
この日経新聞の記事が教えてくれたこと。
それは、そもそも、森・プーチン外交で取り返せなかったものを、安倍・プーチン外交で取り返せるはずがなかったのだ。
「北方領土問題解決で衆参ダブル選挙だ」という政治記事は、メディアがつくりだした世迷いごとだったのである(了)
し

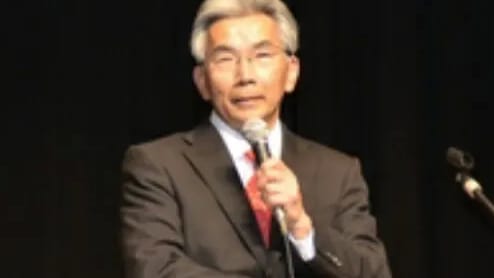
マハティール首相 あなたまでもか
2019-05-11
私の長い外交官人生において、ブッシュ大統領(父)やアラファトやマンデラなど、国際政治を動かすプレーヤーと直接あって言葉を交わす機会に恵まれたことはよかった。
マレーシアのマハティール首相もそのうちのひとりだ。
その中でも特にマハティール首相は、米国のパレスチナ政策に一貫して批判的であり、そしてあのイラク攻撃を止められなかった国連のアナン事務局長を、その責任を取って即刻辞任すべきだと発言するなど、私にとってもっとも尊敬する指導者だ。
そのマハティール首相が90歳を超えて再びマレーシアの首相に返り咲き、マレーシアの憲法に日本の憲法9条を取り入れると発言したことは私を勇気づけてくれた。
それにとどまらず、世界の国々は憲法9条を取り入れよと提唱して私を驚かせた。
ますます私はマハティール首相のフアンになった。
ところが、きょう5月11日の朝日と日経が、それぞれ「マハティール首相 苦境」(朝日)、「マハティール氏 いばらの道」と、奇しくも同じような記事を掲載した。
すなわち、きのう5月10日で首相に返り咲いて丸一年経ったが、ここにきて、支持率が激減しているというのだ。
財政再建が思うように進まないとか、成長戦略が見えてこないとか、マレー民族優遇政策を見直そうとしたからだとか、様々な理由が挙げられている。
しかし、私が残念に思ったのは、朝日と日経が共通してこう書いていたところだ。
マハティール首相は、今度の政界復帰に際しては、かつて自ら追放したアヌワール元副首相と和解し、アヌワール元副首相と組んで選挙に勝利し、そして今度こそ2年でアヌワール元副首相に首相の座を禅譲すると公約していた。
私はそれを高く評価した。
ところが、ここにきてマハティール首相は任期について言葉を濁すようになってきたという。
あと3年やるか2年やるかわからないと言い出したという。
そんな事を言うようではおしまいだ。
今度こそアヌワール元副首相との約束を反故にしてはいけない。
権力につけば、マハティール首相と言えども、その権力を手放し難いのか。
マハティール首相 あなたまでもか
そういう思いで私は朝日と日経の記事を読んだのである(了)
奨学金「半額超えた分返して」 650万円求め提訴へ
未返還の奨学金をめぐり、日本学生支援機構が保証人に半額しか支払い義務のないことを伝えず全額請求している問題で、すでに全額を返し終えた保証人ら4人が、半額を超えた約650万円の返金などを求める訴えを14日、東京地裁などに起こす。
原告側弁護士によると、4人は東京、埼玉、北海道に住み、2009年以降、機構から全額を返すよう求められた。3人の保証人は計約1270万円の返還を完了し、1人は半額を約17万円超えて返還した。
『(数人の保証人がある場合)民法第456条数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。
(分割債権及び分割債務)第427条数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。』
奨学金では、借りた本人が返せない場合に備え、連帯保証人(親)と保証人(4親等以内の親族)を1人ずつ立てる。民法で各保証人は等しい割合で義務を負うとされ、本人と同様に全額を負う連帯保証人とは異なり、保証人には半額の支払い義務しかない。「分別の利益」と呼ばれる。
機構は、分別の利益は保証人が申し出るべきものだと主張。返還中なら減額に応じるが、返還を終えた場合などは対象外としている。機構は「すでに払われた分は次世代の奨学金に充てている」と説明してきた。
一方、原告側は「分別の利益を伝えず、法知識がないのを利用して全額回収するのは悪質。機構が半額を超えて回収した分は不当利得にあたる」と訴える。
機構は「訴状を確認できないためコメントは控える」としている。
朝日新聞の取材によると、機構は17年度までの8年間で延べ825人の保証人に未返還分の全額、計約13億円を請求し、返還に応じなければ法的措置をとると伝えていた。(諸永裕司)
民法第三編 債権第一章 総則
第三節 多数当事者の債権及び債務
第一款 総則(第四百二十七条)
第四款 保証債務(第四百四十六条-第四百六十五条)
現実に日本学生支援機構の奨学金貸与の資金的維持が、現実に困難なって来ている為なのでしょうか。
連帯保証人とは異なり、保証人には半額の支払い義務しかない。
第三編 第一章 総則債権第三節 多数当事者の債権及び債務
第三節 多数当事者の債権及び債務 第一款 総則(第四百二十七条)第四款 保証債務(第四百四十六条-第四百六十五)
(数人の保証人がある場合)民法第456条数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。(分割債権及び分割債務)第427条数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。』の「分別の利益」と呼ばれる民法の規定を日本学生支援機構は守るべきです.
日本学生支援機構の件で話題。保証人の「分別の利益」とは?
朝日新聞のこちらの記事が話題となっております。
国の奨学金を借りた本人と連帯保証人の親が返せない場合に、保証人の親族らは未返還額の半分しか支払い義務がないのに、日本学生支援機構がその旨を伝えないまま、全額を請求していることがわかった。
奨学金を借りる場合、その親や親族が保証人・連帯保証人となることがあります。
通常は借りた本人が返済をしますが、本人が支払えなくなった場合には保証人・連帯保証人に請求がいきます。
分別の利益とは?
保証人が1人、連帯保証人が1人の場合、保証人と連帯保証人とでは返還義務を負う金額が異なってきます。
連帯保証人は残債務額全額について返還義務を負いますが、保証人は残債務額の半分しか返還義務を負いません。
根拠条文は民法456条、民法427条です。
(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
二つの条文の関係を読み解かなければならないので少々複雑ですが、要は、保証人が複数いる場合には、個々の保証人はそれぞれ等しい割合で返還義務を負うということです。
つまり、残債務額が100万円で、保証人が2人の場合には、個々の保証人は50万円の範囲で返還義務を負うということになります。
こういった保証人が複数いる場合に保証人の責任の範囲が限定されることを専門用語で「分別の利益」と呼んでいます。
なお、この分別の利益が認められるのは保証人だけで、連帯保証人には分別の利益は認められません。
記事のケースでは保証人と連帯保証人が一人ずついるケースのようです。
この場合、保証人は分別の利益を受けることができるので残債務額の半分を返還する義務を負うだけです。
他方、連帯保証人には分別の利益はありません。ですから連帯保証人は残債務全額の返済をする義務を負います。
何が問題なのか?
以上の法的知識を前提として、今回の日本学生支援機構の対応のどこが問題なのかについて考えていきましょう。
今回、日本学生支援機構は、残債務の返還を請求する際に、この分別の利益を有する保証人に対しても、「分別の利益を主張できますよ」ということを伝えないまま残債務額全額の請求をしていたとのことです。そして、保証人側から分別の利益の主張があれば返還額を半分に減額していたようです。
記事では、この日本学生支援機構の請求の仕方自体は違法ではないと説明されています。(ここについては個人的に疑問がないわけではありませんが、違法でないという前提で以下続けます。)
問題の焦点は、「分別の利益」という法的知識を有している人は減額され、そうでない人は減額されないという対応が果たして妥当か、という点です。
同じ「保証人」であっても、ある人は残債務全額を支払っているが、別の人は残債務の半分しか支払っていないという事態が発生しているわけですが、それは果たして妥当なのかということです。
どう考えるべきか?
日本学生支援機構の請求の仕方が法的観点からは問題ないとしても、道義上・社会通念上はどうでしょうか。
日本学生支援機構と保証人とは対立当事者ですから、日本学生支援機構がいわば「敵」に対してわざわざ「分別の利益というのがあってですね・・・」などと丁寧に説明する必要はない、敵に塩を送る必要はない、という考え方もあると思います。
他方で、記事の中で山野目教授が指摘しておられるように、奨学金事業を担う公的機関としての社会的責任は否定できないでしょう。保証人側との情報格差も考慮しなければなりません。法的知識を有しているかいないかという事情で、同じ保証人なのに責任の割合が異なってきてしまうのは不平等ではないか、という意見もあるでしょう。
私は、この日本学生支援機構の請求の仕方は問題が大きいと考えています。
民法456条と427条を読む限り、保証人の債務の範囲は法律上当然に半分になります。契約締結当初から保証人は債務額の半分の責任しか負っていないわけです。
保証人が「分別の利益」を主張した時点で、ポコッと債務の額が半分に減額されるわけではありません。
保証人が複数いることも、その保証人が分別の利益を有していることも日本学生支援機構にとっては自明のことです。当然保証人の責任の範囲が債務額の半分ということも認識していると考えるべきです。
その日本学生支援機構が、この事実を無視して保証人側の無知につけ込むような請求の仕方をする、その上全額回収までしてしまうのは問題だと考えます。
そもそも保証制度自体問題が大きい
そもそも保証制度は借りた本人のみならずその家族や親族にまで影響が及んでしまうことも多い制度です。
奨学金が返せないために、借りた本人のみならず、その親まで破産をしなければならないというケースも稀ではありません。
保証制度自体を廃止すべきだという主張もあります。
今回の民法改正で保証制度には大きな変更がありましたが、廃止にはなっていません。
保証・連帯保証制度や民法改正による変更点についてはまた別の機会に記事を書きたいと思います。
保証人はどう行動すればいいのか?
最後に、現在保証人になっている人はどう行動すべきなのかについて書きたいと思います。
機構によると、救済されるのは、全額請求を受けて機構との返還計画に合意し、返還中の保証人。計画に沿って返還中であっても、分別の利益を主張すれば機構は減額に応じる。すでに返還した額が総額の2分の1を超えている場合、超過分は返金しないという。返還を終えた人や、裁判の判決や和解で返還計画が確定した人は、返還中でも減額に応じない。・・・
また、機構側から保証人に対し、分別の利益を伝えるかどうかは検討中という。・・・
こちらの記事によれば、返済中の保証人であっても分別の利益を主張すれば減額されるとのことです。しかし返還済みの保証人や裁判の判決や和解に基づいて返還をする義務を負う保証人は、救済されないようです。
また、日本学生支援機構側から保証人に対して分別の利益について説明をするかどうかは検討中とのことです。
保証人としては、機構に対し、できる限り早めに、「自分は分別の利益を有しているので半分しか支払わない」ときちんと通知することが大事です。
あとあとの立証も見据えて、通知は書面で行うべきでしょう。
自分が分別の利益を有しているかよくわからない、どんな書面を送ればいいかわからないという方は、弁護士にご相談されることをオススメします。
奨学金問題対策全国会議が緊急声明を発表【2018.11.8 追記】
「当会議は、独立行政法人日本学生支援機構に対し、学資金の借主の保証人が有する分別の利益を無視して保証人に全額請求する行為を直ちに止め、あわせて、これまで分別の利益を無視して保証人から取得した法律上支払義務のない金員は、保証人が敢えて返還を求めない場合を除き、これを直ちに全額返還するよう求める。」
独立行政法人日本学生支援機構に対し、分別の利益を無視した保証人に対する全額請求の即刻停止と、保証人から取得した支払義務のない金員全額の即時返還を求める緊急声明
こちらの声明は、今回の日本学生支援機構の対応の問題点をほぼ網羅的に指摘しており大変参考になります。途中の法律論はちょっと難しいかもしれませんが、一読の価値ありです。
2018年11月03日
その他の弁護士コラム
シベリア抑留死
ウェブ検索結果
新たに14人特定
産経新聞2019年05月10日16時09分
厚生労働省は10日、第二次大戦後に旧ソ連に抑留され、シベリア地域で死亡した日本人計14人を特定し、都道府県別の出身地とともにホームページで公表した。これで抑留死亡者の特定はシベリア地域(モンゴル地域を含む)で4万261人となった。
公表された14人は次の通り。(敬称略)
◇
【秋田県】佐藤喜一郎
【山形県】石川吉之助、小関好
【宮城県】小島靖男、柏原清之助
【岐阜県】河江水保
【大阪府】八川奈良治郎
【京都府】杉山壽三
【岡山県】岡田三男、小林増美
【愛媛県】小島兼一
【熊本県】荒牧貢、上野賢三郎、高本保
資本主義国は、悪いことをしても共産党の政権の社会主義国家は悪いことをしていないと言共産党支持者Facebookでこのまえ反論して来ましたが。
ダモイと騙されて極寒地シベリアに強制連行されて、亡き母の
シベリア抑留されていた伯父の証言ですが。キャベツ一枚浮いているスープの食事だけだったそうです。
戦後強制労働で亡くなった日本人をどう見据えるのか。モンゴルや、北朝鮮送られて亡くなった日本もいます。
過去の歴史に眼をつぶるもの日本の昭和史に盲目になると言うことです。
社会主義国、労働者の味方で有るはずのソビエト社会主義共和国の日本人を強制労働で、約5万5千人が死亡させた歴史に残るロシア側の責任放棄の無責任さです。
遺族の方々は、ロシアや日本共産党には、良い気持は持てないと思います。
日本だけが、悪いと言うなら、社民党も共産党も遺族の為に損害賠償請求をするのが、日本人なら、人としての道です。
亡くなられた人達に異国の丘の歌を供養の為にお贈り申し上げます。
/合掌
"異国の丘" を YouTube で見る
https://youtu.be/9hkoI_r3MLM
ウィクペディアより一部引用
シベリア抑留(シベリアよくりゅう)は、第二次世界大戦の終戦後、武装解除され投降した日本軍捕虜らが、ソビエト連邦(ソ連)によって主にシベリアなどへ労働力として移送隔離され、長期にわたる抑留生活と奴隷的強制労働により多数の人的被害を生じたことに対する、日本側の呼称である。ソ連によって戦後に抑留された日本人は約57万5千人に上る。厳寒環境下で満足な食事や休養も与えられず、苛烈な労働を強要させられたことにより、約5万5千人が死亡した]。 このソ連の行為は、武装解除した日本兵の家庭への復帰を保証したポツダム宣言に反するものであった。ロシアのエリツィン大統領は1993年(平成5年)10月に訪日した際、「非人間的な行為」として謝罪の意を表し]。ただし、ロシア側は、移送した日本軍将兵は戦闘継続中に合法的に拘束した「捕虜」であり、戦争終結後に不当に留め置いた「抑留者」には該当しないとしている。