記事のポイント①2025年の大阪万博では「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマに②資材の高騰や建設工事要員の不足で、未来社会の共創が困難になりつつある③「ふさわしい万博はどうあるべきか」を問い直す必要がある

2025年4月の大阪万博開催まで2年を切りました。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。サブテーマに「いのちを救う」「いのちに力を与える」「いのちをつなぐ」を掲げて、未来社会の実験場として未来社会を共創することをコンセプトにしています。(サステナ経営ストラテジスト・松田雅一)
一方で、コロナウイルスのまん延や資材の高騰、建設工事要員の不足から、受発注が成立せず、今後の突貫工事を許容するような要請が出されるなど、未来をデザインするには、ほど遠い状況と言わざるを得ません。
今、日本を含む世界では、自然災害による社会生活への影響が甚大なほか、ロシアによるウクライナへの侵攻と破壊が続きます。未来社会を描くべき領域や手法はほかにあります。これを機に、万博のあり方を見直してはどうでしょうか。
長い年月をかけて万博を誘致し、大阪の活性化へインフラの整備や様々な建設計画が進んでいることは理解しつつも、開催に「黄色信号」が灯った現状で、そのテーマやコンセプトを考えた時に、あるべき姿が見えてくる気もします。
まずは、地球の資源・資材を使い、いずれは撤去するようなハコモノを作る必要があるのかどうかです。展示品だけではなく、ハコモノを創る段階から未来社会を共創することが、テーマに沿った本来の姿のはずです。
2025年ではない、今この瞬間に「いのちを救う」「いのちに力を与える」「いのちをつなぐ」ところがあるのです。食糧危機、自然災害、戦争の災禍に苛まれている場面をリアルに観る中で、実験場ではない実地での未来創造が必要です。
世界では、小中学校の教育施設まだまだ不足しており、テンポラリーに巨額の費用でパビリオンを建設するよりも、不足する国々に教育施設を増やすことで、世界の知恵を底上げすることこそが共創かも知れません。
また、万博を開催するにあたっては、日本の現状の立ち位置にも問題がある。世界中の課題やソリューションを共有し、プラットフォームを創って世界の英知を集めるとするならば、日本の今ある英知をまず明確に示すべきでしょう。
日本にもSDGs推進本部が設置され持続可能な社会への課題を見据えてはいるものの、その中身は定性的で、具体的数値目標に乏しく、目標達成へのアプローチが見えず、結果としての統計結果を追いかけているのみです。
インフラを整備し、ハコモノを創り、アトラクションやイベントを開催し、世界の人が集う。お祭りとしての万博であれば、それはそれで成功かも知れません。しかし、「地球が沸騰する時代」の中で、真のサステナビリティを実現するために、私たちは何をすべきか問われています。
「いのち輝く未来社会のデザイン」、「いのちを救う」「いのちに力を与える」「いのちをつなぐ」ことをテーマとするなら、それにふさわしい万博はどうあるべきかを改めて問い直せれば、日本のプレゼンスは相当評価されるでしょう。













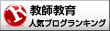



 </picture>
</picture>











コメントを書く
コメント(0件)