




年越蕎麦です
紅白なるとは彩りに
くわい 人参 蕗 大根 こいも
煮しめもできました
柚子をたっぷり入れたお風呂に入って 除夜の鐘を待ちます
今年もなんとか大晦日
さようなら 子(ね)の年 また12年後に





年越蕎麦です
紅白なるとは彩りに
くわい 人参 蕗 大根 こいも
煮しめもできました
柚子をたっぷり入れたお風呂に入って 除夜の鐘を待ちます
今年もなんとか大晦日
さようなら 子(ね)の年 また12年後に





大晦日のうちに三が日で使う具材は切って蓋付容器に準備しておきます
元旦早々に刃物を使わない一種の縁起担ぎです
里芋・牛蒡・人参・大根・水菜・蒲鉾は紅白 それから竹輪
鶏肉 昆布 鰹節などでだしをとり調味した汁で 野菜が柔らかくなったところで お餅を入れます
水菜は火を止める前に入れます





お煮しめに使った後の野菜やこんにゃくの端など小さく切って煮たモノ
人参・筍・鶏肉・牛蒡・こんにゃくなど 入っております
お煮しめの最後の汁で煮ます
味付けして煮た卵は食べやすいように 半分に切って





海老・牛蒡・筍・蓮根 味もよくしんで いい色に仕上がりました♪
味付けは父です
一つの野菜を煮るのに 始め 間 仕上げと 三度味付け致します
間の見張りと 取り上げて重箱に詰めるのが 私の仕事です
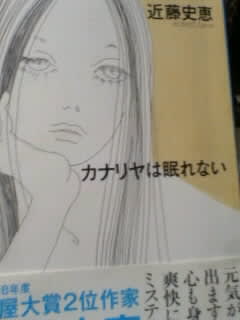

寝違えに悩む男と買い物依存症の女の接点は?
体に触れれば ピタリと判る男 整体師 合田力
何故か男と見れば一度は寝ないと気が済まない美女
可愛いのに食事の悩みがあるその妹
はっきりしない何かは・・・一つに繋がり・・・合田の慧眼により やがて思いもかけぬ 爽快なエンディングを迎える
近藤史恵さんは ひどく暗い話(そりゃあ救いようがないほどに)も書けば 読了して そうきましたか ふ~~~んと にやにやしたくなる話も書いてくれる
有栖川有栖氏の解説も楽しい
少し昔の作品ですが どうしてシリーズ化しなかったんだろ―と思うほど 合田先生も助手の美人姉妹も
小松崎クンも その同僚女性も魅力的です


父が娘に話す物語の形を借りて
「千姫と乳酪」
「九枚の皿」
「おすが」
「奥方行状記」
「献上牡丹」
「繁昌の法則」
「やせ男」
「本多様の大銀杏 」
解説は児玉清さん
こちらも楽しい




何をやっているかと言えば フライパン・サイズのデカ・ホットケーキを焼いています
これに林檎入りミルクセーキを添えて
半分おやつみたいなブランチです
何かの悪い冗談ではないのか
織田裕二を主役とした新しい話の時代劇ではいけなかったのか
観ながらそうした思いが強まっていった
この映画は 黒澤明監督 主演 三船敏郎のリメイクである
だが 時代劇に見えて来ない
三船敏郎はテレビでも峠 九十郎 など 素浪人役を演じた
三船敏郎の素浪人役は味があった
そこに立っているだけで 見る者を納得させる存在感があった
この新しい椿三十郎は―私にはどうしても時代劇に見えなかった
織田裕二が主演し これだけの俳優を使うのなら ならばこそ
何故 全く新しいオリジナルの物語ではいけなかったのだろう
とても残念に思う
むしろ敵役 豊川悦史が椿 三十郎 を演じていたらどうであったろうか などとさえ思う
藩内に悪玉善玉がいて 片方に味方することになった椿三十郎と名乗る凄腕の素浪人
敵方の強い侍との最後の対決
オリジナルの映画ではあちこちに見せ場と盛り上がりが・・・あった


江戸時代大阪にあってお嬢様と呼ばれる身分にありながら 世間並みの女としての生き方をしたくなかった女
恋をしたとて不器用で 男と添うて生きるほど見境なく惚れることはできず
自由に生きることは幸せであったのだろうか
好きに生きる―ということ
はたして?
どのように生きても寂しさ 哀しさからは 逃れられなかったのではあるまいか―と思ってしまう
いつの時代も世間から外れて生きるのは ラクではないから



黒豆さん
こんな感じにできました
煮込んで味がついた煮物
これに柚子の刻んだ皮混ぜて味付けした白味噌をちょこっと添えます


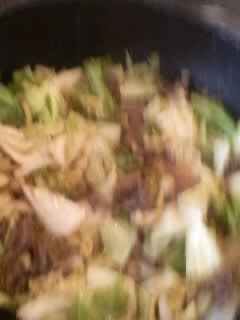


はや水仙の蕾が開きそうな感じになっていました
この花の香りが好きです
私の教わったお花の流派では 同じ花でもイリスや水仙などは 冬の間は花のついた茎は葉より低く内側になるように組み直して紐をかけまとめます
水仙の場合は下部に袴がついている時は それをそうっと外して被せ直します
夏の花の場合は 花を葉より長く組むのです
花に細い紐をかける時の先生の鮮やかな手さばきを 懐かしく思い出します
今朝は卵雑炊 里芋と大根の煮物
味味噌を作り田楽のように仕立てるつもりです
野菜炒め
あと黒豆を圧力鍋にかけました
数の子は塩抜きの水に漬けて
次は来年の干支の牛の置物を倉庫から出してくる予定です


「似せ者」名優 藤十郎そっくりの役者を二代目に仕立ててはみたが―与一の目論見外のことが起きるのだった
「狛犬」男は役者として力落ちる相手と二人ひと組な扱い 見られることに苛立ち―
「鶴亀」 一世一代の引退興行を幾度も繰り返す役者
振り回された男は笑うしかなくなる
「心残して」江戸から明治へ移る時代の狭間で人々は―
世の中には貧乏籤を引くしかない人間もいるけれど それはあながち不幸なことではないのかもしれない―と思えてくる一冊


「小日向源伍の終わらない夏」上司のわがまま息子により息子は身動きとれない体にされた
そのバカ息子が今度は自分の上司になる
彼の煩悶は―
「儚月」実在の人物と関わりある登場人物の鬱屈
「愚かもん」滝沢馬琴の妻は本当に愚妻だったのか
妻から見た馬琴とは
「捨てた女」信仰に入れあげる妻
女遊びの道楽息子
病を得た身で男は来し方を思う
捨ててきた女には 母親そっくりの娘があると言う
男は・・・気になった
「あの橋を渡って」 商いを広げよう大きくしようと頑張ってきた男
その耳に入れられた母のこと
彼が子供の頃 母親は男と逃げた
そして残された父親は首をつった
今 男は自分の人生を振り返る
人としての幸せ
周囲の人々のこと
彼は今まで気付かずきたことに気付かされる
母が橋を渡って来れない―そう言うなら 自分から橋を渡って迎えに行こうと・・・男は思うのだ
物語の中に派手な人間はいない
多分脇役に回るような人間を主役に据え 彼らの人生 懊悩を見せる





山口県の叔父から届きました
秋穂の河豚の刺身と車海老
今年は白ワインと塩で焼いてみました
長男は何と海老を殻ごと食べておりました




