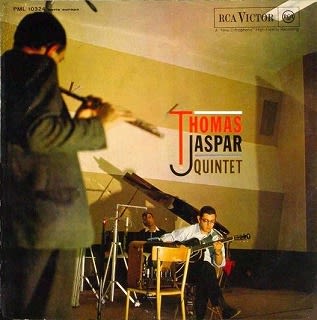■Gerry Mulligan & Art Farmaer Quartet Live In Rome 1959 (Impro-Jazz = DVD)
これまた先日ゲットしてきた発掘映像DVDのご紹介です。
主役はジェリー・マリガンがアート・ファーマーを相手役にしていた時期に敢行された欧州巡業から、ローマでのライブ映像をモノクロで約70分、じっくりと堪能出来ます。結論から言うと、カメラワークや照明が単調です。それでもステージのホリゾントに伸びたメンバーの影を撮ったり、いろいろと工夫は凝らされているのですが……。
しかし演奏は、なかなか充実しています。つまり画面を観ていると飽きるのが正直な気持ちなんですが、音だけ聞いている分には素晴らしい♪
収録されたのは1959年6月19日のローマ、メンバーはアート・ファーマー(tp)、ジェリー・マリガン(bs,p)、ビル・クロウ(b)、デイヴ・ベイリー(ds) という白黒混成のカルテットです――
01 Announcement By Gerry Mulligan
02 As Catch Can
03 Walking Shoes
04 Baubles, Bangles And Beads
05 Just In Time
06 I Can't Get Started
07 News From Blueport
08 Moonlight In Vermont
09 Spring Is Sprung
――上記の演目は淡々と進行していきますが、まずアート・ファーマーが右に首を傾げながらトランペットを吹く姿が、実になんともいえません。もちろん流麗なフレーズからは独自の歌心が溢れ出て止まらない感じですし、スーツの着こなしも正統派のジェントルな雰囲気が好ましいですね。
で、実際のライブは、ジェリー・マリガンの如何にも白人らしい落ち着いたユーモアもニクイほどのMC、スタート前のチューニングタイムも面白いと思います。
そしてアップテンポの「As Catch Can」、アート・ファーマーがチェット・ベイカーの代役を見事に務める「Walking Shoes」の2連発で、その場は完全にカルテットの支配下に置かれるムードですから、続く「Baubles, Bangles And Beads」のシンミリとして味わい深い世界が、尚更に心に染み入る展開が実に秋の夜長にジャストミート♪
あぁ、ジェリー・マリガンの歌心は本当に素敵ですねぇ~♪
ただし既に述べたように映像的な面白さに欠けるところは残念……。というか、このメンバーの地味な佇まいでは、そうなってあたりまえかもしれませんね。もちろんそれがシブイ、本当のカッコ良さという見方も出来ますが、個人的にはデイヴ・ベイリーの左後頭部にある五百円玉ほどのハゲが気になったりします。
肝心の演奏はジンワリとスタートしてグイノリに変化していく「Just In Time」がモダンジャズ王道の楽しさで、アート・ファーマーが歌心の塊のようなアドリブを披露すれば、ジェリー・マリガンはリズミックな絡みから豪放にして洒脱なフレーズの連なり、そしてオーバー気味のアクションで対抗します。ここはデイヴ・ベイリーのブラシもイブシ銀ですよっ♪
それとジェリー・マリガンは「I Can't Get Started」と「Spring Is Sprung」でピアノを弾きますが、その姿が実にカッコイイ! そのピアノスタイルも流麗ではありませんが、妙に個性的な響きが印象的です。まさに「味」の世界とでも申しましょうか♪
ですから「I Can't Get Started」ではアート・ファーマーのトランペットも柔らかな歌心が全開した名演だと思います。また不思議な和みが醸し出される「Spring Is Sprung」も4ビートの良さが満喫出来る演奏ですねぇ~♪ このあたりは映像を観て、はじめて納得出来るところでしょうから、このDVDのハイライトではないでしょうか。
収録の演奏では他にも彼等流儀のハードバップという「News From Blueport」やシンプルにメロディを追求してアドリブを極めんとする「Moonlight In Vermont」の完成度も高く、通して楽しめば決して派手さは無いものの、やはりモダンジャズの黄金期が楽しめると思います。
気になる画質は「B+」程度で、些かコントラストが強すぎる白黒フィルムの傷みも残念ですが、音質はバランスの良いモノラルミックスですから、繰り返しますが聴いているだけで満足されるでしょう。
その意味からでしょうか、ボーナストラックには音源だけで以下の2曲が入っています――
10 Blueport (imcomplete)
11 Utter Chaos
――いずれも同日の録音かと思われますが、「Blueport」は相当に熱いハードバップで、リズム隊のビシッとしたグループが気持ち良く、フロントの2人もノリまくっています。また「Utter Chaos」はバンドテーマの短い演奏ですが、メンバー紹介も兼ねているのでした。
ということで、これもマニア向けのブツでしょうね。しかし見つけたら最後、ゲットせずにはいられない「何か」を秘めています。個人的にそれは、あの1958年のニューポートジャズ祭のドキュメント映画「真夏の夜のジャズ」の夢よもう一度であり、その後に作られる永遠の超名盤「Night Lights (Mercury)」と同じ味わいを求めてしまうからなのですが……。
まあ、それはそれとして、やはりジャズメンはカッコイイ!