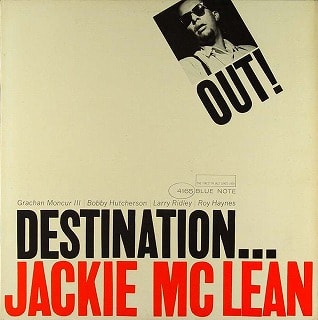■Rockin' The Boat / Jimmy Smith (Blue Note)
ジャズの名門インディーズ「ブルーノート」で一番、リアルタイムの売上に貢献したのはジミー・スミスとルー・ドナルドソンじゃないでしょうか。
もちろん今日に至る長期的なところでは、もっと他の名盤が多数売れているわけですが、自前のプレス工場を持たないマイナーレーベルはレコードのプレス代金は現金決済、しかし配給したレコードの代金回収は後払いなのが当時の常識でしたから、店頭で長期間、つまり店晒しになるような商品は、いくら質が高くても困り物でした。
というようなわけで、売れない商品はプレス枚数も少なく、直ぐに廃盤にしていった事情が窺い知れるのですが、これが売れ行きの良い人気スタアともなれば話は全くの逆で、他レコード会社からの引き抜きや契約更新時のトラブル等々、全く「インディーズはつらいよ」の世界です。
で、前述したジミー・スミスとルー・ドナルドソンの場合も例外ではなく、共に1950年代中頃からブルーノートに売り出してもらいながら、1963年を境にあっさりと他のレーベルへ移籍していくのです。
そしてこのアルバムは、その惜別のセッションともいうべき作品でしょうか……。
録音は1963年2月7日、メンバーはジミー・スミス(org)、クェンティン・ウォーレン(g)、ドナルド・ベイリー(ds) というレギュラートリオにルー・ドナルドソン(as) という目論見どおりの面々♪ そしてなんとジミー・スミスが去った後のブルーノートでは大黒柱のオルガン奏者となるジョン・パットンまでもがタンバリンで花を添えるという趣向になっています――
A-1 When My Dreamboat Comes Home
ゴスペルをカントリー&ウェスタンで煮しめたような、レイ・チャールズが十八番としている曲調が楽しい演奏です。軽いドドンパっぽいリズムのドラムス、ウキウキするリズムギターを仲間に引き入れたジミー・スミスは、ちょいと胸キュンのゴスペルメロディに執着したアドリブでホノボノさせられます。
もちろん途中から加わってくるルー・ドナルドソンは、得意のオトボケファンキー♪ 脱力して飄々としながら真っ黒なフレーズを吹きまくりです。
A-2 Pork Chop
一転して粘っこい、これぞブルース&ソウル♪ これも出だしから実に良い雰囲気が広がってきて、グッと惹き込まれます。しかし意外にも作者のルー・ドナルドソンは脂っ気もほどほどのアドリブという肩透かしがニクイところ♪ その分をジミー・スミスがフォローするという展開が「お約束」なのでした。
また、それを全てお見通しのギターとドラムスも流石ですねっ♪
A-3 Matilda, Matilda
まるっきりソニー・ロリンズが出てきそうなカリプソ調の演奏ですが、実はこのトボケた雰囲気は、ルー・ドナルドソンしか醸し出しえない楽しさです。3分ほどの短い演奏でフェードアウトするのが勿体ないですね。
B-1 Can Heat
これもイナタイR&Bがオトボケで味付けされた、往年の我が国ジャズ喫茶では噴飯物の演奏でしょう。気抜けのビールっぽいドナルド・ベイリーのドドンパドラムスにジョン・パットンとされるタンバリンが実際、ど~でもいいような雰囲気で……。
ジミー・スミスのオルガンも完全に脱力していますし、このあたりは意図的なんでしょうが、ダレダレのムードは賛否両論でしょう……。
所謂レイドバックした演奏は、後年のスワンプロックにも通じるものですが、ここではどうなんでしょう?
B-2 Please Send Me Someone To Love
そんな雰囲気をグッと真っ黒な世界に引き戻すのが、この演奏です。
曲はお馴染みのブルース歌謡ですから、粘っこくて思わせぶりなルー・ドナルドソンのテーマ吹奏、ツボを外さないジミー・スミス・トリオの伴奏は完全に出来上がった状態で、まさにソウルフル♪
そしてアドリブパートではジミー・スミスのアグレッシブでブル~~~スなオルガンが炸裂し、これぞっ、涙が流れるままの名演を聞かせてくれます。
B-3 Just A Closer Walk With Thee
これもせつなくて、しかし妙に楽しい有名なゴスペル曲ですから、このメンバーにはジャストミートの演目でしょう。実際、このイナタイ雰囲気は、かけがえのないグルーヴを醸し出し、しかもそれが自然体という感じで好感が持てます。
ドドンパのドラムスと井上順に引き継がれるようなリードタンバリンが、最高ですねぇ~♪ 真っ昼間からワインを飲み過ぎたようなルー・ドナルドソン、下半身に力が入らないようなジミー・スミス、眠たいようなリズムギターの妙が渾然一体となって、これもモダンジャズの楽しさのひとつという心地良さです。
B-4 Trust In Me
そして最後に置かれたのが、シンミリと胸キュンの名曲・名演です。ルー・ドナルドソンの艶やかなアルトサックスと低音重視のオルガン伴奏が、最高にしっくりと馴染んだテーマメロディの素晴らしさ♪ もう最高です。
もちろんジミー・スミスのオルガンアドリブには、過激さと和みが同居する十八番の展開が聞かれますし、短めの演奏ですが、まさにハードボイルド小説のラストシーンのようなドライな感傷が……。ベタベタの甘さに流れる寸前の忍び泣きには心底、シビレます。
ということで、冒頭では「惜別のセッション」なんて書きましたが、聴いてみれば、演じているミュージシャンにはそれほどの感慨や気負いがあったとは感じられません。肩の力の抜け具合が実に良い感じで、和みます。
ちなみにジミー・スミスは以降、ヴァーヴへ移籍して、より大衆的な人気を得るわけですが、一方のルー・ドナルドソンもアーゴと契約して、ますますお気楽な路線を歩むことになります。
そうした経緯から、真っ向勝負のリアルジャズが好まれる我が国では些か軽い扱いとなる2人ですが、道こそ違え、やっていた事は当時の最先端に違いありません。
しかし今更言うまでもなく、ジャズは楽しいもんなんですよねっ♪ このアルバムを軽く楽しんだって、バチはあたらないでしょう。