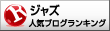筆者がギターを始めたのは1975年、中学に入学した頃だったと記憶する。音楽の授業でクラシック・ギターを弾いて興味を持ったのがきっかけ。同じ頃親にクラシック・ギターを買ってもらった。中2になるとクラスにフォーク・ギターを弾く友人がいて、クラシックとはまったく違うキラキラした音色に憧れた。下敷きを切ってピック代わりにして、クラシック・ギターにナイロン弦ではなくフォーク・ギター用のスチール弦を張ってジャカジャカ弾いていた。『GUTS(ガッツ)』というギター教則雑誌を買った。載っているのは日本のフォーク・ナンバーばかり。当時フォーク歌手がテレビの歌番組に出演することは殆どなかったので、知っている曲は「シクラメンのかほり」とクラスの友人が歌っていた「青空一人きり」しかなかった。それでもコードを覚えたり、アルペジオの練習をするのは楽しかった。ラジオで聴いたアメリカのフォーク歌手ジョン・デンバーが好きだったので、いつかマーチンの12弦ギターを買おうと決心した。
布施明 - シクラメンのかほり - 1975
しかし徐々にフォークよりもロックに興味が移り、エレキギターが欲しくなった。当時住んでいた石川県金沢市の楽器店にはエレキギターは余り置いていなかったが、なぜかスチールギターは何処の楽器店でも扱っていた。たぶんハワイアンやカントリー音楽を習う年配の音楽ファンが多かったのだろう。それでもギターのカタログを集めて眺めていた。中2の誕生日プレゼントにエレキギターが欲しかったが、その頃はまだ「エレキは不良の楽器」というイメージがほんの少し残っていたので、結局言い出せなかった。好きなアーティストはジョン・デンバーからビーチ・ボーイズ、そしてキッス、エアロスミスからジェネシスへと広がっていった。1977年中3に進級する時に金沢から東京練馬区へ引っ越した。東京にはレコード屋や楽器店がたくさんあり、特に自転車で15分の吉祥寺には輸入盤や中古盤のレコード店が幾つもあった。
Song 1 Kiss Alive II Detroit Rock City - APR.2,1977 "BUDOKAN HALL"
前年の1976年から音楽雑誌を中心に紹介されていたパンクロックが、この年には新聞や一般の雑誌でも一種の社会現象として取り上げられるようになり、FMを中心にラジオでもかかるようになった。特にセックス・ピストルズやクラッシュ、ストラングラーズなどロンドン・パンクがセンセーショナルな話題をまいたが、筆者はテレヴィジョンやリチャード・ヘルといったニューヨーク・パンクも好きだった。とは言ってもギタリストとしてはジョニー・ウィンターが最も好きだったので、自分の小遣いを貯めて中学卒業プレゼントとして買ったのはグレコのファイアーバード・モデルだった。
The Clash - White Riot (Official Video)
Johnny Winter - SUZIE Q (Live at Rockpalast)
高校へ進学し1年間はブラスバンドに精を出したが、春休みにヨーロッパ旅行へ行きロンドンの空気を吸ったことでパンクへの想いが募り、高2に進級すると高校の友人を集めてパンクバンド「GLANDES(グランディーズ、亀頭)を結成した。その頃高校内で流行っていたのはニューミュージックやフォークソングばかり。学園祭の最後の日の後夜祭のエンディングは学園祭実行委員やクラス委員が全員ステージに上がってチューリップの『心の旅』を合唱した。「あー、だから今夜だけは君を抱いていたい〜」と歌う脳天気な連中に対して、「I am an Anti-Crist, I am an Anarchist(俺は反キリスト、俺は無政府主義者)」とか「We are all Prostitute(俺たちはみんな娼婦だ)」とがなり立ててぶち壊してやりたい、という欲求が沸き上がってきた。世の中の反乱分子=パンクスの筆者たちにとって軟弱なフォーク野郎は粉砕すべき敵であり「フォーク」と名のつくものは悉く生理的に毛嫌いしていた。
チューリップ 心の旅 1972
The Sex Pistols - Anarchy In The U.K (official video)
The Pop Group - We Are All Prostitutes (Official Video)
一例として、自分史の中で有名な「ゴジラレコード不買事件」というエピソードを紹介しよう。既に何度かブログに書いたので「またこの話か」と呆れる読者もいるかもしれないが、ほんの少しお付き合いいただければ幸いである。
78年〜79年頃愛読していた音楽雑誌『Player プレイヤー』に日本のパンク最初の自主(インディ)レーベル「ゴジラレコード」の紹介記事が掲載された。レビューではなくニュース欄の小ネタだった。そこにはレーベル最初の2枚ミラーズとミスター・カイトのシングルを紹介するにあたってフォーク歌手の泉谷しげるを引合にだして書かれていた。フォーク嫌いの筆者にとってはフォーク歌手と比較されることだけで生理的に「×」だった。吉祥寺の輸入盤店ジョージ・ジュニアでこれらのシングル盤を見つけたが、買う気にはなれなかった。恐らく記事を書いたライターのボキャブラリーには泉谷しげるしかなかったのかもしれない。少なくともパンタと書いてあれば、今となっては貴重盤のこの2枚をリアルタイムで聴けただろう。ゴジラレコードを買うのは3作目のツネマツマサトシの如何にもパンクなジャケットからだった。
Mirrors - 衝撃X (1979)
Tsunematsu Masatoshi - き・を・つ・け・ろ
大学へ入学したのは82年で、音楽サークルはフュージョン全盛だった。そこで筆者にとっての敵の音楽は「フュージョン」に転化した。大学入試で訪れた京都の十字屋というレコード店でザ・シーズのLPを購入したことがきっかけで、60年代サイケデリック・ロックにハマり、ザ・バーズをはじめとするフォークロックやディノ・ヴァレンテやティム・バックリーといったアシッド・フォークや早川義夫や浅川マキ、友川カズキや三上寛など日本のアンダーグラウンド・フォークも聴くようになったが、所謂四畳半フォークやニューミュージックが興味の対象になることは殆どなかった。
THE SEEDS flower lady and her assistant 1967
The Byrds - Turn! Turn! Turn! (Live)
以上、長々と書いてきたのは「フォークは敵」と聴かず嫌いした筆者が最近になって日本のフォーク(の一部)を好んで聴くようになった背景を紹介する為であった。この連載では、筆者如何にして軟弱・日和見主義と思って接してきたアコギ中心の軽音楽の中から、感性に訴えかけるアーティスト/曲を見つけ出し、紹介していきたいと考えている。100フォークス(One Hundred Folks)とは、70年代ロンドン・パンクのキッチュさを象徴するバンド・ジェネレーションXの「100パンクス (One Hundred Punks)」になぞらえた呼称だが、中古レコード店の100円コーナーでよく見かけることも仄めかしている。興味を持った方は埃臭いレコードの墓場を掘り起こしてみてはいかがだろうか。
generation x - one hundred punks
なよなよしたフォークソングを聴きながら自分語りを書き連ねたが、夜は更け明日は仕事がある。ここらでペンを置き、この続きは次回以降に譲ることとしたい。
四畳半
今の家には
ありません