検証アベノミクス⑤ 異次元の金融緩和④ 大銀行に利益 地銀に圧迫
日銀のマイナス金利政策で銀行の経営が圧迫されるといわれます。しかし、マイナス金利の導入で国債価格が上昇しています。国債を大量に保有する大銀行は含み益を増やし、売却益で利益を得ています。
日銀に国債売却
日銀は「異次元の金融緩和」で長期国債の保有残高が年間80兆円増加するよう買い入れを進めています。政府が新しく発行した国債は大手金融機関に入札で販売されますが、落札された国債はすぐに日銀が買い取っていきます。2015年度は新規発行国債の8割を日銀が市場から買い取ってしまいました。
元日銀副総裁の岩田一政日本経済研究センター理事長は次のように指摘しています。
「国債を売る側の民間銀行からすると、どんなに価格が高くても買ってくれるので、当座預金におくマイナス0・1%部分と比較して、日銀トレードから得られる収益のほうが大きいと思えば、国債を売るインセンティブが働く。大量の国債を保有している金融機関にとっては、マイナス金利による評価益を実現益に変える機会にもなる」(『週刊金融財政事情』3月7日号)
3メガバンクグループの国債保有は、三菱UFJ30兆円、三井住友16兆円、みずほ15兆円(2015年9月末時点残高)にのぼります。これが値上がりするのですから、大銀行に利益が転がり込むことになります。
加えて、大銀行は近年、海外業務を拡大しています。マイナス金利が銀行収益に打撃を与えるとみるSMBC日興証券のアナリスト、佐藤雅彦氏も「3メガバンクは、国内資金利益以外の寄与も大きいため、銀行セクターのなかで相対的に減益幅は小さいであろう」
(同誌)と分析しています。その一方、「(マイナス金利による)減益を相殺できる要因があるかによって、増減益が決まってくる」とし、地銀の17年度3月期の業績は「軒並み2割以上の減益となろう」と予測します。
銀行の本業は預金を集めて企業・個人に貸し出し、利ざやで利益を得ることです。しかし、異次元緩和による金利低下はその利ざやを縮小させ、マイナス金利はそれに拍車をかけます。民間シンクタンク、日本総研が1月に発表したリポートによると、貸出金利息を中心とした銀行の国内資金利益は10年度から14年度にかけて10%減少しました。
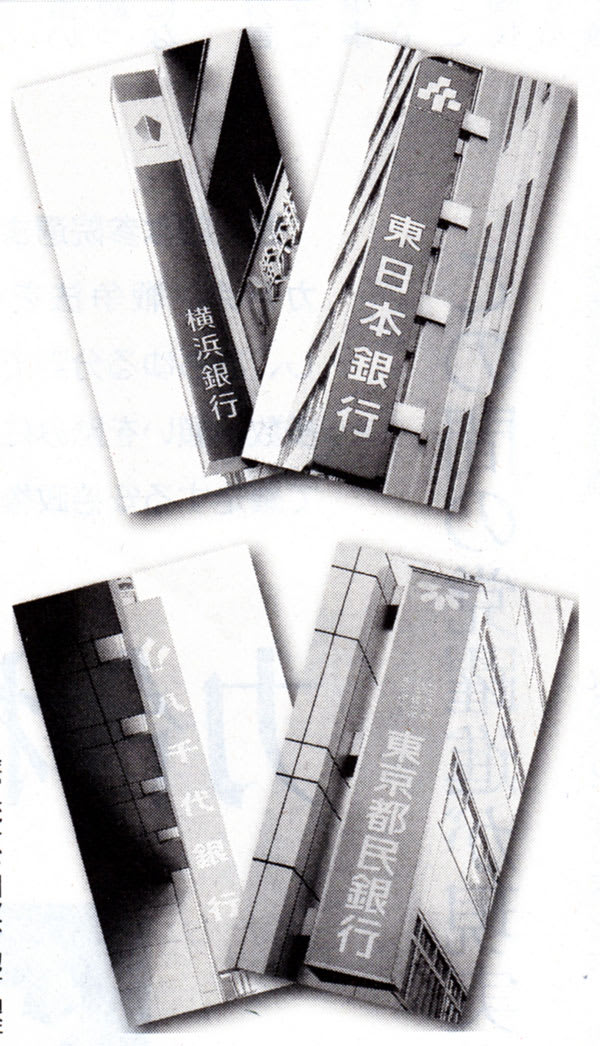
経営統合が相次ぐ地方銀行
中小には回らず
しかも14年4月の消費税増税は消費を冷え込ませ、「増税不況」をもたらしています。国内需要が増えないもとでは中小企業の資金需要も増えません。メガバンクの中小企業等向け貸出金の比率は3メガ体制発足以来、最低の水準です。
「都銀は大企業取引や非金利ビジネス、海外業務などに軸足を移しつつあるなか、中小企業向け貸し出しを積極的に増やすことをせず、結果的に地銀がこれを補う形となっている」と日本総研は指摘します。
政府は地方銀行の整理・統合を進めており、異次元緩和やマイナス金利で地銀の経営が圧迫されることで「再編」が加速されるとみられます。中小企業に密着した金融機関が淘汰(とうた)されることになります。年度初めの1日には東京TYと新銀行東京のほか、横浜銀行と東日本銀行、トモニホールディングスと大正銀行など経営統合が相次ぎました。
異次元緩和もマイナス金利も、市場の金利を下げれば民間銀行の貸し出しが増え、実体経済が活発になるとの触れ込みで行われましたが、緩和マネーは中小企業貸し出しに回っていません。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2016年4月9日付掲載
銀行の本業は預金を集めて企業・個人に貸し出し、利ざやで利益を得ること…。
低金利のもとで、大銀行は、国債を売ったり海外で稼ぐ。
中小金融機関はそれもできず、苦境にたたされています。
日銀のマイナス金利政策で銀行の経営が圧迫されるといわれます。しかし、マイナス金利の導入で国債価格が上昇しています。国債を大量に保有する大銀行は含み益を増やし、売却益で利益を得ています。
日銀に国債売却
日銀は「異次元の金融緩和」で長期国債の保有残高が年間80兆円増加するよう買い入れを進めています。政府が新しく発行した国債は大手金融機関に入札で販売されますが、落札された国債はすぐに日銀が買い取っていきます。2015年度は新規発行国債の8割を日銀が市場から買い取ってしまいました。
元日銀副総裁の岩田一政日本経済研究センター理事長は次のように指摘しています。
「国債を売る側の民間銀行からすると、どんなに価格が高くても買ってくれるので、当座預金におくマイナス0・1%部分と比較して、日銀トレードから得られる収益のほうが大きいと思えば、国債を売るインセンティブが働く。大量の国債を保有している金融機関にとっては、マイナス金利による評価益を実現益に変える機会にもなる」(『週刊金融財政事情』3月7日号)
3メガバンクグループの国債保有は、三菱UFJ30兆円、三井住友16兆円、みずほ15兆円(2015年9月末時点残高)にのぼります。これが値上がりするのですから、大銀行に利益が転がり込むことになります。
加えて、大銀行は近年、海外業務を拡大しています。マイナス金利が銀行収益に打撃を与えるとみるSMBC日興証券のアナリスト、佐藤雅彦氏も「3メガバンクは、国内資金利益以外の寄与も大きいため、銀行セクターのなかで相対的に減益幅は小さいであろう」
(同誌)と分析しています。その一方、「(マイナス金利による)減益を相殺できる要因があるかによって、増減益が決まってくる」とし、地銀の17年度3月期の業績は「軒並み2割以上の減益となろう」と予測します。
銀行の本業は預金を集めて企業・個人に貸し出し、利ざやで利益を得ることです。しかし、異次元緩和による金利低下はその利ざやを縮小させ、マイナス金利はそれに拍車をかけます。民間シンクタンク、日本総研が1月に発表したリポートによると、貸出金利息を中心とした銀行の国内資金利益は10年度から14年度にかけて10%減少しました。
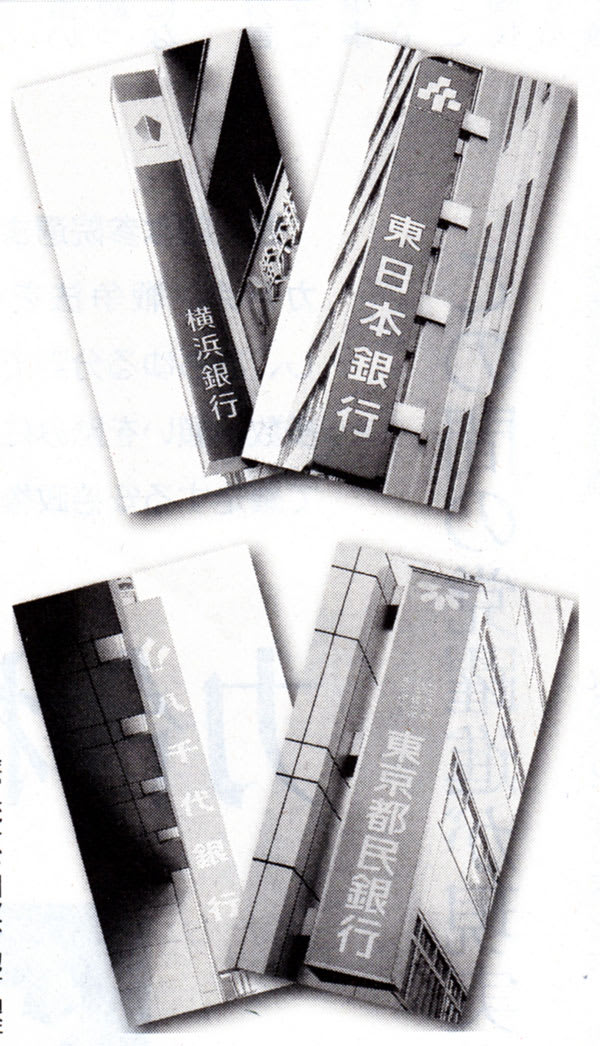
経営統合が相次ぐ地方銀行
中小には回らず
しかも14年4月の消費税増税は消費を冷え込ませ、「増税不況」をもたらしています。国内需要が増えないもとでは中小企業の資金需要も増えません。メガバンクの中小企業等向け貸出金の比率は3メガ体制発足以来、最低の水準です。
「都銀は大企業取引や非金利ビジネス、海外業務などに軸足を移しつつあるなか、中小企業向け貸し出しを積極的に増やすことをせず、結果的に地銀がこれを補う形となっている」と日本総研は指摘します。
政府は地方銀行の整理・統合を進めており、異次元緩和やマイナス金利で地銀の経営が圧迫されることで「再編」が加速されるとみられます。中小企業に密着した金融機関が淘汰(とうた)されることになります。年度初めの1日には東京TYと新銀行東京のほか、横浜銀行と東日本銀行、トモニホールディングスと大正銀行など経営統合が相次ぎました。
異次元緩和もマイナス金利も、市場の金利を下げれば民間銀行の貸し出しが増え、実体経済が活発になるとの触れ込みで行われましたが、緩和マネーは中小企業貸し出しに回っていません。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2016年4月9日付掲載
銀行の本業は預金を集めて企業・個人に貸し出し、利ざやで利益を得ること…。
低金利のもとで、大銀行は、国債を売ったり海外で稼ぐ。
中小金融機関はそれもできず、苦境にたたされています。











