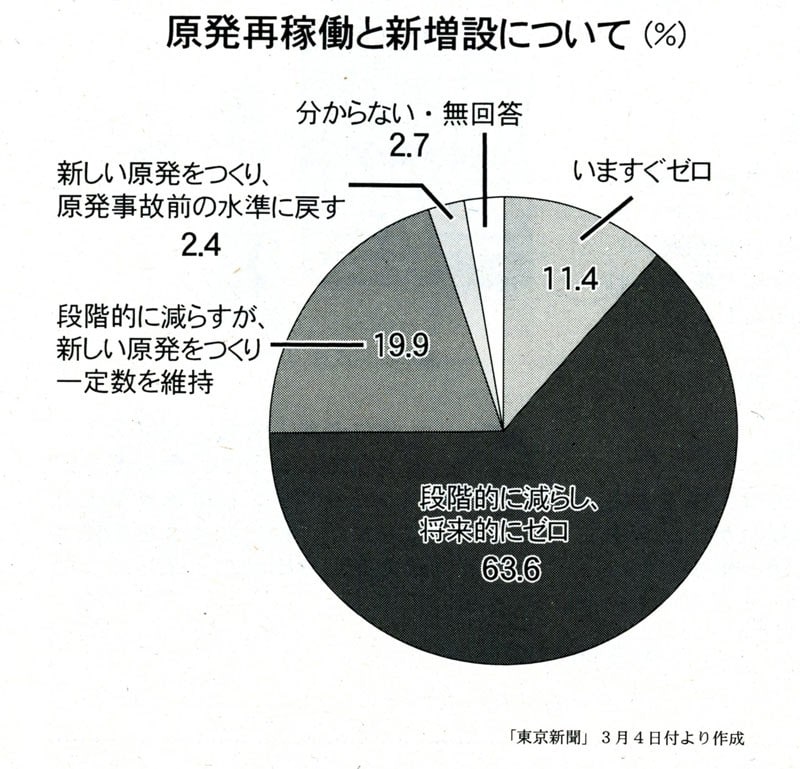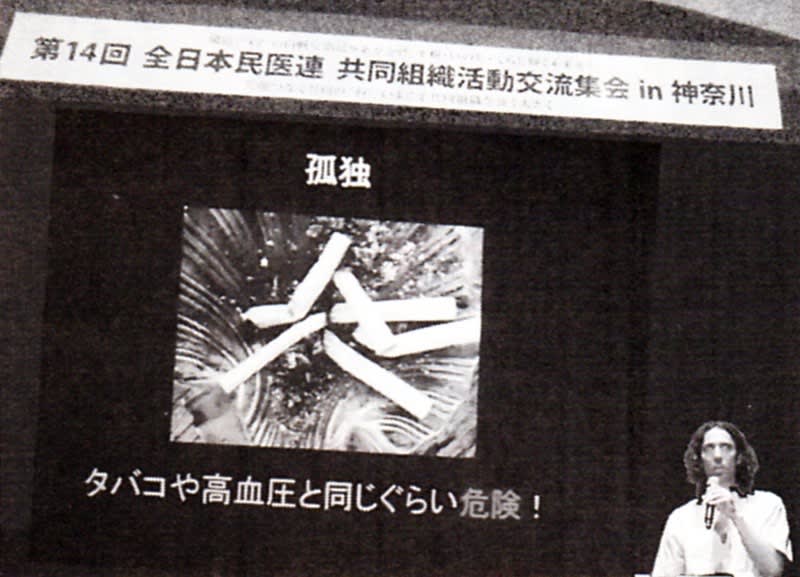“浄化”汚染水の基準値越え放置 福島第一原発 問われる東電・国の責任
東京電力福島第1原発の高濃度の放射能汚染水を処理設備で“浄化”したはずの水の約8割に、トリチウム(3重水素)以外の放射性物質が国の放出基準(告示濃度限度)を超えて残っていることが明らかになりました。処理済み水の処分方法をめぐる公聴会では海洋放出に反対する声が多数を占め、国の会議でも東電への批判が相次ぎました。国と東電の倫理観が問われています。(唐沢俊治)
「思ったより、告示濃度を超えているものが多い」「詳細な説明は初めてだ」
10月、処理水の取り扱いを議論している経済産業省の小委員会で、タンク内の処理水の放射性物質濃度について説明する東電の担当者に対し、厳しい指摘がありました。

増え続ける放射能汚染水をためるため、敷地に林立するタンク=東京電力福島第1原発
トリチウムとは
トリチウム(3重水素)は、水素の放射性同位体で、半減期は約12.3年。汚染水中の水分子の水素がトリチウムと置き換わった状態で存在し、除去は困難です。
トリチウムは、通常の原子力施設でも発生し、福島第1原発では事故前、年間約2兆ベクレルを放出していました。経済産業省のまとめによると、現在タンクで保管する汚染水に含まれるトリチウム量は、約1000兆ベクレル。事故前の年間放出の約500倍に相当します。
増え続ける汚染水
福島第1原発の汚染水は1日当たり百数十~二百数十トン増え続けています。建屋地下の滞留水やタンクにためている汚染水は10月時点で合計約117万トン(うちアルプス処理水は96万トン)。タンクを増設する敷地の確保が困難になっているとして、東電はタンク建設計画を2020年末(総容量約137万トン)までしか示していません。
国の汚染水処理対策委員会の作業部会は2016年、汚染水の処分をめぐり、①地層注入②海洋放出③水蒸気放出④水素放出⑤地下埋設―の各方法について、技術・コスト面から評価。現在、小委員会で、風評被害などの観点から処分方法を議論しています。
都合良いデータを列挙
2万倍タンクも
発生し続けている汚染水は、多核種除去設備(アルプス)で処理しタンクにためています。アルプスは、トリチウム以外のセシウム137やストロンチウム90など計62種の放射性物質を基準未満まで除去できると、東電は説明してきました。
小委員会は当然、処理水に含まれるのはトリチウムだけであることを前提に処分方法を議論していました。
ところが小委員会で東電は、タンク群約89万トン(8月時点)のうち約75万トンの処理水で、トリチウム以外の放射性物質が基準を上回るという推定結果を明らかにしたのです。ストロンチウム90が基準の約2万倍となる、1リットル当たり約60万ベクレル含まれているタンク群もありました。
基準超えの原因について東電は、アルプス稼働初期の不具合、処理を急いで放射性物質の吸着材を交換しなかったことによる性能低下をあげました。
東電は、基準超えの処理水があると当初から知りながら説明せず、国も事態を放置してきました。それどころか2016年11月の小委員会の初会議で示した説明資料では、セシウム137、ストロンチウム90、ヨウ素129などの放射性物質は「ND」(検出限界値以下)などと、実態とかけ離れた都合の良いデータを並べていたのです。
実際には東電が10月に公開したデータで、基準の25万倍以上になる1リットル当たり約756万ベクレルのストロンチウム90を検出した処理水があったことが分かりました。
東電は、基準超えを説明しなかった理由を「東電と委員との関心、問題意識の差」と述べるなど、あまりにも当事者意識のない態度を見せました。委員の関谷直也東京大学准教授は「国民への説明として、倫理的に問題はなかったと考えているのか」と厳しく批判しました。

事実上の隠蔽に
東電福島第1廃炉推進カンパニーの小野明プレジデントは10月25日の記者会見で「隠蔽(いんぺい)というより、情報の出し方、伝え方に大きな問題があった」と述べましたが、事実上の隠蔽だとの批判は免れません。
野口邦和・元日本大学准教授(放射線防護学)は「何十年も続く廃炉作業では、地元住民や国民との信頼関係が非常に重要だ。東電は、やれることをやらずに、信頼関係を損なうことを自ら招いた」と批判。処理水の扱いについても「とても処分できる状況ではない。当面はタンクで保管するしかない」と言います。
基準超えが表面化した直後の8月に、小委員会が福島と東京で開いた一般の人の意見を聞くための公聴会は「議論の前提が崩れた」として紛糾しました。発言した市民らの圧倒的多数は、海洋放出反対や安全性に疑問があり慎重に対応すべきだとの意見でした。石油備蓄用の大型タンクでの長期保管も選択肢に加えることを求める意見が出ました。
漁業の打撃心配
福島県漁連の野崎哲会長は、「風評の払拭(ふっしょく)には想像を絶する精神的、物理的な労苦を伴うことを経験した」と強調。海洋放出されれば「福島県漁業に致命的な打撃を与える」と訴えました。
汚染水について「状況はコントロールされている」という安倍晋三首相の主張もむなしく、政府はタンク中の汚染水の放射性物質濃度さえも把握できていませんでした。事故を起こした東電は、柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働を進めるのではなく、被害賠償や廃炉作業に向き合うべきです。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年11月19日付掲載
トリチウムの半減期は短いとはいえ12.3年。海洋放出など許されません。
しかも、取り除かれていたとされる核種・ストロンチウムなどが残っていたのですから…
東京電力福島第1原発の高濃度の放射能汚染水を処理設備で“浄化”したはずの水の約8割に、トリチウム(3重水素)以外の放射性物質が国の放出基準(告示濃度限度)を超えて残っていることが明らかになりました。処理済み水の処分方法をめぐる公聴会では海洋放出に反対する声が多数を占め、国の会議でも東電への批判が相次ぎました。国と東電の倫理観が問われています。(唐沢俊治)
「思ったより、告示濃度を超えているものが多い」「詳細な説明は初めてだ」
10月、処理水の取り扱いを議論している経済産業省の小委員会で、タンク内の処理水の放射性物質濃度について説明する東電の担当者に対し、厳しい指摘がありました。

増え続ける放射能汚染水をためるため、敷地に林立するタンク=東京電力福島第1原発
トリチウムとは
トリチウム(3重水素)は、水素の放射性同位体で、半減期は約12.3年。汚染水中の水分子の水素がトリチウムと置き換わった状態で存在し、除去は困難です。
トリチウムは、通常の原子力施設でも発生し、福島第1原発では事故前、年間約2兆ベクレルを放出していました。経済産業省のまとめによると、現在タンクで保管する汚染水に含まれるトリチウム量は、約1000兆ベクレル。事故前の年間放出の約500倍に相当します。
増え続ける汚染水
福島第1原発の汚染水は1日当たり百数十~二百数十トン増え続けています。建屋地下の滞留水やタンクにためている汚染水は10月時点で合計約117万トン(うちアルプス処理水は96万トン)。タンクを増設する敷地の確保が困難になっているとして、東電はタンク建設計画を2020年末(総容量約137万トン)までしか示していません。
国の汚染水処理対策委員会の作業部会は2016年、汚染水の処分をめぐり、①地層注入②海洋放出③水蒸気放出④水素放出⑤地下埋設―の各方法について、技術・コスト面から評価。現在、小委員会で、風評被害などの観点から処分方法を議論しています。
都合良いデータを列挙
2万倍タンクも
発生し続けている汚染水は、多核種除去設備(アルプス)で処理しタンクにためています。アルプスは、トリチウム以外のセシウム137やストロンチウム90など計62種の放射性物質を基準未満まで除去できると、東電は説明してきました。
小委員会は当然、処理水に含まれるのはトリチウムだけであることを前提に処分方法を議論していました。
ところが小委員会で東電は、タンク群約89万トン(8月時点)のうち約75万トンの処理水で、トリチウム以外の放射性物質が基準を上回るという推定結果を明らかにしたのです。ストロンチウム90が基準の約2万倍となる、1リットル当たり約60万ベクレル含まれているタンク群もありました。
基準超えの原因について東電は、アルプス稼働初期の不具合、処理を急いで放射性物質の吸着材を交換しなかったことによる性能低下をあげました。
東電は、基準超えの処理水があると当初から知りながら説明せず、国も事態を放置してきました。それどころか2016年11月の小委員会の初会議で示した説明資料では、セシウム137、ストロンチウム90、ヨウ素129などの放射性物質は「ND」(検出限界値以下)などと、実態とかけ離れた都合の良いデータを並べていたのです。
実際には東電が10月に公開したデータで、基準の25万倍以上になる1リットル当たり約756万ベクレルのストロンチウム90を検出した処理水があったことが分かりました。
東電は、基準超えを説明しなかった理由を「東電と委員との関心、問題意識の差」と述べるなど、あまりにも当事者意識のない態度を見せました。委員の関谷直也東京大学准教授は「国民への説明として、倫理的に問題はなかったと考えているのか」と厳しく批判しました。

事実上の隠蔽に
東電福島第1廃炉推進カンパニーの小野明プレジデントは10月25日の記者会見で「隠蔽(いんぺい)というより、情報の出し方、伝え方に大きな問題があった」と述べましたが、事実上の隠蔽だとの批判は免れません。
野口邦和・元日本大学准教授(放射線防護学)は「何十年も続く廃炉作業では、地元住民や国民との信頼関係が非常に重要だ。東電は、やれることをやらずに、信頼関係を損なうことを自ら招いた」と批判。処理水の扱いについても「とても処分できる状況ではない。当面はタンクで保管するしかない」と言います。
基準超えが表面化した直後の8月に、小委員会が福島と東京で開いた一般の人の意見を聞くための公聴会は「議論の前提が崩れた」として紛糾しました。発言した市民らの圧倒的多数は、海洋放出反対や安全性に疑問があり慎重に対応すべきだとの意見でした。石油備蓄用の大型タンクでの長期保管も選択肢に加えることを求める意見が出ました。
漁業の打撃心配
福島県漁連の野崎哲会長は、「風評の払拭(ふっしょく)には想像を絶する精神的、物理的な労苦を伴うことを経験した」と強調。海洋放出されれば「福島県漁業に致命的な打撃を与える」と訴えました。
汚染水について「状況はコントロールされている」という安倍晋三首相の主張もむなしく、政府はタンク中の汚染水の放射性物質濃度さえも把握できていませんでした。事故を起こした東電は、柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働を進めるのではなく、被害賠償や廃炉作業に向き合うべきです。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2018年11月19日付掲載
トリチウムの半減期は短いとはいえ12.3年。海洋放出など許されません。
しかも、取り除かれていたとされる核種・ストロンチウムなどが残っていたのですから…