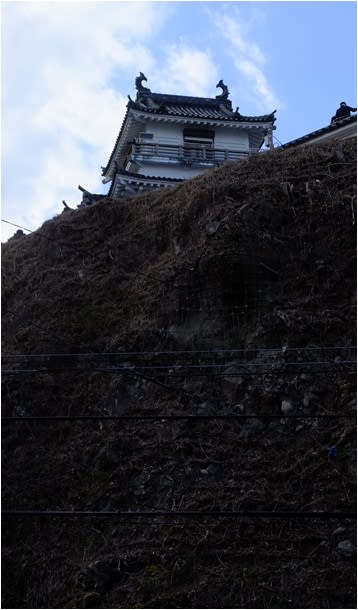杵築城下町 ひいなめぐり
南台武家屋敷から 東の鼻にある天守に移動
天守より 海側の浜を埋め立てた所のお店で
お寿司と桜餅を食べて
八坂川河口に架けられた橋を 徒歩徒歩した
⇒⇒⇒ トホトホ ⇒⇒⇒
16:49
日は長くなったとは言え 夕方
もう 色温度が低く 青みが強い
が 補正無しで
もうちょっと 一階層まで見えるくらい
木を伐りたいですね
でも 上だけを伐るのは ムリですしね
白漆喰が青い
飛ばした方がよかったか?
雲 空を 写しこむには 露出差が違う…
夕焼けも 期待できそうにないし…
そう思いながら トホトホ
天守上空に 穴が!
私の腕では こんくらいが 精一杯
ムクドリの大群でも 来てくれなくては
風雲急を告げる
ならぬでござ~る
天守 が消した 崖下
まだ 橋の袂 渡ってません
こちら側は 断崖完全伐採
天晴でござ~る
あまり 崖下過ぎて 天守最上階がやっと
橋の上からならば
渡りましょ
🕶 ダーダーダー
崖の上に 天守
崖が見えるように
崖に露出合わせる
ナバロンの要塞 よりは 楽勝
こっちからは 完全に上が有利ね
橋 渡り始めた位置から
二階の 大破風が見えてきました
崖は 落石防護ネット 張ってますね
最終的にモルタル吹き付けまでするのかも
往時は 無かった 橋の上から
別府方面
かすかに 天使のはしご
遠景の山 中央やや左の 高いのが 鶴見岳(活火山)
その左の先が 湯布院方面
鶴見岳右下の 枯草△に見えるのが 扇山
その右の 枯草が 十文字原演習場
中央の山の先に 🎡 ハーモニーランド
もうちょと ひいて 右の山の向こうが 宇佐方面
今年は 久々に 宇佐神宮にも 参ろうぞ!
ここから こんな風に見えるの知りませんでした
この橋を 徒歩で渡ったのは 初めて ヨカッタ
橋も 真ん中手前辺り まで渡ったところで
カッコいいじゃないですかっ!
模擬天守なんで こうじゃなかったですが…
最上階は 望楼で 外を廻れます
向こう側も 木を伐採してしまう計画かも
後半につづく~