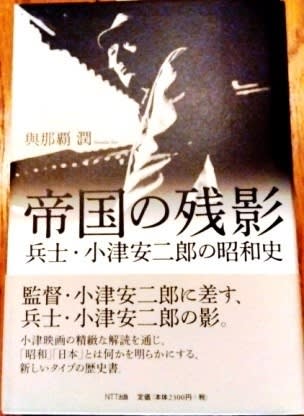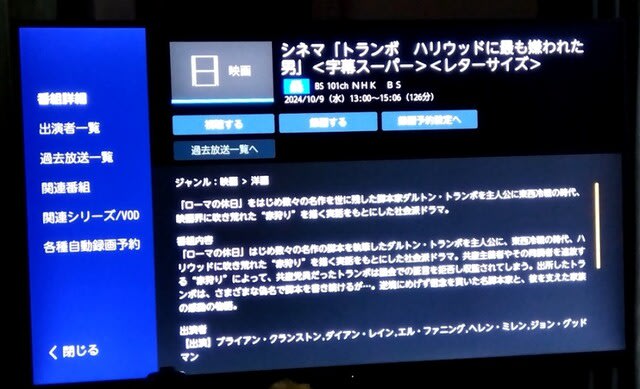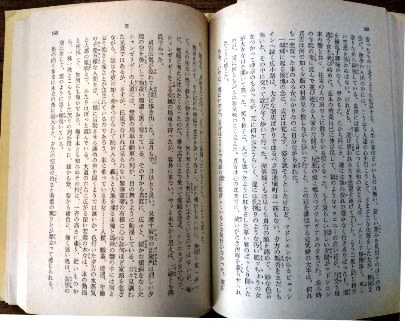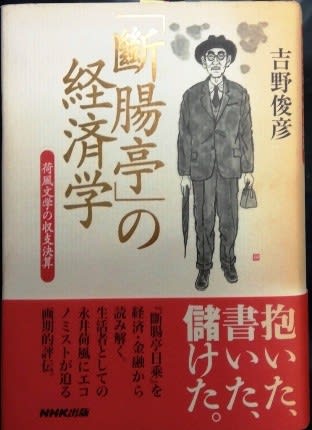與那覇 潤「帝国の残影――兵士・小津安二郎の昭和史」(NTT出版、2011年)を読んだ。
先日、旧北国街道、海野宿にドライブした際に、街道沿いの古書店で買ったもの。「古本カフェのらっぽ」という店だったらしい。「らっぽ」とはどういう意味か、店主に聞いておけばよかった。
さて、読んでみると、これが大変に面白かった。小津の映画をこんな風に読む(見る)こともできるのかと思い知らされながら読んだ。
小津はあの戦争(日中戦争ないしアジア太平洋戦争)を兵士として体験しながら、あの戦争を描かなかった監督といわれてきたし、ぼくもそう思っていた。しかし著者によれば、小津は、明治期から日中、太平洋戦争の敗北にいたる(大日本)「帝国の残影」を描きつづけた映画監督だったという。最も「日本」的といわれ、戦争描写の欠落した「家族映画」といわれる小津映画の中に、東アジアに植民地を有する「帝国」だった日本の歴史が反映されており、一兵士としての小津の中国大陸における経験がいかに影響していたかを著者は析出する。
しかも著者は、このことを小津の失敗作といわれる(シネマ旬報の順位の低かった)作品の系譜をたどる中から論証していく。すなわち、「風の中の雌雞」(1948年、キネマ旬報7位)、「宗方姉妹」(1950年、同7位)、「お茶漬けの味」(1952年、同12位)、そしてシネ旬の順位が最低だった「東京暮色」(1957年、同19位)などの諸作品である(26頁~)。
「戸田家の兄妹」で、二男の佐分利信が、長男・長女夫婦らに冷遇されている母と妹を連れていく先が実際には(画面でも脚本でも)「天津」なのに、多くの小津映画研究者(佐藤忠男も含む)が「満州」と誤読していることの指摘と、その誤読の解釈もユニークである(32頁)。大陸に渡った佐分利の行先がどこだったのかぼくは記憶にない。日本が侵略した中国大陸のどこかに佐分利は一旗揚げに行ったので、そこが天津だろうと満州だろうと同じことくらいにしか考えていなかったのが正直なところである。
しかし著者にとって「天津」であることはきわめて重要な意味をもつ。中国に派兵された小津は、戦場で志賀直哉「暗夜行路」(岩波文庫)を愛読しているが、「暗夜行路」で時任謙作の恋愛相手となるお栄は、大陸に渡ったものの天津で水商売に失敗し、大連で盗難にあい、最後は京城(現在のソウル)で行き詰って謙作に引き取られて帰国する。「王道楽土」の「満州」ではなく、「暗夜行路」お栄の不吉な行路の出発点となる「天津」は、戸田家の一見すると安定した家族像の裏面に小津がしのびこませた家族崩壊の予兆のメッセージだったと著者はいう(35頁~)。
そして、「宗方姉妹」にわずかに登場する「大連」は、「暗夜行路」のお栄が流れていった先であり、ここにも著者は「帝国」の残影を見る。著者によれば、「宗方姉妹」は「晩春」に見られた小津調家族映画に対する自己批判である(47頁)。さらに、「暗夜行路」のお栄が最後に流れ着いたのが京城であり、時任謙作がお栄を迎えに京城に行った留守中に(謙作の)妻と従兄とが密通してしまうのであるが、「東京暮色」でも、夫(笠智衆)が「京城」に単身赴任中に、妻(山田五十鈴)が夫の部下(中村伸郎)と駆け落ちしてしまう。この映画でも「京城」は家族崩壊の記号としての意味をもっているのである。
小津映画では、「戸田家の兄妹」の天津、「宗方姉妹」の大連を経て、「東京暮色」で京城に辿りつく。「そしてその時点で『晩春』のごとき『小津的』な家族は完全な自壊へと至るのである」と著者はいう(58頁)。天津、大連、京城にそんな含意があったとは、ぼくは思ってもみなかった。しかも「東京暮色」は、林芙美子(というか水木洋子)の「浮雲」に対する小津の応答でもあるという(同頁。このことは浜野保樹の見解だそうだ)。「浮雲」と「東京暮色」との関連など、「浮雲」を見た時も、「東京暮色」を見た時にもまったく思い浮かびもしなかった。「浮雲」の高峰秀子と森雅之が、「東京暮色」の山田五十鈴と中村伸郎だったとは。
さらに「暗夜行路」を下敷きにした「風の中の雌雞」の、戦後の生活困窮時に売春をしてしまった事実を復員してきた夫に告白する妻(田中絹代)と夫(佐野周二)が抱擁しあって再生を誓うラストシーンを、病気の子どもも、戦場から帰ってきた夫も、階段から突き落とされた妻もみんな死人であり、あれは幽霊同士の抱擁であるとする黒澤清の解釈を、「暗夜行路」の結末から見て正当な解釈であると支持する(41頁)。田中は告白などしなければよかったのにとぼくは思ったが、著者によれば、「嘘」を嫌った小津にとって、この場面での「嘘」は許されなかったのだ。
ぼくは、田中絹代の台詞まわしは、田中が「雨月物語」の幽霊になっても「田中絹代」そのままだと感じたことがあったから、「風の中の雌雞」ラストシーンの田中が実は幽霊だったという解釈は、これもなるほどと呻った。この本を読んでいると著者の深読みにしばしば呻らされることになる。
「呻らされる」ついでに、「東京暮色」のラストシーンで、北海道に去っていく山田と中村の不倫カップルの乗った列車が出発を待つ上野駅ホームで、応援団風の学生たちが歌う明治大学校歌の騒々しさに辟易したのだが、著者は、同校校歌の「いでや東亜の一角に・・・正義の鐘を打ちて鳴らさむ・・・独立自治の旗翳し・・・遂げし維新の栄になふ 明治その名ぞ吾等が母校」という漢文調の(すなわち「中国化」された?)歌詞を引用しつつ、あのシーンは「明治」以来の「私たちは『帝国』たりうる存在なのだ」という「嘘」の崩壊を暗示しているという(206頁)。明大校歌の歌詞まで援用しながらタネ明かしをされると、ここでも「なるほど」と呻らざるを得ない。この「東京暮色」のラストシーンを佐藤忠男や川本三郎さんは小津の最高の表現のひとつに数えているという。
日本の近代化はたんなる西欧化ではなく、朱子学化でもあったという指摘は、明治初期の法制度の近代化の過程を少し眺めただけのぼくにも了解可能であるし(明治20年代になっても「民法出でて忠孝亡ぶ」などという批判がまかり通っていた!)、まさに近代化の尖兵の一つであった明治大学(明治法律学校)の校歌は、西欧化にして漢語化を象徴しているように思う。
小津は、次の世代の木下惠介「日本の悲劇」の試写会を退席して以来両者は不仲となり、お互いの作品を見なかったという。ぼくは木下の「カルメン故郷に帰る」を見た後の小津が「いい映画を見た後は酒がうまい」と言ったというエピソードを何かで読んだ覚えがあるのだが・・・。小津が嫌った「日本の悲劇」で母親を見捨てる冷淡な長男役を演じた田浦正巳に、妊娠した有馬稲子を見捨てて死に追いやり平手打ちを食らうという人格下劣な男の役を「東京暮色」で割り振ったのは木下への意趣返しだったのではないかと解釈する(161頁)。そこまでは、とも思うが、「東京暮色」の田浦の役は俳優としては演じたくない役柄ではあっただろう。
小津映画に頻出する「麻雀屋」への嫌悪感(128頁ほか)、同じく「ラーメン屋」の意味(「東京暮色」の鶴田浩二と津島恵子のラーメン屋でのデート、東野英治郎と杉村春子父娘が営む来燕軒など)の解釈などにも(144~5頁)呻らされた。
その他、「小早川家の秋」、「青春放課後」(というテレビドラマが小津の最後の作品だったという)、「彼岸花」、さらには「麦秋」「晩春」などの小津作品に見られる日本の「東西」問題(西日本問題)が、網野善彦の「日本」論などとの関係で語られる(151頁)。ぼくは「東西」問題以前に、浪花千栄子や中村雁治郎らの関西弁が耳障りで画面に集中できないのだが、関西弁に対してそんな強い拒否感をぼくが抱く深層にも、日本人の「東西」問題が潜んでいるのだろうか。
サブタイトルにもなっている「昭和史」に対する成田龍一らの最近の視点、丸山眞男、竹内好、蓮實重彦ら旧世代の発言と、それらに対する著者の応答も、ぼくの読解能力を超える。そして何より残念なのは、著者與那覇さんの創見である「日本の中国化」という視点が理解できていないので、小津映画にみられる「中国化」についても論評できないことである。
もっと勉強しなければならないと思う一方で、小津映画はもっと単純に見てもよいのではないか、という思いも捨てられない。本書で一番の収穫だったことは、一般に小津の失敗作といわれている「戸田家の兄妹」「風の中の雌雞」「東京暮色」「宗方姉妹」などが決して失敗作などではなく、小津の戦争体験が背景にある重要な作品と見る見方を教えられたことだろう。
ぼくは「父ありき」から「秋刀魚の味」に至る小津の「家庭映画」の温かさも嫌いではないが、「戸田家の兄妹」「風の中の雌雞」「東京暮色」なども印象的な作品で、失敗作とは思えなかった。本書はこれらの諸作品を解読して、新たな見方をぼくに示してくれた。
ぼくは、「帝国」と「家族」の矛盾(206頁)という側面に注意しながら「東京暮色」を見たくなった。
2024年10月25日
蛇足を1本。本書の冒頭に、「晩春」のなかで子役が川上の赤バットをまねてバットに塗料を塗りたくったが乾かないと言って泣きべそをかき、これを原節子がからかうシーンの意味が不明であるという指摘がある。実は当初のシナリオでは、娘を嫁がせた父親(笠智衆)が家に戻ってひとり号泣するというラストシーンだったのを、笠が号泣するという演技に猛反発したため現行のようなシーンに改変されたという。そのために生じた「オチの欠如した落丁本だった」という(9頁)。
ぼくは、「晩春」の原と子役の会話シーンがあったことなど忘れていたが(小津映画の子役が出てくるシーンは嫌いでいつも読みとばしてしまうのだが)、「落丁」というほどでもないと思う。ラストシーンで笠が号泣しようとしまいと、子役と原の会話は「人は泣きたいけれど泣かないこともある」というメッセージを伝えている点で、ラストシーンの笠の心境を暗示していると思う。