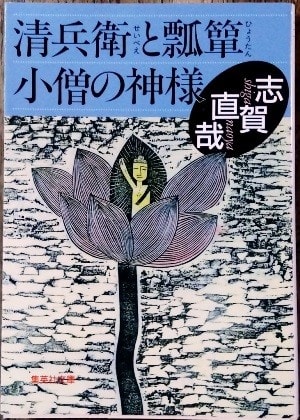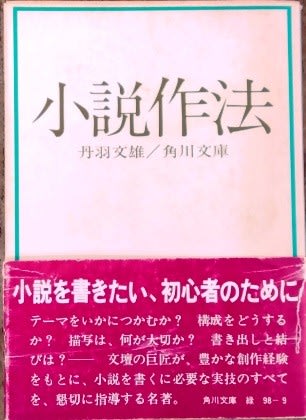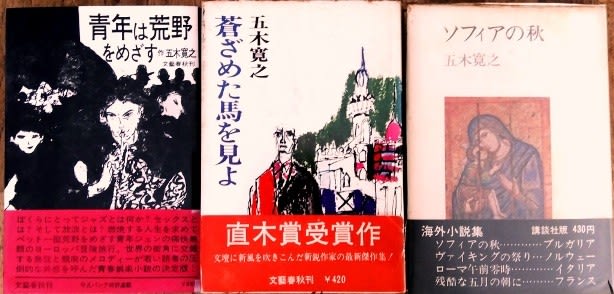東京新聞2025年2月26日夕刊の「下山静香のおんがく ♫ X ブンガク ✑ 」欄で、スタインベックの「怒りの葡萄」を取り上げていた。
執筆者は「ピアニスト、執筆家」という肩書で紹介されているが、以前にもサマセット・モームの「クリスマスの休暇」について、作品中に登場するイギリス人ピアニストがロシア系女性から「あなたにはロシアの曲は弾けない」と難詰される場面を中心に紹介していた。
今回の「怒りの葡萄」も、オクラホマからカリフォルニアに移住してきた主人公ジョード一家が、わずかな安息を求めてハーモニカやフィドル(どんな楽器?)、ギターを弾きながら「チキン・リール」という曲に合わせて踊る場面を紹介している。「チキン・リール」はアメリカ人作曲家デイリーによるラグタイム調のピアノ曲だそうだ。
ぼくは1964年10月11日に「怒りの葡萄」全3巻(大久保康雄訳、新潮文庫、昭和38年4月第14刷)を読み終えた。下巻のカバー裏にその旨の書き込みがある。1964年10月11日といえば、東京オリンピック開会式の翌日ではないか。開会式が土曜日だったから11日は日曜日、前日とはうって変わって東京は雨が降っていたはずである。
日付に続けて「I think “East of Eden” is better than “The Grapes of Wrath” 」などと書き込んである。中学3年生の英作文であるが「エデンの東」への思い入れが最高潮だった時期がしのばれる。
残念ながら、下山氏が書いている「チキン・リール」(どんな曲か?)を主人公のジョード一家が踊る場面の記憶はない。あの頃のぼくたち中学高校生にとっては、文化祭で踊る「オクラホマ・ミキサー」や「マイム・マイム」が女の子と手をつなぐ唯一の機会だったから、「怒りの葡萄」にそんな場面が登場したら記憶に残ったと思うのだが。ぼくの印象に強く残ったのは、シャロンのバラ(大久保訳ではそう呼んでいたが、最近の新訳ではローザンシャロンとか訳していた)が飢えで死期の迫った老人に乳を含ませる場面だった。
というより、「怒りの葡萄」で一番印象に残っているのは実は内容ではなく、向井潤吉が描いたカバーの絵である。アメリカ西部の砂塵に煙ったルート66沿いの風景や、ジョード一家と家財一式を乗せた壊れかけのフォードのトラック、夢見てやって来たカリフォルニアの現実に失望するジョード一家の表情など、今でも瞼に浮かんでくる。主人公は明らかに映画「怒りの葡萄」で主人公を演じたヘンリー・フォンダの顔である(上の写真)。たしか新潮文庫版ヘミングウェイ「武器よさらば」の表紙カバーも向井潤吉だったと思う。あの頃以来、ぼくは向井潤吉の描く田舎の風景画が好きである。
最近の小説をちっとも面白いと思えない(読んでもいないので面白いかどうかも分からないのだが、食指を動かされる題名や推薦文、内容を紹介する宣伝コピーにさえ出会えない)ぼくとしては、モームとスタインベックを登場させた下山さんに、この二人を取り上げただけでも共感を感じてしまうのである。
2025年2月27日 記
追記 書いていて思い出したのだが、ぼくが初めてスタインベックの名前を知ったのは、中学校の国語教科書(石森延男編だったと思う)に載っていた石森の随筆の中に、「赤い子馬」を読んでいる少女が登場して、「赤い子馬」は「スタインベックという人の作品よ」と語っている場面だった。