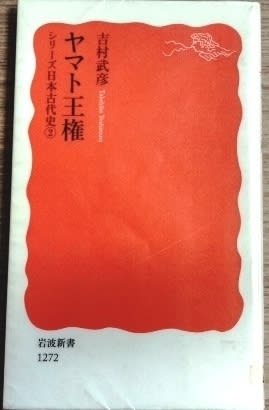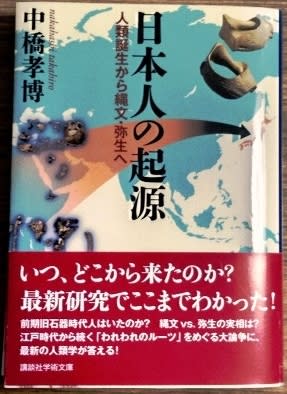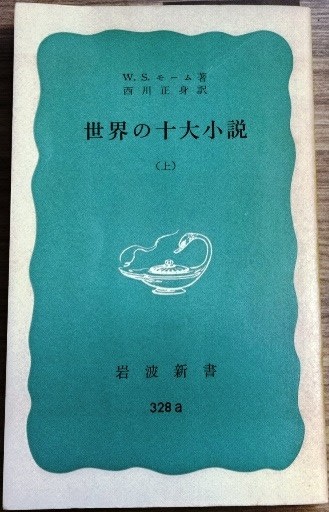(承前)
次に、吉村武彦『ヤマト王権』(岩波新書、2010年)を読んだ(冒頭の写真)。
なぜ「ヤマト」なのか、なぜ「王権」なのか? から勉強のやり直しである。
『後漢書』に登場する1~2世紀の「倭国」から、3世紀半ばの「邪馬台国」の卑弥呼を経て、4世紀前半、『日本書紀』では第10代とされる崇神をヤマト王権で最初の天皇とし(34頁~)、それから6世紀初の推古朝(592~628)までを本書『ヤマト王権』の対象とする。
『漢書』や『魏志倭人伝』に「倭」と表記されている政権のことを、著者は「誤解を避けるために」「やまと」ではなく「ヤマト」と表記するというが(まえがきⅷ頁)、どう「誤解」されるのかぼくには分からなかった。
『後漢書』などによれば倭王自らが「王」と名のっていたことから「王権」と表記し、王宮(ヤマト権力の中心を著者は「王宮」と呼んでいる)の所在地や権力の範囲が「大和」地方に限定されるわけではなく、いわゆる「大八洲国」(東北地方南部から本州、四国、九州)に及ぶことから「ヤマト」と表記するようだ(同ⅸ頁)。
『日本書紀』には「はつくにしらすスメラミコト」(=初代「天皇」)が2人登場するが(51頁)、神武天皇以降の数代は実在せず、「書紀」では第10代とされる崇神天皇を、著者は(ヤマト王権の)初代の王とする(55頁)。
『宋書』に登場する「倭の五王」のうち「珍」が反正(仁徳の子)、「武」が雄略(仁徳の孫)と比定される(73頁)。継体の(天皇)即位(507年)によって仁徳系は断絶する。「継体」という諡号は、当時の貴族にとって継体が新しい「王統」と見られたことを反映しているという。
継体が応神の五世孫であることは事実だとあるが(~117頁)、どのような根拠からそう断定できるのかは書いてない。古代の男たちは、どのようにして生物的父子関係の存否を確信していたのだろうか。文化人類学の世界では、どの時代、民族にも父子関係(生殖)を確信させる根拠となる独自の「民族生殖理論」というのがあるうそうだが、日本古代の「民族生殖理論」はどのようなものだったのか。
「王統」という用語も分からない。「王統の変更」は「万世一系」と矛盾しないのか。
ぼくの学生時代から提唱されていた騎馬民族説をはじめとする王朝交代説をめぐる(井上光貞、直木孝次郎、水野佑ら昔ながらの面々の)議論も、「万世一系」への関心から興味があったのだが、本書の学説紹介(98頁~)だけではぼくは十分には理解できなかった。
古墳(とくに前方後円墳とヤマト王権の関係)、遷都など王宮の所在と権力関係、朝鮮半島諸国との関係なども、ここにうまく要約できないところを見ると、残念ながら理解できていない証拠である。
なお、「天皇」という文字史料は、飛鳥池遺跡から出土した木簡(677年のものとされる)が初出で、720年に編纂された「日本書紀」や712年の「古事記」が(歴代の倭王を)天皇と表記するのは後世の知識による加筆であるとされる(~11頁)。「天皇」が正式な制度上の名称となったのは浄御原令(689年施行)であるが、大海人皇子が(天武)天皇(本書の年表によれば673年即位)であったことは間違いないとある(12頁)。
* * *
以下は、『ヤマト王権』(岩波新書)の中から、ぼくの関心に触れた知識をいくつか列挙しておく。
5世紀代の王の后妃の出自は、豪族との婚姻が多いが、6世紀の欽明天皇以降になると近親婚が増えてくるとあった(「ヤマト王権」41頁)。具体的にはどの範囲の近親婚で、どのような理由からだったのだろうか。
記紀には王位継承をめぐる兄殺しの伝承が記されているが、継体天皇は王位継承者を定める「大兄」制度を創設した。背景には5世紀後半からの家長の地位の父系的、直系的継承や、6世紀前半の夫婦同一墓という家父長制的な動向があった。
しかし一夫多妻のもとでは后妃ごとに大兄が存在するため、特定の長子を「太子」(皇太子)とする制度が生まれたという(134頁)。なお、同著『古代天皇の誕生』によれば、「大兄」「太子」制度以降も複数の王位継承候補者が存在する場合には、「群臣の議と推挙」によって継承者が決められた(吉村武彦『新版・古代天皇の誕生』角川ソフィア文庫、2019年、113頁)。ただし「群臣」といっても、厩戸皇子の場合の蘇我氏のように、時の有力者の意向が強かったという(同~120頁)。
継体天皇の没後に、継体の子のうち仁賢天皇の娘のと間に生まれた欽明天皇が即位するが、『書紀』は彼を「嫡子」と表記しているという(152頁)。これがわが国における「嫡子」の初出なのだろうか。
氏姓制度が成立する以前の5世紀までは、倭国王は「倭」を姓として名のったが、氏姓制度が確立すると、倭国王は氏(も姓)も名のらないことになった。氏、姓を付与する王は氏姓制度を超越する存在となったのである。近代までは天皇一族と(五色の)賤が無姓者であったが、近代になり賤は有姓者となったが、天皇一族は現在も姓がない(170頁)。
天皇に氏(姓)がないことは森達也『千代田区一番一号のラビリンス』もこだわっていた。
2022年5月30日 記
次に、吉村武彦『ヤマト王権』(岩波新書、2010年)を読んだ(冒頭の写真)。
なぜ「ヤマト」なのか、なぜ「王権」なのか? から勉強のやり直しである。
『後漢書』に登場する1~2世紀の「倭国」から、3世紀半ばの「邪馬台国」の卑弥呼を経て、4世紀前半、『日本書紀』では第10代とされる崇神をヤマト王権で最初の天皇とし(34頁~)、それから6世紀初の推古朝(592~628)までを本書『ヤマト王権』の対象とする。
『漢書』や『魏志倭人伝』に「倭」と表記されている政権のことを、著者は「誤解を避けるために」「やまと」ではなく「ヤマト」と表記するというが(まえがきⅷ頁)、どう「誤解」されるのかぼくには分からなかった。
『後漢書』などによれば倭王自らが「王」と名のっていたことから「王権」と表記し、王宮(ヤマト権力の中心を著者は「王宮」と呼んでいる)の所在地や権力の範囲が「大和」地方に限定されるわけではなく、いわゆる「大八洲国」(東北地方南部から本州、四国、九州)に及ぶことから「ヤマト」と表記するようだ(同ⅸ頁)。
『日本書紀』には「はつくにしらすスメラミコト」(=初代「天皇」)が2人登場するが(51頁)、神武天皇以降の数代は実在せず、「書紀」では第10代とされる崇神天皇を、著者は(ヤマト王権の)初代の王とする(55頁)。
『宋書』に登場する「倭の五王」のうち「珍」が反正(仁徳の子)、「武」が雄略(仁徳の孫)と比定される(73頁)。継体の(天皇)即位(507年)によって仁徳系は断絶する。「継体」という諡号は、当時の貴族にとって継体が新しい「王統」と見られたことを反映しているという。
継体が応神の五世孫であることは事実だとあるが(~117頁)、どのような根拠からそう断定できるのかは書いてない。古代の男たちは、どのようにして生物的父子関係の存否を確信していたのだろうか。文化人類学の世界では、どの時代、民族にも父子関係(生殖)を確信させる根拠となる独自の「民族生殖理論」というのがあるうそうだが、日本古代の「民族生殖理論」はどのようなものだったのか。
「王統」という用語も分からない。「王統の変更」は「万世一系」と矛盾しないのか。
ぼくの学生時代から提唱されていた騎馬民族説をはじめとする王朝交代説をめぐる(井上光貞、直木孝次郎、水野佑ら昔ながらの面々の)議論も、「万世一系」への関心から興味があったのだが、本書の学説紹介(98頁~)だけではぼくは十分には理解できなかった。
古墳(とくに前方後円墳とヤマト王権の関係)、遷都など王宮の所在と権力関係、朝鮮半島諸国との関係なども、ここにうまく要約できないところを見ると、残念ながら理解できていない証拠である。
なお、「天皇」という文字史料は、飛鳥池遺跡から出土した木簡(677年のものとされる)が初出で、720年に編纂された「日本書紀」や712年の「古事記」が(歴代の倭王を)天皇と表記するのは後世の知識による加筆であるとされる(~11頁)。「天皇」が正式な制度上の名称となったのは浄御原令(689年施行)であるが、大海人皇子が(天武)天皇(本書の年表によれば673年即位)であったことは間違いないとある(12頁)。
* * *
以下は、『ヤマト王権』(岩波新書)の中から、ぼくの関心に触れた知識をいくつか列挙しておく。
5世紀代の王の后妃の出自は、豪族との婚姻が多いが、6世紀の欽明天皇以降になると近親婚が増えてくるとあった(「ヤマト王権」41頁)。具体的にはどの範囲の近親婚で、どのような理由からだったのだろうか。
記紀には王位継承をめぐる兄殺しの伝承が記されているが、継体天皇は王位継承者を定める「大兄」制度を創設した。背景には5世紀後半からの家長の地位の父系的、直系的継承や、6世紀前半の夫婦同一墓という家父長制的な動向があった。
しかし一夫多妻のもとでは后妃ごとに大兄が存在するため、特定の長子を「太子」(皇太子)とする制度が生まれたという(134頁)。なお、同著『古代天皇の誕生』によれば、「大兄」「太子」制度以降も複数の王位継承候補者が存在する場合には、「群臣の議と推挙」によって継承者が決められた(吉村武彦『新版・古代天皇の誕生』角川ソフィア文庫、2019年、113頁)。ただし「群臣」といっても、厩戸皇子の場合の蘇我氏のように、時の有力者の意向が強かったという(同~120頁)。
継体天皇の没後に、継体の子のうち仁賢天皇の娘のと間に生まれた欽明天皇が即位するが、『書紀』は彼を「嫡子」と表記しているという(152頁)。これがわが国における「嫡子」の初出なのだろうか。
氏姓制度が成立する以前の5世紀までは、倭国王は「倭」を姓として名のったが、氏姓制度が確立すると、倭国王は氏(も姓)も名のらないことになった。氏、姓を付与する王は氏姓制度を超越する存在となったのである。近代までは天皇一族と(五色の)賤が無姓者であったが、近代になり賤は有姓者となったが、天皇一族は現在も姓がない(170頁)。
天皇に氏(姓)がないことは森達也『千代田区一番一号のラビリンス』もこだわっていた。
2022年5月30日 記