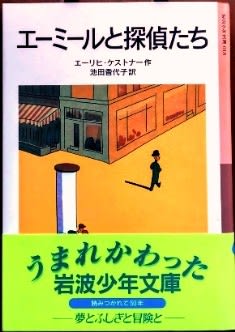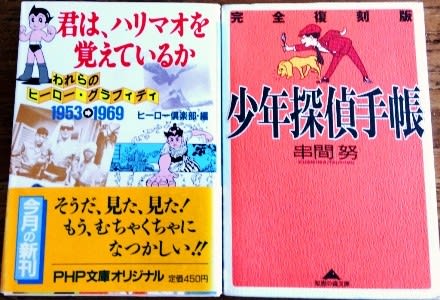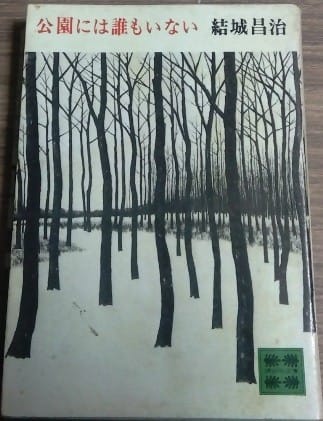ぼくの探偵小説遍歴、第3回。
★創元推理文庫(東京創元社)
ようやく大人の本の世界に入った。ぼくにとって探偵小説の入り口は東京創元社の創元推理文庫だった。背表紙に黒猫(ミステリー)か時計(倒叙もの)のマークがついた作品が多かった(冒頭の写真はペリー・メイスンものの何冊か)。
コナン・ドイル「シャーロック・ホームズ」は創元推理文庫版でそろえた。当時は短編集は4冊出ていたと思うが(「冒険」「生還」「回想」「最後の挨拶」)、ホームズの短編は2冊で飽きた。長沼弘毅など「シャーロキアン」ものも何冊か買ったが、そんなに入れ込むほどの魅力はぼくは感じなかった。法律を勉強する者にとっては、ホームズと言えば、オリバー・ウェンデル・ホームズだろう。
アール・S・ガードナー「ペリー・メイスンもの」や、ウィリアム・アイリッシュ「暁の死線」なども創元推理文庫版で読んだ。「暁の死線」は章ごとに時間経過を示す時計のイラストが入っていた。「黒衣の花嫁」式のアイリッシュとは違う一面があった。

ヒラリー・ウォー「失踪当時の服装は」、同「事件当夜は雨」(上の写真)。「失踪当時の服装は」にはぼくが生まれた日、1950年3月20日のことが出てくる。この日付けが出てくる小説は他に知らない。
W・マッキヴァーン「悪徳警官」など、悪徳警官ものも好きなジャンルだった。
BSのテレビドラマの「警部フォイル」「女警部ヴェラ」「刑事モース」などにも悪徳警官が頻繁に登場する。アメリカだけでなく、イギリス警察でも常態なのだろうか。
★早川ポケットミステリ(早川書房)
エド・マクベイン「87分署」シリーズは、事件の背景の何気ない景色や季節の描き方、それと書きだしと結びの文章が好きだった。「明日の新聞の見出しには“熱波去る”の文字が躍るだろう」という最後の一文があったような・・・。
一番印象に残っているのは「被害者の顔」という作品。平凡な主婦と思われていた女性が殺されたが、捜査が進むとその女性の様々な「顔」が明らかになり、彼女の人生のどの側面(=顔)が犯行の原因になったかの究明が解決につながるといったストーリーだった(下の写真)。

ジョン・ボール「夜の熱気の中で」も印象的だった(シドニー・ポワティエの映画も)。アメリカ南部の、夜になってもじっとりした熱気が伝わってきた。「十二人の怒れる男」(ヘンリー・フォンダ)や「アラバマ物語」(グレゴリー・ペック)なども同じように汗の滲む南部の熱気が印象がある(映画の印象かも)。
逆に、雨と言えば、ニコラス・フリーリング「雨の国の王者」。
これを読んだときには「これがぼくの一番好きな推理小説だ」と思った。理由は覚えていないが、感傷的な文章だったのか。ぼくは雨をうまく描いた小説が好きである。雨の日それ自体も好きである、出かける必要がなければ、だが。これ以外のファン・デル・ベルク警部ものは読んでいない。
BSで放映されているドラマの「ファン・デル・ベルク警部」は主人公のイメージが違いすぎるうえに、時代と舞台が現代の病んだオランダに変更になっていて、1950年代のオランダに対してぼくが抱いた「風車とスケートの国、オランダ」のイメージが粉砕されてしまった。

ウィリアム・アイリッシュ「黒衣の花嫁」「喪服のランデブー」「幻の女」「死者との結婚」(コーネル・ウーリッチ名義かも)などの感傷的な文章、ストーリーも嫌いでなかった(上は、ハヤカワ文庫版の表紙)。
羽仁未央のエッセイで、「アイリッシュの小説は好きだけど、私が編集者なら表紙に彼の写真は載せない」と書いていたのを読んで笑えた。確かにハヤカワ文庫の裏表紙に載った著者の写真は、内容から想像する作者のイメージとあまりに違いすぎた。「ティファニーで朝食を」のジョージ・ペパードまでの容貌は期待しないけれど。
マルコ・ペイジ「古書殺人事件」、べロック・ローンズ「下宿人」、レイモンド・ポストゲイト「十二人の評決」はいずれも長らく品切れだったので渇望していたところ、ポケットミステリ1000冊か2000冊突破記念で復刊されたので喜んで買って読んだが、いざ読んでみるとどれもそれほど面白くはなかった。「下宿人」は切り裂きジャックがモデルだが、結局「下宿人」がジャックだったかどうかは分からずじまいでがっかり。

早川ポケットミステリにも、メリー・メイスンもの、メグレ警部ものが何冊が入っている。「モース警部」の原作も何冊か入っているが、テレビドラマで済ませた。
「フロスト警部」の原作は創元推理文庫(?)に入っているが、これも厚すぎて読む気にならないのでスルーして、テレビドラマで済ませた。
★早川書房ほかのハードカバー
ドロシー・ユーナック「法と秩序」(早川)、
ジョセフ・ウォンボー「オニオン・フィールド」(早川)、
同「ブルー・ナイト」(早川)など1970~80年代に読んだ早川の単行本も悪徳警官ものだったか。
V・ビューグリオシー「裁判――ロサンゼルス二重殺人事件」(創林社、1979)なんてのも読んだ。実話だったのかフィクションだったのか内容は覚えていない。
このあたりの単行本はかさばるために断捨離してしまったので確認できない。
★スパイ小説
スパイものは、ジョン・ル・カレ「寒い国から帰って来たスパイ」(早川書房)、イアン・フレミング「007ロシアより愛をこめて」(創元推理文庫)くらいしか読んだことはなかったが、フレデリック・フォーサイスの「ジャッカルの日」は面白かった印象がある。
「ロシアより愛をこめて」は間違いなく裏表紙につられて買ったのだと思うが、それらしかったのはこのシーンを描いたページだけで期待(?)外れだった(下の写真)。

サマセット・モーム「秘密諜報員アシェンデン」(創元推理文庫ほか)はモームの実体験がもとになっている。第1次大戦中のスイスが舞台だが、スパイのはかなさが印象的。「禿頭のメキシコ男」(だったか?)というエピソードがよかった。モームはぼくが好きな作家で、「木の葉のそよぎ」「コスモポリタン」などの短編がとくにいい。
「法王の身代金」「ジャッカルの日」など、一時期角川書店から出た単行本も何冊か読んだ。

マイ・シューヴァル、ペール・ヴァ―ルー「笑う警官」など、最初はハードカバーで読んだが、その後のマルティン・ベックシリーズ(全5冊か)は角川文庫版で読んだ。好きなシリーズだったが、パートナーのどちらかが亡くなってしまい、シリーズも終わってしまった。スウェーデンもかつてのリベラリストにとっては理想の国だったが、その後は失楽園になってしまった(上の写真)。 (つづく)
2024年2月17日 記