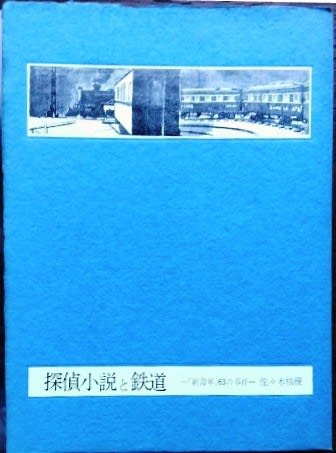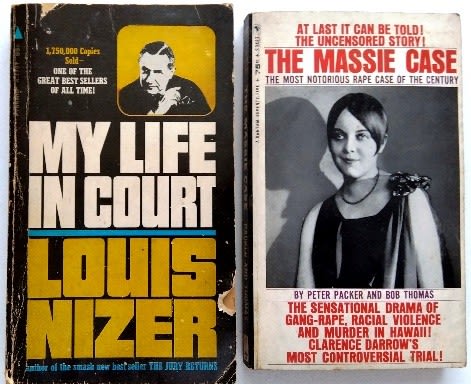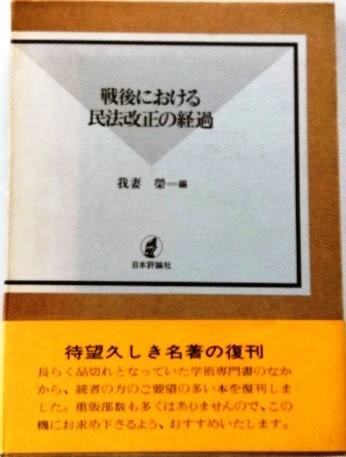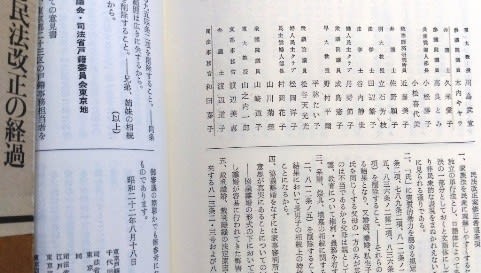永井荷風「摘録・断腸亭日乗」(岩波文庫、1987年、磯田光一編)下巻を読みおえた。
「巻措く能わず」と言いたいところだが、何度か巻を置いて嘆息した。
ぼくも若い頃だったら、荷風の「傍観者的態度」に我慢できなかっただろう。しかし老境の今になって読むと、昨今の日本や世界の状況に対して、結局自分も日本が再び戦前になりゆく時代の「傍観者」の1人ではないのかという自省、自責の念から嘆息してしまうのである。
「日乗」になぜ削除、切取の個所がたくさんあるのかは、昭和16年6月15日の日記で分かった。
荷風が中央公論に寄稿した文章によって、彼が長年にわたって日記をつけていることが世人に分かってしまい、彼が時局について何を記録しているかを探る者が出てくることを懸念し、荷風はある深夜、日記の中の不平憤惻の文字を切り取ったのである(142頁)。「断腸亭日乗」は秘かに書かれた記録ではなく、これ以降はいつ権力者に発覚するかしれない文書になったのだ。
それにしては、日記の一部を切り取り、削除したその日に、日支戦争は日本軍の張作霖暗殺に始まり、・・・支那の領土を侵略し始めたが、長期戦に窮して聖戦と称する無意味の語を用いだした、南洋進出は無知の軍人ら獰猛の壮士の企てたことで、一般人民の喜ぶところではない云々と書き記している(143頁)。切取、削除した個所にはこれよりもっと踏み込んだ軍部、政権批判が書いてあったのだろう。
そもそも、新聞を読まず、送呈された雑誌類も読まず、ラジオも聴かなかった荷風はどのようにして、それらの情報を得ていたのか。すべて玉ノ井の娼婦や、浅草、銀座などでの友人や編集者との会話だけから得ていたのだろうか。
下巻でも、荷風の当時の政治家、軍人、文士らに対する筆鋒は相変わらず厳しい。
昭和14年1月に東京市長の音頭で「大都会芸術」なるものが提唱された際には、参加した「菊池吉屋佐藤西条らいずれも大の田舎漢にて噴飯の至り」と書く(67頁)。菊池寛、吉屋信子、西条八十だろうが、佐藤は紅緑か春夫か。
昭和18年5月に、菊池寛が設立した言論報国会が無断で荷風の名前を名簿に載せた際には、「同会々長は余の最も嫌悪する徳富蘇峰なり」、しかし抗議することによってかえって相手に名をなさしむことになるので捨て置くことにするとある(192頁)。
--などと、上巻と同様に下巻についても印象に残った記述を摘録しようと思ったが、億劫になってきたので、もう止めにする。
下巻には、昭和12年(1937年)1月から亡くなる前日の昭和34年4月29日までの日記が掲載されている。
相変わらず軍人、文士らの「田舎漢」批判、出版社や編集者の批判、印税や税金の話題などが多いが、戦後になると女性の話は減ってくる。毎日その日の天候から始まり、散歩の道すがらの風物、病気(「腹痛下痢二回」など)の話題は一貫している。
この間、軍人の専制政治があり、戦争が激化し、やがて日本の敗色濃厚となり、昭和20年3月の東京大空襲では麻布の自宅「偏奇館」も焼失し、岡山、熱海その他で疎開生活を送る。敗戦後も暫くは従弟宅などで居候生活をした後に、千葉県市川に40坪の住宅を購い、亡くなるまで一人で過ごすことになる。
戦前には、印税、株の配当などでかなりの収入を得ていたようだが、戦後は預金封鎖、新円切替、財産税導入など(303頁など)があり、経済面で不安を感じたようだ。預金封鎖にあったため、中央公論社嘱託となるという記述もある(294頁)。
「偏奇館売文覚書」なる備忘も残している(316頁)。戦前には軽蔑していた「売文」業に自分も堕ちいったことを認め、売文で糊口をしのぐ生活を送る(石川淳によれば戦後の荷風の作品に見るべきものはないそうだ)。
昭和27年には、朝永振一郎、辻善之助、安井曽太郎、梅原龍三郎らとともに文化勲章を受けている。この年、佐々木惣一までもが文化勲章を受けていたことには驚いた。
「日乗」に記された言動からは、荷風が文化勲章を受けるなど考えられないことだが、毎年50万円の年金を生涯貰えることは、戦後の荷風には経済面で魅力だったのかもしれない。授賞には、当時荷風全集を刊行していた中央公論社の島中雄作の画策、尽力があったと推測される。なお「中央公論高梨」という名前が時おり出てくるが、どこかで見覚えがあると思ったら、中公バックス版「世界の名著」(中公)奥付の発行人が「高梨茂」となっていた。彼だろう。
昭和29年頃から日記の記述の分量はだんだん少なくなり、昭和34年には「晴。正午浅草。」のような記載がつづいていて、亡くなる前日の4月29日の「祭日。陰。」(陰には「くもり」とルビが振ってある)で「日乗」は終わっている。
戦後の世相に関する感想では、昭和22年5月3日の、「米人の作りし日本新憲法今日より実施の由。笑うべし」という記述が一番気になった(308頁)。どういう意味で笑うべし、なのだろうか。
風景についての描写では、森鴎外の墓参のため井の頭線で吉祥寺に向かう場面がよかった。
鴎外の墓は三鷹の禅林寺にあるらしい。渋谷から井の頭線に乗った荷風は、北沢までの車窓は目黒あたりと変わらないが、高井戸あたりから空気は清涼になり田園森林の眺望が目を喜ばすと印象を語る。荷風には米国の田園らしく見えるところもあったようだ(210頁)。
荷風が頻繁に歩く下町の風景にはまったく馴染みがないが、井の頭線が出てくるとは。最近久しく井の頭線に乗っていないが、昭和30年代には浜田山、久我山あたりの車窓には田園風景が広がっていて、緩やかな丘の雑木林や小川が見えた。なぜかこの光景の思い出と一緒に、ぼくにはデル・シャノンの「悲しき街角」が聞こえてくる。
下巻に登場する女性で一番印象に残ったのは、昭和24年6月15日に地下鉄浅草駅のホームで出会った21、2歳の街娼である。荷風が煙草に火をつけるのに難渋していると火を貸してくれ、「永井先生でしょう」と尋ねて、「鳩の町」も読んだという。荷風は煙草の空き箱に100円札を3枚入れて渡す。3日後に偶然再会し再び300円を渡そうとすると、彼女は「何もしないのにそんなにもらっちゃ悪いわよ」と辞退する。
荷風は、その悪ずれしない可憐さに「そぞろに惻隠の情を催さしむ。不幸なる女の身の上を探聞し小説の種にして稿料を貪らむとするわが心底こそ売春の行為よりもかえって浅間しきなり」と書く(332頁)。荷風老いらくの恋のはじまりかと思ったら、小説のネタ取材が目的だったとは・・・。
ぼくはこの女性に小津安二郎「風の中の雌鶏」の文谷千代子を思い浮かべた。彼女のような娼婦以外の女性は荷風を読むのだろうか。
2024年6月30日 記