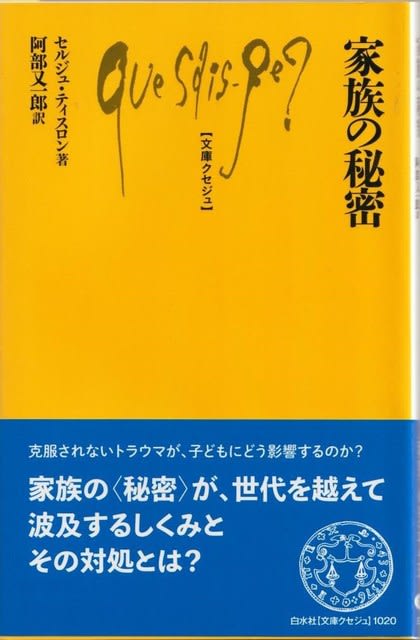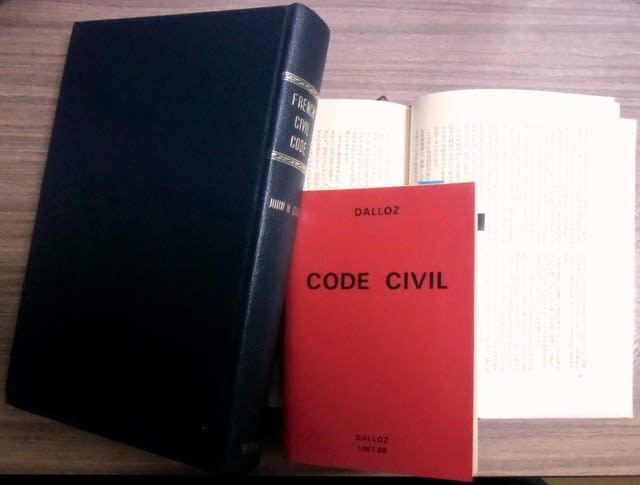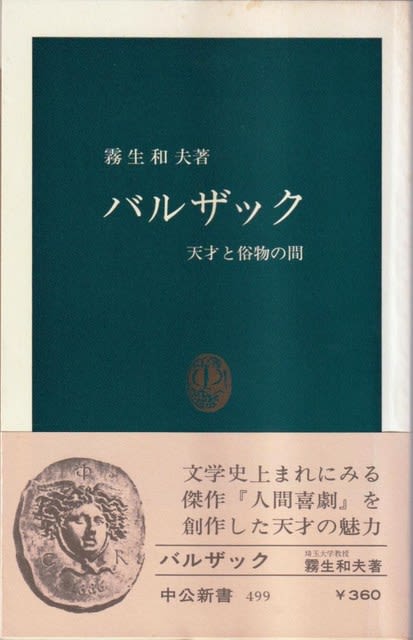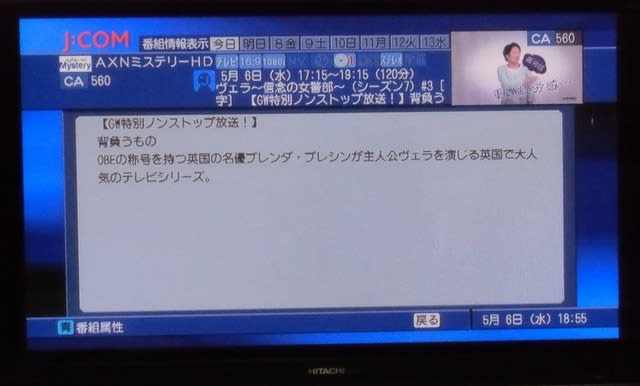遠い昔、ラジオの深夜放送で、不思議なシャンソンを紹介していた。
記憶では、こんな歌詞だった。
ある時、少年が口笛を吹いて嬉しそうにしているので、
父親が「何かいいことでもあったのかい?」と聞いた。
息子が言うには、好きだった彼女にプロポーズしたら、
彼女も “ oui ” と言ってくれたので、ぼくたちは結婚することにしたんだ。
これを聞いたお父さんは、顔を曇らせて言った。
「残念だけど、お前と彼女は結婚できない。
実は彼女はお父さんが浮気をして産ませた子、お前の腹違いの妹なんだ」と。
少年ががっかりした顔をしているので、
母親が「何か心配事でもあるのかい?」と聞いた。
息子がお父さんから聞いた話を伝えると、
これを聞いたお母さんは、笑顔になって言った。
「大丈夫、お前たちは結婚できるよ。
だってお前はお父さんの子ではないのだから」と。
晴れて二人は結婚することになった ♪ ♪
というのである。
講義で嫡出否認のあたりをやるときに、余談でこのシャンソンを紹介すると、毎学年かならず学生の笑いを取ることができた。
この歌は、「家族のスキャンダル」という歌で、フランスでは結構有名らしい。
Google で検索すると、何件か記事がヒットする。ダリダなども歌っているらしい。
昨年買った、セルジュ・ティスロン『家族の秘密』(クセジュ文庫)にもこの歌のことが出てきたので驚いた(54ページ)。
歌詞はちょっと違っていたが、ストーリーは間違っていない。
フランスでは、妻が産んだ子の7%は夫の子ではないという(半公式の)統計数字が、ある学術論文で紹介されていたが、フランス法の専門家は実際はもっと高い数字だろうという。
こんな歌が歌われるくらいだから、フランスでは「不倫は文化」なのだろう、フランス人はこんなことは歌って笑い飛ばしているのかと思っていたが、クセジュによれば、フランスの子どもはこの問題でけっこう悩むらしい。
そして、本題のバルザック『結婚の生理学』である。
数日がかりで、ようやく昨晩読み終えた。
第2部の途中から、これは風刺小説ないしパロディ小説だろうと決めた。そう思うと、叙述の冗漫さ、大げさ振りも理解できる。
「序論」と「第1部 総論」を読んだときは、この本は、妻が貞節を守り、夫が子の父親が誰なのかで悩まなくなり、家庭の幸福が守られるためには、夫はどんな予防策を講ずればよいのか、その兆候が表れた場合にはどのような対抗手段を取ればよいのか、についての「真面目な」議論というか考察だと思ったのであった。
しかし、あまりにも深淵そうな、しかし冗漫な記述を読まされているうちに、どうもこの著者は、決して妻の貞節の維持や姦通の防止を本気でテーマにしているのではないのではないかと思うようになった。
極めつけは、夫が出かけるふりをして、留守宅に愛人がやって来た頃合いを見計らって不意に帰宅するという対抗策(戦術論?)である。
夫が手なずけておいた召使だか義母だったかに、下剤を混ぜたワインを飲まされていた愛人は、慌ててクローゼットに隠れるのだが下剤が効いてきて、我慢できずにナポレオン帽の中に脱糞する、などという「戦術」のあたりで、風刺ないしパロディ小説であるとの確信に至った。
訳者である安士正夫さんの解説には、「単なる風刺もしくはパロディとみなすことができない」とか、「流行に迎合したユーモラスな調子にもかかわらず」といった評価が書いてある。
ということは、「単なる」風刺、パロディではないとしても、「風刺」の側面もあり、「ユーモラスな調子」の小説であることには違いないのだろう。
それにしても、よくもこんなテーマを1巻の書物に仕立て上げたものだと、バルザックのエネルギーと筆力に感服させられた。
さて、次のバルザックは何を読もうか。
2020/5/28 記