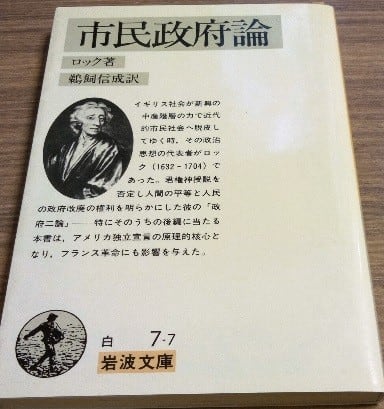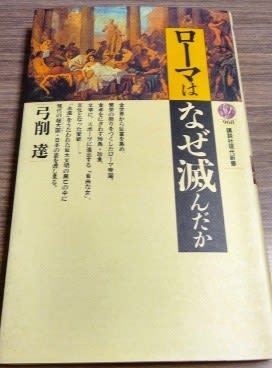トマス・ホッブズ『法の原理ーー自然法と政治的な法の原理』(高野清弘訳、ちくま学芸文庫、2019年)をようやく読み終えた。
よく理解できなかったので、要約もはたして正しいか、心もとない。情けないが、今回も印象批評になってしまった。
第1部が人間の本性について、第2部が政治体についてと題されている。
第1部でホッブズは、数学ないし自然科学における演繹的な推論と同様に、言葉の定義を積み重ねて「人間の本性」を解明しようと試みる(らしい)。感覚(sense)から始まって、対象、概念、知識、想像、記憶、推測、しるし(signs)、理解、判断、意志、約束、脅迫、命令・・・など数十語の概念が規定され、それらの概念が積み上げられていく。「愛」、「情念」、「怒り」、「嫉妬心」、「復讐心」なども分析の対象となっている。
興味はあるのだが、残念ながらこの段階ですでにぼくはついて行けなくなってしまった。
第2部では、自然状態における「自然法」(=「神の法」?)と、政治体が成立した後の「政治的な法」との関係が論じられる。
人々の群れが自然状態にあっては、各々が自分自身の裁判官であり、「私のもの」と「君のもの」を区別し、正邪・善悪を判断する権利を有し、自己保存のために必要不可欠であると信ずる防衛行為を行う権利を有する。このような「戦争の状態」を免れるためには、人々は合意によって一つの「共通の権力」を設立し、この共通の権力に対する恐怖によって構成員間の平和を維持し、外敵に対抗するしかない。これが「政治体」(政治社会、ポリス、都市[シティとルビがある])であり、人々は自己を防衛する権利を共通の権力(=政治体)に移譲する。政治体は「私のもの」と「君のもの」を区別し、正邪・善悪を判断する共通の基準を提示する。これが「政治的な法」(Law Politic)ないし「国家法」(Civil Law)と呼ばれるものである。
本書は書名の通り「法の原理」がテーマなのだが、そもそも「神の法」と「自然法」と「国家の(civil)法」の区別がよく理解できなかった。その前提として、ホッブズがキリスト者なのか理神論者なのか無神論者(ではなさそうだが)なのかもよくわからない。ただ、裁判官の理性(の積み重ね)によるコモンローの支持者でないことは分かる。
ホッブズが君主制を支持しているのか、民主制を支持しているのかも読み取れなかった。貴族制は支持していないようで、どちらかといえば君主制を支持しているように読んだが、民主制を否定しているわけでもなさそうである。3つの政体を並列させて論じており、政体の異同よりも「主権者(君主ないし人民)」の「主権的権利」が重視されている。
ギリシャの「都市」やローマの民主政を背景に論じた箇所についてはヨーロッパの古代史の知識が足りず、執筆当時(1620~40年頃)のイギリス政治を背景にした個所についても「短期議会」などイギリス近代史の知識がおぼろげなために、ホッブズが当時のイギリスのどのような状況を背景に民主政を危惧しているのかが読み取れなかった。

この本のメイン・テーマとは直接関係しないかもしれないが、ぼくの関心をひいた記述をいくつかメモしておく。
(1)コモンウェルスにおいては(君主制にせよ貴族制にせよ民主制にせよ)主権的権力者による平和の維持があってはじめて、人民の自由も可能になるのであって、主権的権力者からの「自由」などいうものはありえない、とホッブズはいう。
むかし村上淳一『イェ―リング「権利のための闘争」を読む』(岩波書店)を読んだ時に、ドイツ語の“Freiheit”の原義は「保護されてある」という意味であり、この語に“free from everything”などという意味はない、ゲルマン時代のドイツにおける“free from everything”など「森の中で狼に食われて死ぬこと」に等しいといった趣旨が書いてあったことを思い出した。最近読んだ「営業の自由」と「精神の自由」の優劣に関する江藤祥平氏という若い憲法学者の論議も想起した(法律時報93巻4号90頁)。ホッブズとはあまり関連はないかもしれないけど。
(2)自己保全はすべての人間が目指す目標であるから、そこに至る道程は「善」であり、自己保全に資する自然法や自然法に従う慣習は「徳」(“virtue”)と呼ばれる、とホッブズはいう(190頁)。
民主政治における“virtue”、新渡戸稲造のいう「平民道」はぼくの永遠のテーマだが、自己保全に資する自然法に従うことが“virtue”であるというホッブズはどう考えればよいのか。ホッブズのいずれかの本には、保全されるべき「生命」に関するホッブズの考えを述べたものがあるのだろうか。
(3)モンテスキュー『法の精神』は近親婚に対してかなり寛容な記述が散見され、望ましくない遺伝的疾患が出現する恐れなどはまったく考慮されていなかった。これに対して、ホッブズ『法の原理』では、創造主は2人の人間しか作らなかったが、「産めよ、殖えよ」の教えに従い、人間の数が多いことは人間の福利の第一にあげられる。この目的を実現するため、主権的権力者は人間の数が増えるように「交接に関する法令」を作ることを義務づけられており、その内容として「自然に反する交接を禁止する」こと、「女を乱れた性のために用いることを禁止する」こと、「一定の血族、姻戚間の結婚を禁止する」ことを定めなければならない、なぜなら、これらの行為は人類の改善にとってきわめて有害だからであるという(355頁)。
「一定の血族、姻戚」がどの範囲までを想定しているのかは明記していないが、ホッブズはそれが人類の改善にとって有害であるという理由で近親者間の結婚を禁止する法令の制定を要求している。ホッブズは「婚姻」外の交接を認めているが、婚姻外であれば近親者間の「交接」(原語は何だろう?)も認める趣旨だろうか。人類に対する有害性という理由は、現代における(血族間の)近親婚の禁止と同じ理由づけである。1640年当時は、人間の遺伝に関する知見は現在ほどではなかっただろうが、畜産における近親交配の影響に関する知見はすでにあったはずである。
「姻戚」関係にある者の間の婚姻(相姦)は遺伝的には問題ないはずだが、ホッブズはこれも禁止すべしという。禁止する根拠は示されていないが、何だろうか。
(4)子どもは男女共同の子を作る行為(generation)の結果であるが、出生後に1人の人間が子に対する権利を取得する根拠は何か。ホッブズは、生まれてきた子に対する権利は原則として母親に帰属するという。自然法によって人は自らの身体に対する権利(所有権)を持っており、子どもは分娩の時まで母親の身体の一部なのだから母親は子どもに対する所有権を持つことになる。自然状態にあって母親は産んだ子の生殺の権利を持っているが、子に対する支配権は、その子を産んだことによってではなく子を保護することによって母親に帰属する。しかし、母親が夫に服従する信約を結んだ場合は、信約によって夫は(母親が子に対して有する)支配権を獲得することになる。その子が夫の子であるか否かは関係ない。男女間の信約が同棲の信約にとどまるか、交接に関する信約にとどまる場合には、子どもをどちらが引き取るかは信約の内容によって決まる(264~7頁)。
ホッブズは、親子関係は「子を作ること」(“generation”)によってではなく、生まれた子を保護することによって生ずるという。しかも血縁関係の存否には関わりないという。さらに現代語で言えば、「内縁関係」や「性的パートナーシップ関係」にとどまる男女の場合、子の帰属は当事者の契約によって定まると言っているように読める。ちなみにロック『市民政府論』は、“generation”(「産みの力」と訳されている)を親権の根拠にしていた(鵜飼信成訳、岩波文庫56頁、Everyman's Library,p.141.)。
(5)自然状態においては争いに決着をつける「正しい理性」などというものは存在せず、実は「正しい理性」による決着を主張する人の個人的理性にすぎない。「正しい理性」の役割を果たすのは主権的権力を有する人(人々)の意志、すなわち「国家の法」であるとして、その具体例として、奇形児が生まれた場合にそれが「人間」かどうかは「法」によって判断されなければならないという例をあげている(371頁)。
「国家の法」による判断の具体例が障害新生児の生殺の問題ということにまず驚いた。障害新生児の治療差控えの基準として、現代イギリスの裁判例では、障害の程度が“demonstrably so awful”か否かという基準を掲げたものが先例とされているが、該児が「人」か“monster”かという基準を唱える法学者がいることを宮野彬氏が論文で紹介しているのを読んだことがあった(確か「鹿児島法学」に載っていたはず)。ホッブズもその一人だったのか。
(6)くじ(籤)による決定の正当性を説く個所も印象に残った。分割できないものや共同で使用できないものの使用はくじ引き(か交互使用)しか解決手段はないという(183~4 頁)。長子相続は生まれた順番という「偶然」によって後継者を決定する制度であり、くじ(籤)による決定と同じく正当な決定方法であるとホッブズは言う。くじによる決定は最も平和的な決定方法であると記した旧約聖書の一節(「箴言」18章18節)も援用されている(198頁)。
最近わが法学界でも「くじ引き」の合理性の議論が見られるが(数年前の「論究ジュリスト」で特集を組んでいた)、ホッブズも「くじ引き」論者だった。夫婦別姓の選択を認めるべきであるという主張がなされているが、夫婦は別姓でよいとしても生まれてくる子の氏をどうするかが隘路となっている。くじ引きによる決定は有力な選択肢となるだろう。
ホッブズ『法の原理』には何冊かの翻訳書が出ているようだが、本書の訳者、高野氏は早稲田を卒業後に藤原保信氏とともに本書の翻訳をはじめ、それから数十年をかけて本書が完成したのだという。相当読みやすい訳文になっているのに十分理解できなかったのはぼくの能力のゆえだろう。
なお、巻末の加藤節氏の解説によれば、わが国のホッブズ研究は水田洋、福田歓一氏らの第1世代に始まり、藤原氏らの第2世代、高野、加藤氏らの第3世代を経て、現在の第4世代では聖書解釈学に基づく研究や中村敏子氏の『トマス・ホッブズの母権論』などこれまで触れられなかったテーマを扱う研究が出てきているという。ぼくは、第1期かせいぜい第2期の自然権思想や社会契約論者としてのホッブズに光を当てた議論に関心があり(『近代人の形成』!)、それ以降の議論は(読んでいないが)些末な感じがする。何のためにホッブズを研究しているのかが分からない。第1世代への反発、反「近代」主義なのだろうが。
アダムとイヴの子孫は母子相姦ないし父子相姦か兄妹相姦によるしか子孫をもうけることはできなかったはずであるというダニエル・ゲラン(だったか)の批判と、ホッブズの「産めよ殖えよ」の聖書解釈、近親相姦批判は最近の研究ではどのように止揚されているのか(そんなことを最近の研究が論じているかは知らないけれど)、興味のわくところである。これも些末な興味だが・・・。
2021年7月2日 記
※ 2021年7月3日 追記
ホッブズは「自然状態にあって人は万人の万人に対する闘争状態、すなわち弱肉強食に陥ってしまうため、人々は契約によって自己保全のための権利を絶対権力=国家に移譲した」とか覚えていたが、高校の教科書(柴田三千雄ほか『新世界史(改訂版)』山川出版社)を見ると、「ホッブズは自然法を解釈しなおして、人間は自然状態においては『万人の万人に対する闘争』状態にあるため契約によって国家をつくったとし、個人は自然権を主権者(国王)に譲渡したのだから主権者に服従するのは当然だとした(『リヴァイアサン』)。この理論はイギリス王政復古の専制政治を弁護する結果になったが、神権ではなく経験にもとづく人間の観察から主権の根拠を論じた点で画期的であった」と書いてあった(204頁)。
なるほど、と思った。『リヴァイアサン』を読まなければならないが、最後の部分などは『法の原理』の第1部にも当てはまりそうである。ホッブズは誰のどのような行為の「観察」から、「怒り」や「復讐心」や「嫉妬」について論じたのだろうか。