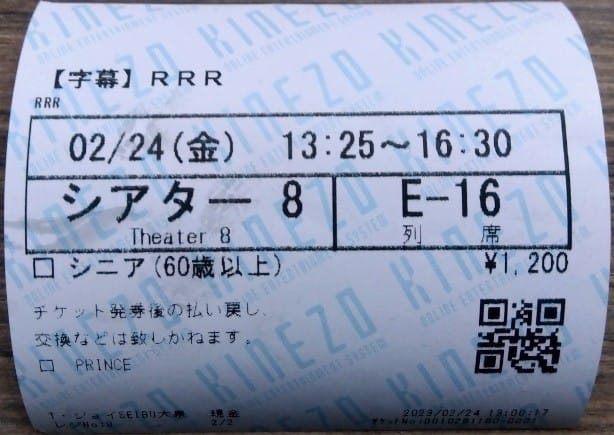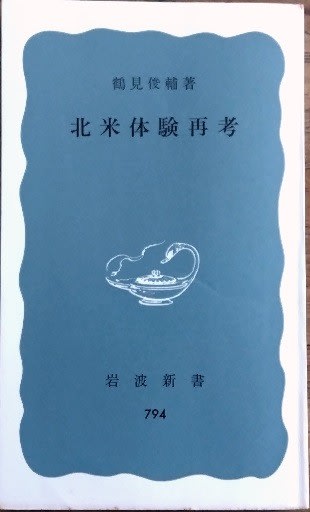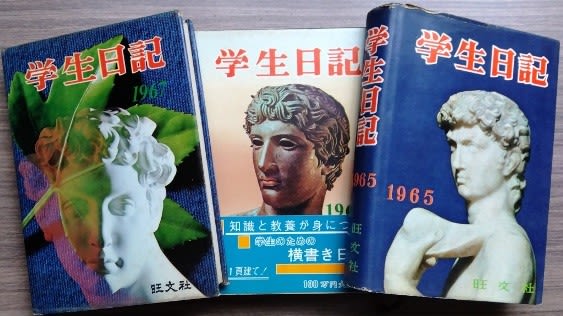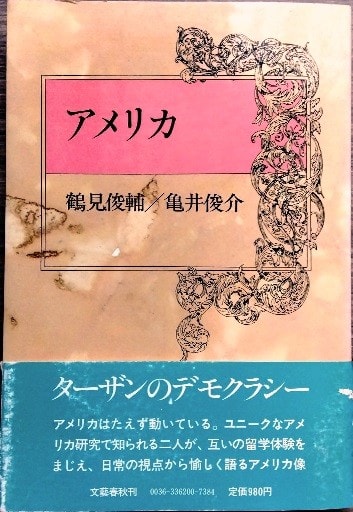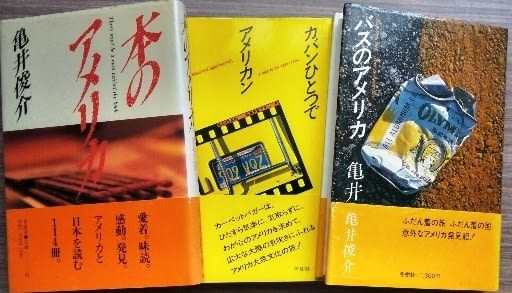インド映画『R R R』を見てきた。
何人かの知人が面白かったというので期待して見に行ったのだが、T - Joy では、入口から会場まで、ポスターの一枚すら貼られていなかった。
上映も一日2回だけ。平日の昼だったので、観客の入りは3分くらいか。
チケットに「字幕」と明記してあったのにも驚いた。劇場公開の外国映画が字幕なのは当たり前のことで、吹き替えの映画を映画館で見たことなど一度もなかった。最近では吹き替え版で劇場公開され\る外国映画もあるのだろうか。
内容は、シルベスター・スタローン『ランボー』のインド版といったところ。
インド映画を見たのは、『踊るマハラジャ』『クイズ・ミリオネア』(だったか)につづいて、3本目である。前2本は面白かったので、期待して見に行った。歌あり、踊りありで、いかにも「インド映画」という風ではあったが、3時間は長すぎる。2時間以内に編集できる内容だろう。
ちなみに、題名の “R R R” とは、“water”、“fire”、“interval” の3つの単語の中の “R” ということらしい。
1920年代、イギリスの植民地時代のインドが舞台で、残虐、凶暴なイギリス人総督とその妻が登場する。こんな白人優越主義者で、残虐な性格のとんでもない総督夫婦を演ずるイギリス人俳優がよくいたものだと感心した。しかし帰宅後にネットで俳優の素性を調べてみて納得した。2人ともアイルランド系のイギリス人だったのである。

17世紀のアイルランドは、イングランド国王が任命したダブリン総督(王代官)によって支配されていた。アイルランド人はカトリック教徒が多かったために弾圧を受け、1649年にはクロムウェルが指揮するイングランド軍によるカトリック教徒大量虐殺事件もおきている。
このようなアイルランドの歴史をふり返れば、アイルランド系の「イギリス人」が、イングランド・ウェールズ人とインド人のどちらに共感をおぼえるかは、簡単には断言できないだろう。イングランドから派遣された悪代官(総督)に対する抵抗という点では、むしろインド人に共鳴するアイルランド人もいるのではないか。
映画は期待したほどではなかったが、帰宅後に、堀越智『アイルランドの反乱--白いニグロは叫ぶ』(三省堂新書、1970年)を復習し(アイルランド人は「白いニグロ」と呼ばれていたのか!)、近藤和彦『イギリス史10講』(岩波新書、2013年)の該当箇所を読み直すきっかけになったのだから、良しとしよう。
2023年2月26日 記