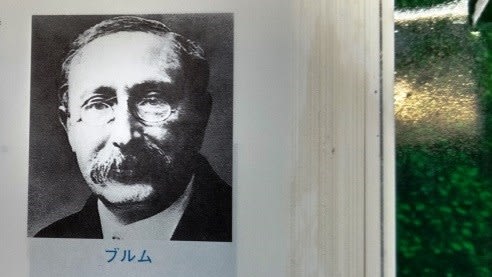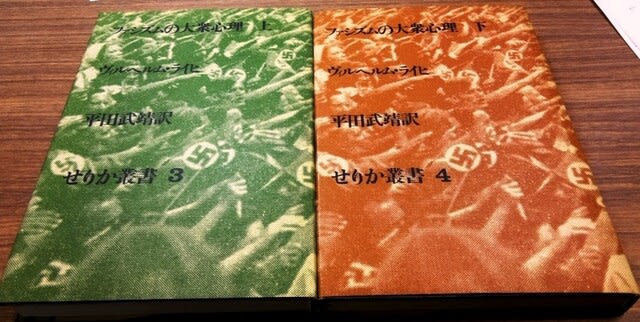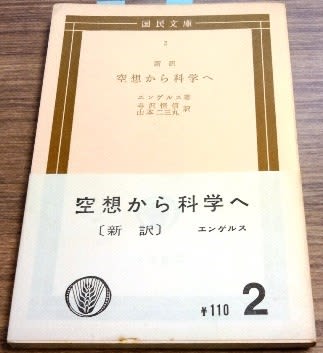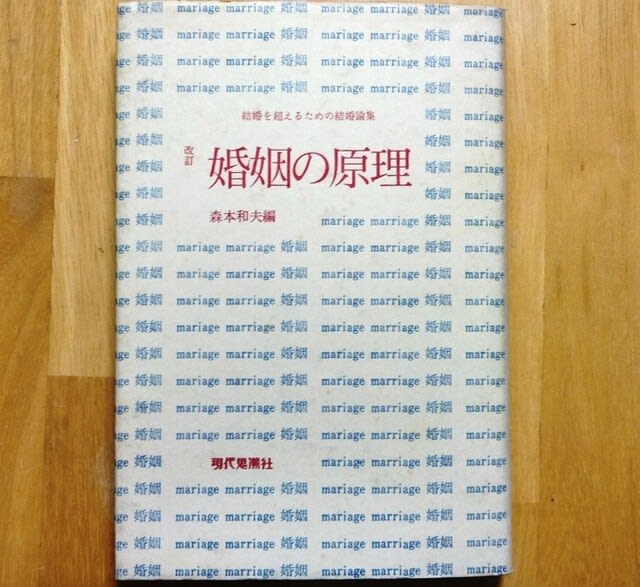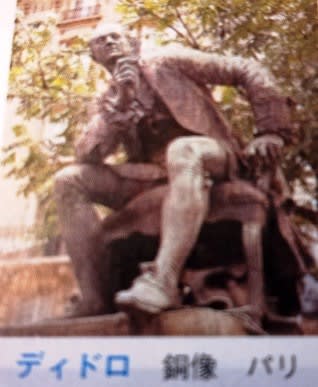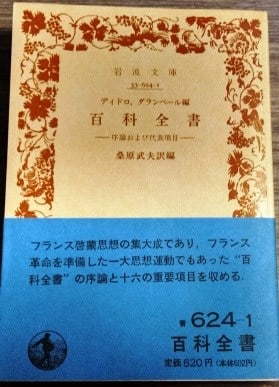ルイ・アントワーヌ・ドゥ・ブーガンヴィル『世界周航記』(1771年)から「タヒチ島」に関する部分を読んだ(「17・18世紀大旅行記叢書(2)」岩波書店、1990年)。
原書の正式な書名は「1766、1767、1768および1769年の国王のフリゲート艦「ラ・ブードゥーズ」と改造輸送船「レトワール」による世界周航記」というらしい。
ブーガンヴィルはフランスの法服貴族一族の出身で、ダランベールら当代一流の人士から教育を受け、数学の分野で才能を発揮した後、イギリスとのカナダ争奪戦に陸軍士官として従軍するが、敗北後に海軍に転じて、この航海の指揮官となる。
ディドロ『ブーガンヴィル航海記補遺』や、ダニエル・ゲラン『エロスの革命』にユートピアのように援用されるブーガンヴィルが見聞したとされるタヒチの習俗のうち、どこまでがブーガンヴィル自身が見聞した事実として書き残したものなのかを知りたくて、図書館から借りてきて読んだのである。
面白い本だった。
最初に、彼は、世界一周の航海に関して先人たちが残した文献記録を要約、整理し、本航海の周到な準備について記述した後に、いよいよフランス、ナントから2隻の船、400名の乗組員で出航する。正式の書名にあるフリゲート艦ラ・ブードゥーズ号と改造輸送船レトワール号である。
南アメリカ、太平洋(当時は「南海」と呼ばれていた)、南太平洋諸島をめぐり、バタヴィアからフランス、サン・マロに帰港するのだが、航海の記録、暗礁などの海図、発見した島々の所在などは、オランダなど各国が機密としてきたのだが、彼は航海によって明らかになった事実を調査報告として書き残すという立場を貫く。
それまでの海図の正確性や誤り、航路の位置の測定法、錨を下ろす地点の情報などから、上陸ないし通過した島嶼の住民の友好性、凶暴性(メラネシア島)など、当時の航海者には必須だが現在のぼくには不要な情報もかなり書かれている。
※ ただし訳者山本淳一氏の巻末解説によれば、そうは言いつつもブーガンヴィルはタヒチ島の緯度、経度を不正確に記述するなど、「意図的な隠蔽」の疑いがあると指摘されている。
さて、ラプラタ川から太平洋に出て、南太平洋の島嶼部の暗礁や浅瀬の航行に苦労した後に、彼はタヒチ島に到着する。

見慣れない船を見つけて、現地人たちが数百隻のカヌーに乗って彼の船に近づいてくる。どうも彼ら現地人は遠来の航海者に出会うのは初めてではないようだ。
船上でのポトラッチ(贈与合戦)が始まる。船乗りたちが上陸してからも贈与はつづく。現地人たちは、ココヤシ、バナナ、雌鶏、ハト(食用で美味という)、貝殻などを贈り、ブーガンヴィルらは鉄(とくに釘がありがたがられたという)と耳飾りを贈った。
タヒチの男たちの多くは長身で、均整のとれた体つきをしており、顔だちは西欧風だった。耳に孔をあけて真珠の輪を吊るしている。女性も美しい身体をしていて、腰と尻に青い刺青を施している。
彼らは男女ともに、全裸に近い状態で布一枚を腰に巻いているだけだったが、遠来の「タイヨ」(友だち)の前で、娘たちはその布さえ脱ぐことを促され、恥らいながら従っていた(193頁~)。
そして、女性も提供された。招待されたあるフランス人船乗り(料理人)は、現地人の手で全裸にされ、衆人環視の中で現地の娘との性行為を促され、船に逃げ帰って来た。上官には首長の醜い妻が提供されたとある。
彼らは「愛」をもっとも重視し、たえず快楽の中に生きているーーと彼は書く。
一夫多妻制がとられていて、妻の数が多いことが富者の唯一の贅沢とされる。子育ては男女が共同で行い、弱い性(女性)に家事や耕作という辛い仕事を押しつけるような因習はタヒチにはない。
妻は夫に全面的に服従する義務があり、夫の同意のない不貞は「血をもってすすぐ」ことになるが、夫の同意を得ることは簡単で、むしろ夫から不貞を急き立てる。嫉妬は彼らには無縁の感情である。
結婚が非宗教的な契約なのか、宗教上の聖別を受けるのか、離婚があるのかは不確かだったが、娘たちはまったく遠慮なく心の傾き、感情の掟に従う。行きずりの多数の愛人があったことは、後に彼女が夫を見つける際の妨げにはならない(220‐221頁)。
--簡単な「タヒチ語語彙集」しかもたなかったブーガンヴィルたちがよくぞこのような委細を聞きだせたものである。この翻訳本では原書には附録についていた「タヒチ語語彙集」が省略されているが、これはぜひ収録してほしかった。ブーガンヴィルがどの程度の語彙によってタヒチ人の習俗を聞き取ったのかは、彼の記述の正確性を判断するうえで必須と思う。
彼らの道具を使う技能と知力は優れており、黒石でできた石斧だけでカヌーを作り、星だけを頼りに数週間も正確に航海する(224頁)。
タヒチ人には所有の観念はなく、生活に必要なものは立ち寄った家から取ってくる。航海者たちの物も盗む。ポケットから銃を盗んだりするので、ブーガンヴィルは彼らを「スリ」と呼ぶ。
同じ島内では敵対関係はないが、他の島とは戦争があり、男は殺し、女は見逃すが時には妻にする例もある。島民の間には不平等があり、首長には島民の生殺与奪の権利がある。重要な決定(ブーガンヴィルらに上陸して設営することを許すか否かなど)は首長と顧問会議で決まる(230頁)。
ブーガンヴィルらの以前にもイギリス人が来島しているが、彼らは性病を置き土産に残していった。
そして、ブーガンヴィルは一人のタヒチ人青年(と行っても31歳)をフランスに連れ帰っている。かれはフランス語をほとんど理解できなかったが、オペラを見に行くことを楽しんだという。
※ ただしブーガンヴィルは南太平洋の島々のすべてがタヒチ島のような理想郷だったと言っているわけではなく、ペシュレ人の悲惨な生活も紹介して、南太平洋に理想的な「自然状態」を夢想した哲学者たちを批判してもいる(山本解説による)。
2021年の今読んでも面白いのだから、18世紀のフランス人にも興味深く読めただろう。
ブーガンヴィルは、何一つ観察したこともないくせに、薄暗い書斎の中で議論にふけってご大層な理論を述べる哲学者を軽蔑しているが(21頁。訳者の注釈によればルソーの『人間不平等起源論』に対する批判だそうだ)、ディドロやフーリエがブーガンヴィル『世界周航記』から影響を受け、タヒチにユートピアを見出そうとしたことは理解できることである。
2021年4月26日 記