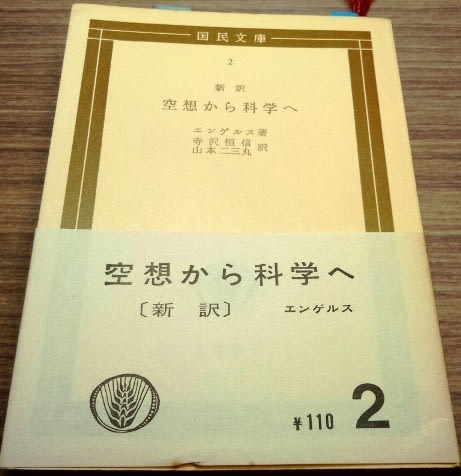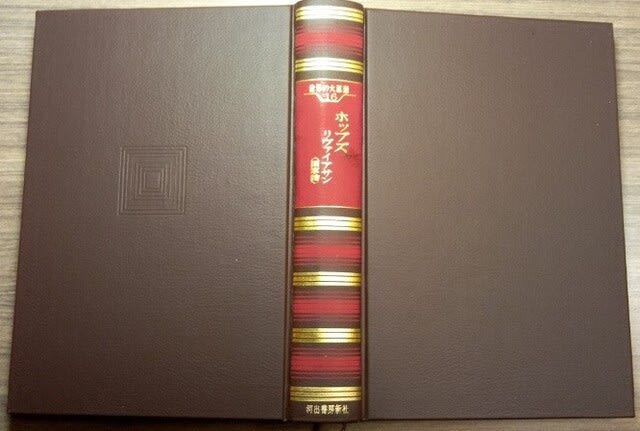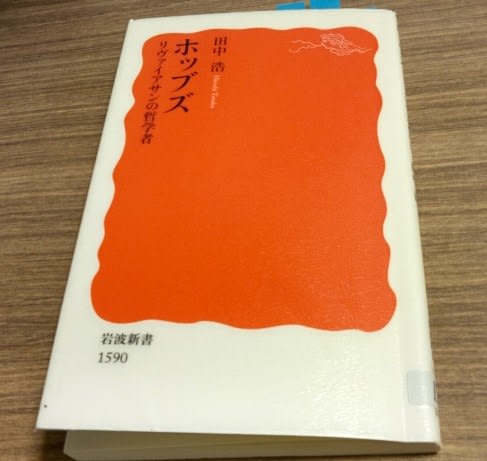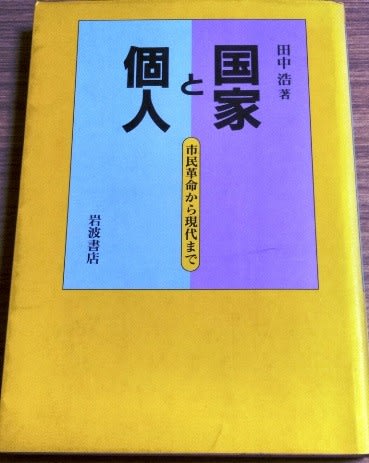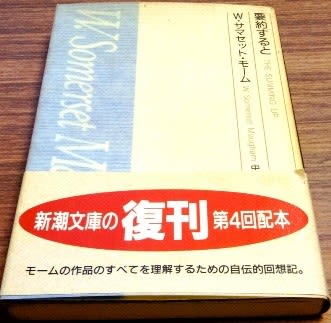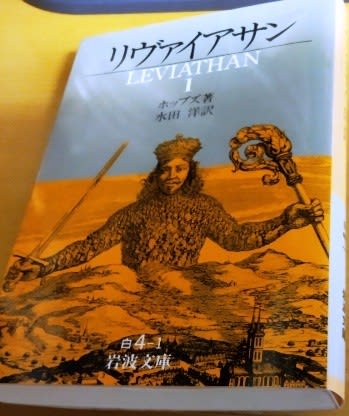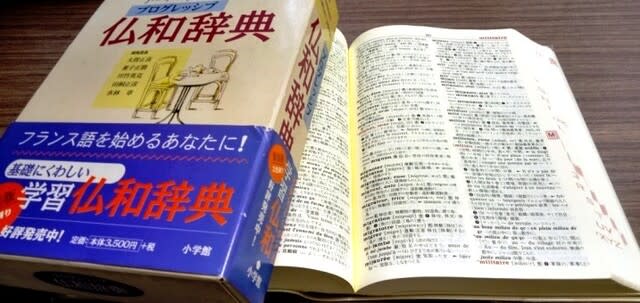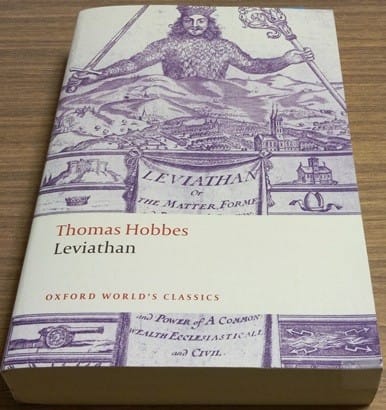荒井輝允『軽井沢を青年が守ったーー浅間山米軍演習地反対闘争1953』(ウインかもがわ、2014年)を読んだ。
買った店は、国道18号沿い、マツヤの隣りにあった平安堂軽井沢店で、2014年8月19日11時09分のレシートが挟んであった。
出版された直後に購入したようだが、パラパラ眺めただけでちゃんと読んでなかった。昨日、眼科の定期検査があり、何か待合室で読む本を持って行こうと思い、カバーのかかったままの本を何だろうと思って本棚から取り出したところ、この本だった(下の写真は平安堂のブックカバー)。
分量、文字の大きさ共に待ち時間に読むのに程よく、知っている人や場所(追分公民館、西部小学校、軽井沢中学校など)も登場する面白い本だった。
敗戦後の1953年に、軽井沢にアメリカ占領軍が演習場を作ろうとしたこと、それに対して、地元の大日向、三石(ともに満蒙開拓団の帰村者が開拓した地域である)や、追分、借宿の青年団が中心になって、さらに千ヶ滝西区!、中軽井沢、発地などの青年らも参加して反対運動が起こったことは、今となっては軽井沢が好きな人の中でも知らない人の方が多いのではないだろうか。
最終的には軽井沢町、長野県全県をあげての反対運動によって、計画発表から3か月後に米軍およおび外務省が設置を断念したという事件である。
著者は、追分で農業を営んでいた青年団員で、この反対運動の中心メンバーの一人だった。
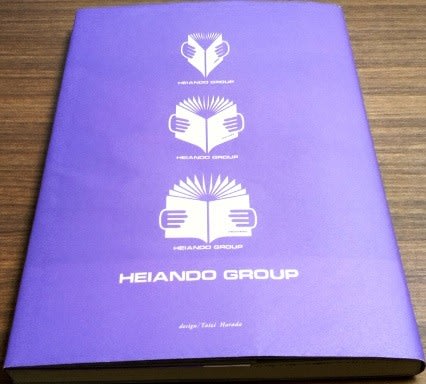
米軍の計画は、実は軽井沢町長らが、町議会や町民に秘密のまま、独断で外務省に誘致を申し入れたのが契機だった。
1953年4月2日に、突如、占領軍と外務省の担当者が軽井沢町にやって来て、計画を発表した。その夜にはグリーン・ホテルで(!)歓迎パーティーまで催されている。
翌日このことが信濃毎日新聞で報じられると、翌4月4日には三石、追分、大日向、借宿の4集落が反対を決議し、またたく間に反対の動きは(軽井沢町)西部区長会、軽井沢町全域、さらに長野県全県、国会への陳情へと拡大して行く。
満蒙開拓で辛酸をなめさせられ、敗戦後に引き揚げてきて帰住した浅間山麓でようやく開墾が軌道に乗ったところで、演習地のためにその土地を接収され三たび離村を強いられることは到底認められないという青年たちの強い思いが出発点にあった。
町の調査団による富士山ろくの米軍演習場の調査(調査委員に星野嘉助の名前もある)により、周辺の環境破壊や、いわゆる“パンパン”が町中を歩きまわる姿などの映像が紹介されると、反対運動は勢いを強めた。
追分という土地柄もあって、文化人の支援の輪も広がった。
たまたま堀辰雄の葬儀に参列した橋本福夫が支援に加わった。橋本は戦後数年間追分に移住して翻訳の傍ら農業を営み、追分の区長を務めたこともあった。橋本は戦前から島崎藤村の小諸学舎に参加しており、その閉鎖後は、教え子である油屋主人(の息子)小川貢に請われ、追分に開講された「高原学舎」で無償で講義を行なうなど、著者も含めた地元の青年たちと交流があった。
橋本は、後に青山学院の英文科の教授になった英文学者で、翻訳家でもあったが、ぼくは、その名前をサリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」を日本で最初に翻訳した人として知った(彼は「危険な年齢」という邦題で出版した)。橋本は、後に堀辰雄宅の敷地の一角を譲受けて追分に永住し、没後はご夫妻とも追分泉洞寺の墓所に眠っているという。
この反対運動は、当初から東大地震研究所の反対が援軍になっていた。地震研の観測所が浅間山麓、峰の茶屋にあった。それもあってか、反対運動の支持者の中には、当時東大総長だった矢内原忠雄や息子の矢内原伊作の名前も登場する。ぼくは何かの記事で、矢内原らの文化人が主導した基地反対運動のように思っていたが、これは誤解だった。
著者らは、橋本の助言もあって、むしろ文化人の間の意見の対立に巻きこまれないように注意していた様子がうかがえる。著名な追分、軽井沢文化人でこの運動にかかわらなかった人もいるが、著者らは、青年団や婦人会、在住の文化人、労働組合、教員組合だけでなく、当初は誘致推進派だった町長らをも反対運動に寝返らせ、町内に広い人脈をもつ中軽井沢地区のボス的人物をも反対派に巻き込むなど、人間関係を軸にして幅広い反対運動を繰り広げている。
反対派の事務局は、何と町役場の中に設けられたという!
演習地反対全町協議会の委員長になったのは田部井健次だった。
彼は戦前に、大山郁夫の日本労農党の書記長や総評書記長などを務めた人物で、治安維持法による弾圧も受けたが、戦後は画家として千ヶ滝西区(!)に住み、西区長を務めていた。演説や交渉はお手の物だったようで、アメリカ軍との交渉での発言はなかなかのものである。
「日本はアメリカ軍のおかげで民主主義の国になった、民主主義のアメリカが日本の民衆の意思を無視して演習場を設けるようなことはしないことを確認せよ」、「軽井沢は国立公園の中にある、アメリカ本国で国立公園の中に軍の演習場は1か所でもあるか」、「地震研究所の観測に影響することが明らかになったら演習地計画を撤回せよ」といった趣旨を穏やな口調で発言し、アメリカ側から言質を取ったという。
※ 田部井には『軽井沢を守った人々』という著書があるが、残念ながらぼくは持っていない。その本の紹介が朝日新聞1987年4月10日付に載っている(下の写真)。版元の「三芳屋」は、あの中軽井沢駅北口や旧軽井沢テニスコート通りにあった書店だろう。確か、信濃ものの本の出版も手掛けていた。
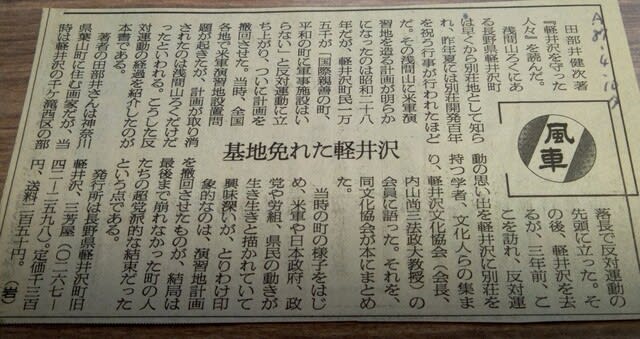
それに引きかえ、日本政府側の岡崎外務大臣や井関アジア局長は、「日本はアメリカに守ってもらっている」、だから浅間山麓の演習地化に反対するな、という情けないアメリカ追随に終始した。橋本の手紙には、長野県選出の国会議員が役に立たないことへの不満も書かれている。
しかし、反対運動から3か月後の7月16日に、その外務省から計画撤回が発表された。もちろん背後にあるアメリカ側の意向だろう。外務省は、表向きは、浅間山にある東大地震研究所の地震観測への影響を中止の理由にあげたが、本書を読めば、演習地建設の中止が反対運動の成果であることは明らかである。
当時の衆議院議長が千ヶ滝開発に利害関係のある堤康次郎だったことも幸いしたようだ。ーー西武(国土計画)の社史や堤の伝記などにはこの運動に関する記述はあるのだろうか。

江戸時代の軽井沢、沓掛、追分は中山道の宿場町(浅間三宿)として栄えたが、いわゆる「めしもり女」(娼婦。吉原から流れてきた娼婦もいたという)が2~300人もいるような宿場だった(上の写真は明治末期の追分、分去れを撮った写真の絵葉書。今も残る常夜灯が見える)。
それが、信越線が開業して以来は衰退の一途をたどり、1953年頃になると追分の旅籠も廃墟と化するものが少なくなかった。国際観光都市に指定されていたものの、万平ホテル、三笠ホテルは米軍に接収されており、観光業も振るわなかった。そのため、町の有力者の中には、軽井沢を赤線地帯に指定してもらおうという意見や、米軍演習場を誘致しようという意見が起こったという。
ーー軽井沢が現在も、曲がりなりにも軽井沢らしさを保つことができているのは、偏えに彼らの運動のおかげである。米軍は石尊山で(北朝鮮との山岳戦を想定した)軍事訓練を実施しようとしていたというのだから、もし実現していたら、夏の夕刻の石尊山のすそ野は悲惨な光景になっていただろう。
近年の商業施設の乱立と別荘地の乱開発は、米軍の演習場建設に劣らぬ惨禍を軽井沢にもたらしているが、もはや反対運動の気運さえ見られない。沖縄でも米軍基地反対の民意を無視した基地建設がすすめられるなど、1953年の軽井沢以上にアメリカへの従属化が進行している。
浅間山に心があれば、何を思っていることだろう。
その他、本書で印象に残ったことをいくつか。
反対運動には、東大をはじめ東京の大学生たちが支援に駆けつけたという。彼らは、ビラ作成、ガリ版印刷、ビラ配りや、人手の足りない農家での援農なども行なった。時には地元の人たちとフォークダンスをすることもあり、異性と手をつなぐという日常ではない機会をあたえられ、連帯感も強まるとともに、恋が芽生えることもあったという。
--1950年生れのぼくでも、この気持ちは分かる。高校の文化祭の後夜祭のフォークダンス、マイムマイムやオクラホマ・ミキサーなどは、近所の女子高生と手をつなぐ唯一の機会だった。そして1969年の新宿西口広場のべ平連のデモでは、腕を組んだ女子大生との間に連帯感も恋心も芽生えた。
追分「すみや」は、橋本が推進した消費者組合、生活協同組合運動から生まれたとある。もともと旅籠だった「すみや」の土間を借りて始めた購買所が、後の「スーパーすみや」になったという。ぼくが毎夏の終わりにシャインマスカットなどを買いに行っていた追分の、あの「すみや」だろうか。
著者の実家は、高等文官試験受験生のための民宿をやっていたという。ぼくの叔父が学生時代に追分学生村に滞在して地元のMさんと知り合ったことが、わが家族と軽井沢との関係の始まりだった。
発地の青年団との会議の際にはドジョウが跳ねる泥湿地の道路を自転車で行った話、恩賀や妙義での反対運動では計画撤回まで数年を要したこと、米軍基地周辺での売春の実態を暴いた『日本の貞操』の読書会をやったことなどなど。--中学か高校生の頃に、父親の書庫にあったこの本をエロ本かと思って中を見たところ、真面目な告発本で驚いた(がっかりした)思い出がある。
そして何より、わが千ヶ滝の家を建ててくれた大工さんと思われる方も、反対運動の活動家の1人として登場する(本当はお名前を書きたいのだが、確認できたわけではないし、ご了解も得ていないので書かない)。
わが家は1968年の建築だから、反対闘争から15年しかたっていなかったのだ。それからすでに50年以上が経過し、わが家もあちこちガタがきているが、基本的なところはいまだしっかりしている。
この方とはぼくも何度かお会いしたことがあるが、演習場反対運動に加わったことはまったく話題に出なかったと思う。穏やかで大へんに誠実な大工さんだった。こんな経歴のある大工さんに作ってもらった思い出の家となると、表札に彼の名前を刻んでおきたいくらいで、戦後民主主義世代のぼくの目が黒いうちは壊すことはできない。祖父母や両親の思い出もこもっている。雨露をしのげるうちは、修繕でしのいでいこう。
2021年9月30日 記
※ 『橋本福夫著作集Ⅰ』を読んで、橋本氏に関する記述を若干訂正した。2021年11月9日 追記