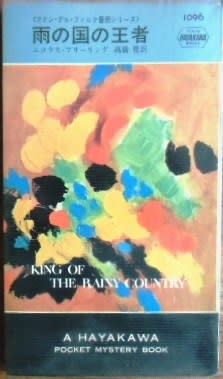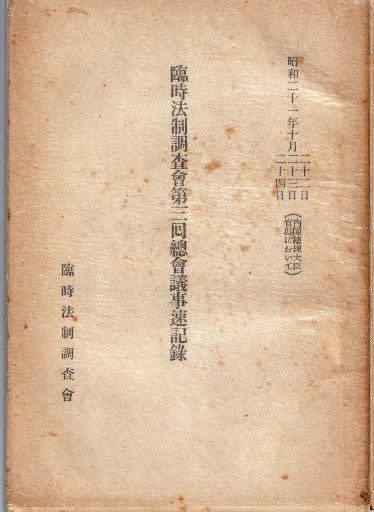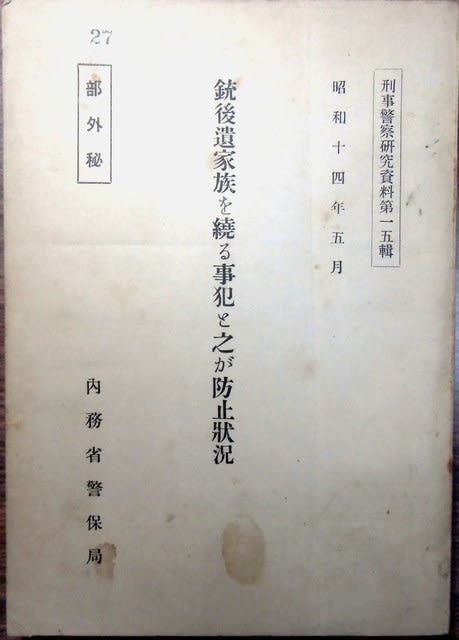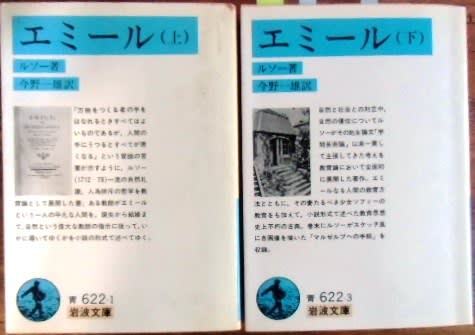★ 陰木達也「帝国期日本の法学者の婚姻史研究と東アジアーー「招婿婚」概念の成立と展開を手がかりに」比較家族史研究34号(比較家族史学会、2019年。ただし手元に届いたのは2020年5月)
この論文は、中川善之助が、自ら編集した『家族制度全集(第1巻)史論篇、婚姻』(河出書房、1937年)に執筆した「婚姻史概説」で提起した「招婿婚」(しょうせいこん=ムコ取り婚)概念を出発点として、「招婿婚」をめぐる議論の展開を日本および台湾を中心に検討したものである。
しかし、ぼくが興味を持ったのは、招婿婚の展開それ自体ではなく、「婚姻予約有効判決」と呼ばれている大正4年1月26日の大審院連合部判決に対して、岡松参太郎が加えた批評について検討した個所である。
岡松は「無過失損害賠償責任論」で有名な京都帝大の民法学者だが、後藤新平から委嘱を受けて日本統治下にあった台湾原住民の旧慣調査に当っていた。その岡松が、この大審院判決を契機として、儀式によって婚姻の成立を認める台湾の蕃族の慣習と同様に、日本においても儀式によって婚姻の成立を認めるべきであると提言していたのである。当時のわが国も、婚姻の儀式によって婚姻の成立を認めるのが社会一般の慣習であり、近代西欧法を継受した明治民法の届出婚主義(婚姻届出によって婚姻は成立するとした)は当時のわが国の慣習上は無理があるとして、立法者意思には反するが届出婚主義を廃棄し、儀式を経た事実上の夫婦に婚姻の効力を付与すべきであると提言したのであった。
岡松の一連の業績を詳細に検討したきわめて有意義な論考であり、岡松の上記大審院判決に対する評釈を読んでいなかったぼくには大変に勉強になった。大学図書館が再開されたら、著者が引用した岡松の論考を読みに行こうと思う。
惜しむらくは、唄(ばい)孝一の同判決にかかる一連の論文への言及がないことである。大審院判決の意味を究明すべく、事件が起きた下妻を何度も訪れ、(昭和28年当時)現存する当事者ら(原告、被告を含む)に面談までした、唄の論文を読んでいたら、さらに深みを増したものと思う(唄論文を読んだけれども、援用する価値なしとしたとはぼくには思えないのだが)。
★ 唄孝一『内縁ないし婚姻予約の判例法研究』』(唄孝一・家族法著作選集第3巻、日本評論社、1992年)

明治31年(1898年)制定の明治民法は、夫婦が婚姻の法的効果(同居協力義務、貞操義務、婚姻費用分担義務、死亡時の配偶者相続権、離婚時の財産分与請求権など)を享受するためには、戸籍法の方式に従った婚姻の届出を必要とした。
立法者はいわゆる「内縁」を法的に保護する必要を認めておらず、当初は大審院判例も内縁の保護を否定した。表向きの理由は、近代法が要求する届出をしないようなカップルはたんなる私通、野合にすぎず、法的保護に値しないということだが、ホンネでは内縁や婚約を不当に破棄する(大部分の場合は)男の都合を優先させるためだったといわれる。明治民法の底流には「男」の都合が貫かれていた。
しかし明治民法制定当時のわが国では、習俗に基づいた婚姻の儀式を挙げれば二人は社会的に夫婦と認められたため、あえて婚姻届出をしないまま共同生活を営むカップルも少なくなかった。もしそのような関係を正当な理由もなく一方的に破棄されたとしても、破棄された側は泣き寝入りをするしかなかったのである。
これに対して、穂積重遠ら一部学説が批判を加えた結果、大審院は大正4年1月26日の連合部判決によって、かかる関係(それが「内縁」だったかは、後に唄論文が疑問を呈することになる)を「婚姻予約」と法律構成して、正当な理由なく「婚姻予約」を破棄した当事者(多くは男)に対して債務不履行による損害賠償の支払いを命じうると判決した。
ちなみにこの事件で訴えていた原告の女性は、結論的に敗訴しており、損害賠償を得ることができなかったのだが、この点も当時の民事訴訟法学の限界だったのか、大審院に何らかの意図があったのか謎が残っている。
さて、上記のように、この大正4年大審院判決に関しては唄の一連の調査研究がある。唄の論文は今回初めて読んだものではないが、陰木論文へのコメントの不十分な部分を補うために紹介しておきたい。
大正4年大審院連合部判決については、一般的には上記のように理解されてきたが、昭和30年代になると、本書に収録された唄孝一ら(唄および当時唄ゼミに所属した都立大学学生2名。「学生も研究者」というのが唄の持論だったという)の一連の現地調査、研究によって、当該事案の当事者は、何がしかの婚礼の「儀式」は行ったようだが、その3日後には女性は実家に帰って(返されて)いることが判明した。
はたしてこの2人の関係が、一定期間の共同生活の継続を必要とする「内縁」といえるかどうかについて唄は疑問を提示し、むしろ「足入れ婚」(唄は「アシイレ」と表記する)などと称する「試し婚」の段階か、それよりさらに前の段階--嫁が実家を出る儀式、婿宅での嫁取りの儀式、親戚縁者を招いての宴会の儀式、同棲の開始といった一連の段階的な「婚姻の儀式」の途中--の「未完成婚」、あるいは判例の文言通り純粋な「婚姻予約」(唄は「純粋婚約」という)だったかもしれないことを示唆したのである。
★ 中川善之助「婚姻の儀式(一~五・完)」法学協会雑誌44巻1~5号(昭和元年、1926年)

大正4年大審院判決は、「婚姻の儀式」を経た(しかし婚姻届出はしていない)当事者の関係を「婚姻予約」として法的に保護することを認めたが、この「婚姻の儀式」を徹底研究したのが、当時は若手研究者で、後に家族法学の第一人者となる中川善之助であった。
中川の本論文は、執筆当時(1926年)のわが国において「婚姻の儀式」が婚姻法上いかなる意義を有するかの解明を目的とする。執筆の契機となったのが、まさに上記の大正4年大審院連合部判決だったことは、論文自体から明らかであるが(連載第4回、法協44巻5号87頁以下)、この大審院判決は「内縁」関係を「婚姻予約」と法律構成して保護した判決であるとする通説的な理解のさきがけとなった論文(の一つ)である。
陰木論文に触発されて、今回改めて読み直した。大変な勉強の成果であるにもかかわらず、中川らしく、論述はおおらかである。
唄が中川らの理解に異議を唱えたことは上述のとおりであり、この大審院判決は「内縁」を保護したのではなく、実際には、試し婚、未完成婚、ないし純粋な婚約関係の保護を認めたにすぎないと考えられるようになった。しかし、この判決をきっかけに、わが国において(民法には規定のない)「内縁」関係が判例法によって少しづつ保護されるようになったことは歴史的な事実であり、その後の中川がこの流れに掉さしたことも間違いない。
中川論文は、婚姻における「儀式」の意義と法的効果の歴史をさかのぼり、広い地域と民族について検討した。法律学というよりは、民族学や人類学的な記述が論文の中心になっている。基本的には法律進化論の立場に立ち、歴史的に諸民族の間で、社会が原始的な状態から発展するに従って社会の最も基礎的な制度である婚姻制度は、安定した強固な(永続的な)制度として保障されるようになり、それにともなって「婚姻の儀式」が確立することになる。
中川によれば、婚姻の儀式は、婚姻の「浄化性」と「公示性」を社会的な動機として実施されてきたのであり、社会が複雑化するにつれて婚姻の儀式が強く要請されるようになったという。「公示性」の要請は説明するまでもないが(婚姻成立を公に示す)、婚姻の儀式のもつ「浄化性」ということの意味がぼくにはよく理解できなかった。
中川によれば「儀式は常に之に依て結合する性的関係を社会意識に対して浄化する作用を有つ」というのだが(法協44巻1号49頁)、儀式がなければ「不浄な」私通、野合に過ぎない性的関係が、儀式を経ることによって「浄化」されるという意味なのだろうか。広辞苑を引いてみると、「浄化」には、不潔なものを清潔化するという一般的な意味のほかに、卑俗な状態を神聖な状態に転化することという宗教的な意味もあるようだ。
上記、唄の調査研究のあとでは中川(その先生である穂積重遠)の功績がやや色あせた感は否めないが、中川のこれ程の浩瀚な「婚姻の儀式」研究があったればこそ、わが裁判所は内縁保護の判例法を形成することができたのだと思う。
ただし、わが大審院は昭和初期の段階で、すでに内縁保護の要件として婚姻の儀式を要求しなくなっている。昭和6年2月20日大審院判決は、双方が誠心誠意将来の結婚を約束したのであれば婚約は有効に成立し、結納取り交わしなどの儀式や家族らへの周知は必要ないとしたのである(「誠心誠意判決」などと呼ばれる)。儀式はあくまでも内縁の成立を証明する証拠方法の1つに過ぎず、儀式がなかった場合でも、関係者の供述など諸般の事情を総合勘案することによって内縁の成立が認められる(無儀式主義)。
* ちなみに冒頭の写真は台湾の九份の夜景。「九份」というのは「9家族」という意味で、もともとは9家族によって拓かれた集落から次第に人口が増えていって、その後の発展につながったことによると、ガイドさんが説明していた。映画「千と千尋の神隠し」の舞台にもなったそうで、訪れた当日は大雨だったにもかかわらず日本人観光客であふれていた。
ちょっと無理があるが、台湾の家族に関係がなくもないので。
* * *
さて、きょう6月30日で、定年退職からちょうど3か月が過ぎたことになる。
無職になって、時間があり余るようになったら何をしたいのか、在職中はまったく何の思いも浮かばなかった。
いざ仕事を辞めて時間に余裕ができてみると、夕方の散歩(せいぜい6000~7000歩)とテレビ(ほとんどはBS放送のイギリス・ミステリー)を除くと、結局は読書に費やす時間が大部分だった。しかも、家族関係のものに食指が動いてしまう。
これからの読書計画を立てるために、この3か月間の読書は、なるべくこのコラムに読書ノートを記しておくことにした。3か月でこの程度だから、1年12か月間ではこれを4倍した程度しか本は読めない。あと10年くらい余命があるとして、その10倍程度である。
やはり優先順位をつけて、イギリスの宗教教育関係の判例報告をまず済ませなければいけない。『エミール』だの『告白録』だの、『統治二論』だのは劣後させなければならないだろう。
2020年6月30日 記