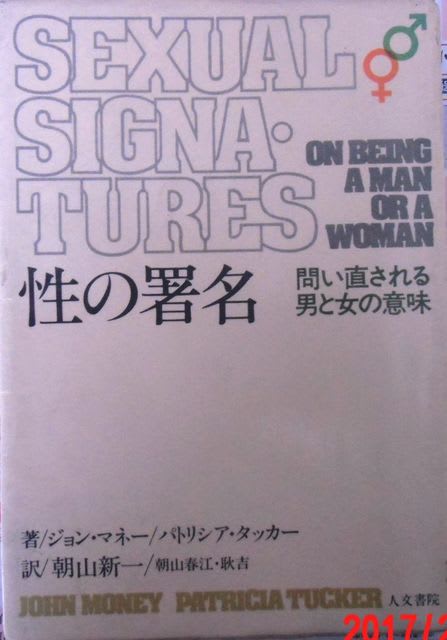ジョン・コラピント『ブレンダと呼ばれた少年――ジョンズ・ホプキンス病院で何が起きたのか』(無名舎、2000年)
カナダのウィニペグ州の片田舎で1966年に一卵性双生児ブルースとブライアン兄弟が生まれた。兄ブルースには包茎による排尿障害があったため、両親は包茎の切除手術を受けさせることにした。しかし未熟な執刀医の電気メスの操作ミスによってペニスに火傷を負った生後8か月のブルースはペニスを切除せざるを得なくなった。
両親は、たまたまテレビでジョン・マネーの自信に満ちた態度を見て、藁にもすがる思いでジョーンズ・ホプキンス病院を受診する。マネーは同病院に所属する性科学者(医師ではない)だが、人間の性自認は生まれながらのものではなく育て方によって形成されるという趣旨の主張を展開して一部の(しかし有力な)医学者やフェミニストの支持を得ていた。ボ―ヴォワール「人は女として生まれるのではない、女になるのだ」の性科学者版といったところだろう。
マネーは、去勢(性器摘出)手術を受けたブルースを女の子として養育させることを提案し、両親もこれに従い名前もブレンダと改める(ブレンダ・リーに因んだらしい)。まったく同一の遺伝的性質を有するはずの一卵性双生児の一方(生物的には男性)の「養育の性」を女性に変更して養育させ、他方(弟)は生物的な性(男性)のままで養育させて、両者を比較することで養育の影響を実証するという願ってもないチャンスを得たのだった。
しかし、この「実験」は失敗に終わる。ブルースはまったく「女性化」することはなく、男の子として男の子の遊びを好んだ。マネーは、彼の行動が「トムボーイ症候群」(要するの「おてんば娘」)にすぎないと一蹴し、両親の努力が足りないと叱咤するが、ブレンダはますます男の子らしくなり、両親が強要する女の子の洋服を着て女の子らしく振舞うことを拒否し、11歳になるとマネーの診察を受けることも拒否する。診察室でマネーから異様な行動を強要されたり、質問を受けたり、さらには医学生に観察されたりすることに耐えられなかったのである(具体的な「診察」の内容は第5章に詳しい)。
後述する本書の原書新版の「後記」によれば、この間ブレンダ一家はマネーの診察を受けるために年に1回ボルティモアのジョーンズ・ホプキンス病院を受診し続けたが、その費用は旅費も含めてすべて、ブレンダ(ブルース)が包茎手術失敗の医療過誤訴訟によって得た損害賠償金で賄われていた。
ブレンダを女の子として養育することがうまくいっていなかったことをマネー自身も認識していたにもかかわらず、この間マネーは自分の仮説の正しさを証明する症例としてブレンダの事例を医学誌に発表し続ける。1975年出版の『性の署名:問い直される男と女の意味』(邦訳は1979年、人文書院。ボーヴォワール著作集の出版社であることも象徴的である。)でも自説の成功例として紹介する(邦訳111頁以下)。
この事例は匿名(仮名)で<ジョン・ジョアン(の一卵性双生児)事例>と呼ばれて世間に知られた。しかし、この症例に疑問を感じたBBCがブレンダを探し出し、実名や住所を隠すことを条件に両親の承諾も得て1980年3月に“Horizon”という番組で紹介する。従来からマネーの仮説や仮説に基づいた「治療」に疑問を抱いていたミルトン・ダイアモンド(ハワイ大学生物学教授)もこの事例に疑問を呈する記事を医学誌に投稿する。ダイアモンドは、若いころから「性自認はホルモンの影響によって胎児の脳に刻印されている」と考えて実験を続けてきた生物学者である。
この番組をきっかけに、両親はブレンダに真実を話し、爾後ブレンダはデイビッドと名前を変え、男として生きることを決意し、本書の著者コラピントとの長時間のインタビューにも応じ、このような悲劇を繰り返さないために実名での発表も許可する。その後、すべてを知ったうえで彼を受け入れる女性と出会い、結婚することになった。妻には前夫との間に3人の子があり、デイビッドはその子らの父親になることもできた。
ここまでで終わってデイビッドには普通の人生を歩んでほしかったが、原書の最新版であるJohn Colapint, “As Nature Made Me:The Boy Who Was Raised As a Girl”(Harper Perennial, 2006)には追記があり、初版刊行後にデイビッドとブライアン兄弟を襲った悲劇を知ることになる。
母親は繰り返し抑うつ症状に悩まされ、父親はアルコール依存となっていたが、弟ブライアンも母親同様の抑うつ症状に悩まされ、仕事を失い、妻に離婚され、子どもの監護権も失い、2002年に薬物を大量に服用して死亡しているのが発見された。両親が兄の治療にかかりきりだったことは幼少期から弟に強い疎外感を与えていた。
弟の死に対して兄は罪悪感を持った。兄デイビッドも定職を失い、さらには本書出版で得た金銭も詐欺師に奪われるなどしてアルコールに依存するようになる。そして、妻から一時的別居を提案された翌日に自殺してしまったのである(“David Reimer : A Tragic Update”Ibid.,P.S.,pp.10-14)。
読み応えのある本だった。しかし本書を読んで私は愕然とした。
本書の中には、「科学者ほど事実を見ようとしない者はいない。彼らは常に自分の仮説によってしか事実を見ようとしない」といった趣旨の言葉が引用されていたが、マネーの症例報告が「ねつ造」とまでは言えないとしたら(本書79~80頁などに引用されたマネーの本症例の報告を読んで判断してほしい)、まさにこのような「科学者」の典型だったのであろう。
いずれにしても、マネーのブレンダ(および弟をはじめ同一家)に対する対応は今日の研究倫理からは決して許されるものではないが、1970年代としても、このような研究が行なわれていたことに衝撃を受ける。無断の梅毒実験で悪名高いタスキギー事件などにも匹敵する事件と思われる。
少なくともわが国では、優生保護法の時代から、未成年者に対する精巣・卵巣を摘出するような不可逆的な不妊手術(優生手術といった)を禁止している(同法3条)。
真実が明るみに出て以降、マネーは本事例について沈黙を貫くことになったらしいが、1997年のダイアモンドの論文によってマネーの仮説は否定され、今日では基本的にダイアモンド説のほうが有力視されているようだが、現在でも(外性器傷害の患者はともかくとして)外性器のあいまいな「性分化疾患患者」に対して生殖器摘出手術を提案する医師は皆無ではないようである。
インターセックスの当事者であり(完全アンドロゲン不応症CAISのようである)、インターセックスの研究者(社会学者)でもあるGeorgiann Davisの“Contesting Intersex”(New York University Press, 2015)は、DSD(Disorders of Sex Development 性分化疾患)という診断名のもとに、医師が両親を誘導して性器摘除も含めた治療を行う近時の傾向を批判する(p.75~, p.90~ほか)。なお、同書は(コラピントの初版(2000年)以降の悲劇的な事実も含めた)ジョン・ジョアン事例、そしてマネーの失墜の経緯も言及がある(p.58~)。
私の関心から言えば、性別決定のような個人の最も本質的な事項に関する決定は本人自身の意思によるべきである。もちろん新生児は自分の意思など表明できないから、両親が医師(セカンドオピニオンを求めることも当然である)や同じ子を持つ親、成長した子などの意見も聞く機会を得たうえで、子の「養育の性」を決定し、必要な治療を決定することになろう。
しかし、その場合でも子の将来の自己決定を妨げる生殖器摘出のような不可逆的治療は回避すべきであろう。腹腔内の停留睾丸はがん化する恐れがあるというのが生殖器摘出を提案する医師の言い分のようだが、エビデンスはあるのだろうか。
個人的には、がん化の可能性にエビデンスがあるとしても、子どもが自分の性別に関する判断能力が成熟する思春期まで待って、上記のような人々の意見も参考にして子ども自身が決定すべきであると思う。
<性別未定>といった中途半端な状態では子どもがかわいそうというのも分からなくはない。「立小便ができない」というだけでいじめられる世界であるが、学校のトイレも洋式化が進んでおり、多目的トイレも増えている。ブレンダのドキュメントを読んだ後では、新生児期に医師に誘導された両親が決定した性別との違和感に思春期以降になって悩むことのほうが、学校でのいじめなどよりはるかに子どもにとっては悲劇的なことに思えてならない。
がんなら運命とあきらめもつくだろうが、自分のあずかり知らないところでの両親(というより医師)による生殖器切除を人は運命と受け入れることができるだろうか。
重い読後感の残る本であった。しかし性別に少しでも関心のある者にとっては必読の本である。
2017/2/5 記
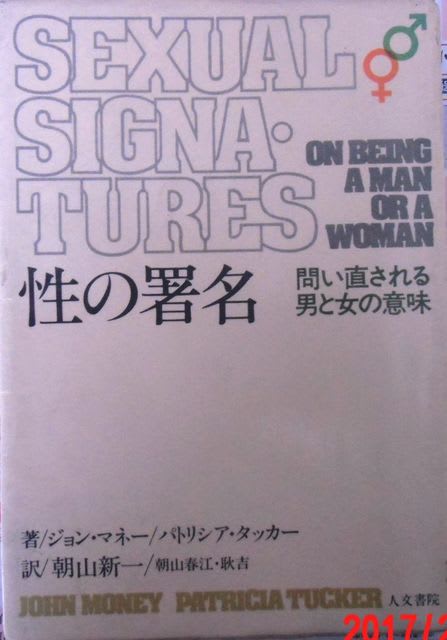
ジョン・マネー『性の署名』はamazonで1円(+送料257円)で購入した。評価は「良い」だったが、大嘘だった。ボールペンによる傍線は数十か所におよび、ページ角のオレも数ページあった。
腹が立ったが(もうこの古本屋では決して買わないが)、前の所有者が傍線を付けた個所が、まさにコラピントらによって今日では否定されている個所(言語獲得と性自認が同時期に起こるのは偶然ではない、など)なので、当時どのように読まれていたかを知ることができる点では得難い資料になっている。負け惜しみでなく。
現在読まれている本のどれだけが10年、20年、30年の歴史に耐えられるだろうか。