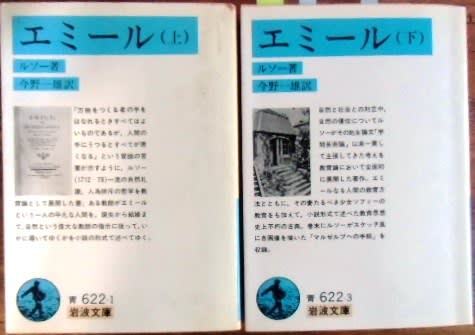定年退職後、これまでに読んだ本の感想文をいくつか。
手あたり次第に読んでおり、時系列では内容的に一貫性がないので、内容別に整理した。バルザック『結婚の生理学』など、すでに書き込んだ本は除く(一部重複あり)。
<「教育」とは何か>
親の教育権についての報告という宿題を背負ったまま定年を迎えてしまったので、まずはこれに片をつけなければならない。ということで、「教育」とは何か、を考える本を数冊読んでみた。
★ Ph. アリエス『「教育」の誕生』(新評論)
★ 堀尾輝久『現代教育の思想と構造』(岩波書店)
両方とも、部分的に読んでいたのだが、時間ができたので通読した。とくに堀尾氏のものは昨年末に東京女子大学の丸山真男資料室(?)で開催された彼の講演を聞きに行ったこともあったので、真っ先に読んだ。
定年前にやり残した仕事の一つが、子どもを教育する親の権利の問題であり、しかも一番勉強させてもらった研究会で、親が信仰する(特異な)宗教に基づいた教育を子どもに課することの可否が争われたイギリスの裁判例を報告する宿題を果たさないままでいる。
親の教育権を論じた先行研究にはあまり納得していないのだが、さりとて自信をもって自説を展開できるわけでもない。
★ ワロン/竹内良知訳「一般教養と職業指導」『ワロン・ピアジェ教育論』(明治図書)
ぼくは新制大学は、戦前の教育制度でいえば「実業学校」であると思っており、そのような性格を持つ新制大学で「職業教育」はどうあるべきかを考えてきたが、そのような動機からたまたま手元にあったこの本(のこの論文)を読んでみた。

★ 新渡戸稲造『自警録』(講談社学術文庫、1982年、原著は大正5年(1916年)刊)
新渡戸が「実業の日本」に連載した実業人向けの人生訓。彼は、一高校長として訓示するときと、「実業の日本」(彼は同社の編集顧問だった)に執筆するときとでは論調も用語も使い分けていたという。
実業学校としての新制大学において、講義をする際にどのようにテーマを設定し、どのような話し方で語りかければよいかを考える際に一番参考になったのは、新渡戸が「デモクラシー」を「平民道」として論じたことだった。ただし、このことを論じたエッセイは『自警録』ではなく、教文館の全集のどれかに収録されていた。
※新渡戸稲造全集5巻(1970年、教文館)に収録された「随想録」(明治40年、丁未出版社刊)のなかに「平民道」が収録されているが、この随想は「デモクラシー」の訳語として「平民道」を当てるという内容ではなかった。ネットで調べると、青空文庫に「平民道」という題名のエッセイ集が収録されているようだ。
「道」とは、政治学者がいう(といっても阿部斉さんが『政治』(UP選書)の中で書いていたのを読んだだけだが)民主主義における “ virtue ” (徳)というやつだろう。スペルを確認するためにウィズダム英和辞典(三省堂)を引いてみたら、“ virtue ” の語源は「男らしさ」であり、語義の中には「(女性の)貞節、貞操」というのもあった。どのように転義すると、こんなことになるのか。辞書を読むと面白い発見がある。
★ 刈谷剛彦・吉見俊哉『大学はもう死んでいる?』(集英社新書)
そういえばこんな本も読んだ。「大学はもう死んでいる?」というより「東大はもう死んでいる?」という書名のほうが内容にふさわしいだろう。近代化のためのテクノクラート養成を目的に作られたキャッチアップ型教育機関である(とぼくには思われる)東大が21世紀にはどうしたらよいかを論じているが、道は険しそうである。
普通の大学の職業教育を考える上ではあまり参考にならなかった。
★ ポール・ウィリス/熊沢誠・山田潤訳『ハマータウンの野郎ども』(ちくま学芸文庫、1996年)
原題は “ Learning to Labor ” であり、「ハマータウンの野郎ども」はあまりにひどくはないか。書名からは何の本か分からない。邦語訳の副題「学校への反抗、労働への順応」の方がよい(ただしこの翻訳者の訳業はすばらしい)。
階級社会であるイギリスの「中等学校」(「セカンダリー・モダン・スクール」とルビが振ってある)が下層労働者階級の子弟(「野郎ども」“ lads ”)の教育に失敗した1960~70年代の状況を(当事者へのインタビューを中心とした)参与観察で記述した部分と考察からなる。
当時のイギリスの中等教育は、上流階級の子が「グラマー・スクール」、中産階級の子が「テクニカル・スクール」、そして労働階級の子が「セカンダリー・スクール」と歴然と分断されており、階級間の移動は極めて例外的だったようだ。「階級」が目に見えないわが国の「実業学校としての新制大学」における職業教育の在り方については、残念ながらあまり参考にはならなかった。
イギリスの中等学校で行われようとした職業教育が「野郎ども」には効果がなかったのに対して、「野郎ども」は(やがて自分たちもその一員になる)下層労働階級に属する親から職業に必要な多くのこと(商品のちょろまかし方などまで含めて)を学んでいるというのは(こういうのも「文化資本の相続」なのだろうか)、親の教育と学校の教育の拮抗という面では興味ある事例を提供してくれる。
★ コンドルセ/渡邊誠訳『革命議会における教育計画』(岩波文庫、昭和24年)

最終ページに1990年3月22日、石神井公園駅側きさらぎ文庫で購入、300円と書き込みがあった。こんな古本屋が石神井公園駅近くにあったとはまったく記憶にない。駅南口の正面に新刊本の書店はあったが。
著者の教育制度論でいえば、今日の日本の「大学」はアンスティチュ( institut ) だろう。それは小学校・中学校の初等教育の次に位置し、アンスティチュ(仏和辞典には「学院」という訳語が載っている)の後には高等教育機関としてリセ( lycee )と学術院(早稲田みたい?)が続く。リセは今日では「高校」に相当するが、コンドルセのリセは今日の「大学」のようである。
コンドルセによれば、わが国の現在の「大学」に相当する「アンスティチュ」では、「人として、市民として、将来如何なる職業に就くにせよ、知っていれば役に立つようなもののみでなく、これら職業の大きな各分野、例えば農業・機械技術・軍事のごとき職業に役だつことのできるすべてのものを教授し、しかも、さらに普通の開業医・助産婦・獣医にとって必要な医学上の知識をも授ける。」とされる(29頁)。
最後の開業医云々はともかく、現在の大学に求められているのは、まさに、このアンスティチュの教育であると思う。
★ ジャン・ジャック・ルソー/今野一雄訳『エミール』(岩波文庫、1962年、1964年)
全3巻のうち、上巻と下巻だけ読んだ。上巻は以前に読んだ形跡があったが、下巻は初めて読んだ。中巻の部分は、堀尾輝久ほか『ルソー「エミール」入門』(有斐閣新書)の要約で済ませた。実は『入門』の要約の方がルソーの言いたかったことが多く理解できた。
堀尾氏の本とのつながりもあるが、実際はバルザック『結婚の生理学』を読んだのをきっかけに読もうと思ったのである。ああいう18、19世紀の饒舌な長々しい文章を読むのがあまり苦痛でなくなったのである。やはり時間があり余っているからだろう。
『エミール』は教育論というより、小説として読む本だろう。バルザックの『結婚の生理学』が家族論(貞節論)なのか小説なのか、ぼくには分からないが、『エミール』は『結婚の生理学』よりは小説的である。
下巻で、エミールがソフィーと出会い、恋愛し、結婚し、そして最後にエミールが父となることを先生に報告に行き、生まれてくる子どもは自分たちで教育すると宣言するのだが、親から引き離され家庭教師による教育を受けたエミールが、自分の子は自らの手で育てると宣言することが「自然教育」の結末というのは反語的である。
一種の「捨て子(の再生)物語」として読んだ。
下巻の最初の数十ページには、ルソーの女性論が書いてあるが、かなり固定的な性別役割分担論で貫かれている。最近のジェンダー論者はルソーをどう読むのだろうか。
バルザックとのつながりで言えば、姦通に関して、「世にも恐ろしい状態があるというなら、自分の妻に信頼をもたず、・・・わが子をだきしめながらも、他人の子を、自分の不名誉の根拠となるものを、自分の財産をうばいとる者を、だきしめているのではないかと疑惑を感じている不幸な父親の状態がそれだ」などという記述に出会った(下巻13頁)。
フランスだからと言って、 “ 家族のスキャンダル ” のように陽気に笑って済ませる問題ではないようだ。
2020年6月10日 記