こんばんわ。
大相撲春場所千秋楽。誰が、手負いの稀勢の里が本割で照の富士に追いつき、優勝決定戦にまで持ち込み、それにも勝ち、優勝すると思っていただろうか。(実はぼくは14日目の記事で十分可能性はあると看破していた 。でもネ、本音をいうと、まず駄目だろうと思っていた。ただ、その日の照の、大関復帰を果たすために真剣に立ち向かってきた琴将に、ひらりと変わって勝ったことで、すもうの神さまの逆鱗にふれ、バチが当たるのでは、という神頼みはあった)。
。でもネ、本音をいうと、まず駄目だろうと思っていた。ただ、その日の照の、大関復帰を果たすために真剣に立ち向かってきた琴将に、ひらりと変わって勝ったことで、すもうの神さまの逆鱗にふれ、バチが当たるのでは、という神頼みはあった)。
まさに、その通りになって、全く、稀勢の優勝のゆの字も言っていなかった、解説の北の富士さんもびっくりぎょうてん。こんなこともあるんだねえ、と。そして、ぼくは、同じ状況の千秋楽で、武蔵丸を破り、優勝した鬼の形相の貴乃花を思い出していた。また、なんと、新横綱優勝は貴乃花以来22年振りという。そういえば、今場所の稀勢の土俵上での表情は、現役時代の貴乃花のそれとそっくりで、まるで貴乃花が乗りうつったようだと感じていた。
とにかく、奇跡の逆転優勝!うれしくてうれしくて、晩酌もいつもの倍になってしまった 。居眠りする前にこれを書き終えてしまおうと。歴史的な、稀勢の里伝説になるに違いない、今日の一番を記録しておきたい。
。居眠りする前にこれを書き終えてしまおうと。歴史的な、稀勢の里伝説になるに違いない、今日の一番を記録しておきたい。
本割
いよいよ世紀の対決。場内、大歓声。
稀勢、少し、左に動き、有利な態勢を狙うも、押し込まれ、あわやというところだったが、突き落としで破る。場内、割れんばかりの大歓声。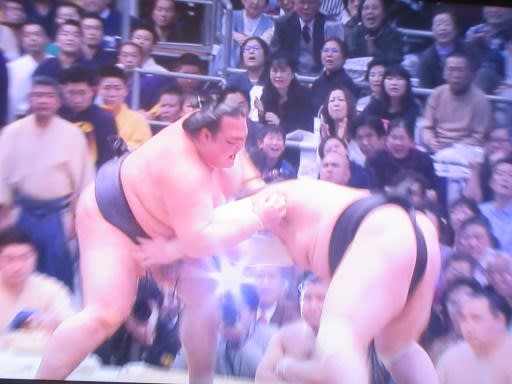

まさかの勝利で、北の富士さんもどぎまぎ。でも決定戦では無理でしょう、と心の内。ここまで、やれば、もう負けてもいい、怪我を拡げないようにと。そして、優勝決定戦へ。
優勝決定戦
さあ、立ち合いだ。
左手が万全ではない稀勢、中に入られ追い込まれも、土俵際で起死回生の小手投げ。勝った!まさかの逆転勝利。ぼくは、ビデオのとき、いつも写真を撮るが、このときNHKの速報が入り、その字幕入りで、お見苦しいでしょうが、その世紀の一戦の経緯をご覧ください。


稀勢の里、優勝!新横綱優勝は、貴乃花22年振りの快挙!

表彰式 君が代斉唱のとき思わず涙。日本中がもらい泣き。よくやった稀勢の里!
涙の優勝賜杯。



では、おやすみなさい。
いい夢を!
(海老蔵は歌舞伎界一の角界通。成田山新勝寺では稀勢の里と一緒に豆まきをする)
(2016年2月3日、成田山新勝寺にて)




































