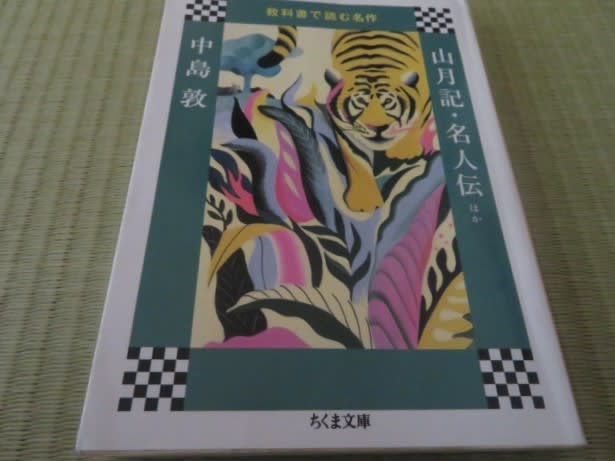おはようございます。
今日は、ひと月も前に見た神奈川近代文学館で開催されている中島敦展のこと。ブログ記事にするのが遅れているが、ぼくの中ではまだ展覧会は続いている。そのとき売店で買った文庫本の二冊目の”わが西遊記”を読んでいる途中だからである。ぼくの読書はほとんど都内に遊びに行く電車の中だけなので進行は遅い。
実は、展覧会に行くまでは、中島敦のことをよく知らなかった。原節子も通った横浜の女学校の先生をして、途中でやめて作家になったという程度。彼の本も読んだことがない。
本展で、彼の作品が、高等学校教科書の収録文学作品の5位に入っていることを初めて知った。1位が漱石のこころで2位が芥川の羅生門。そして、鴎外の舞姫、志賀の城崎にて、とつづき、中島敦の山月記がベスト5入りしているのだ。錚々たる作家たちが並んでいる。これは、是非、読まねばと思った。
山月記を読み始めて、びっくり。教科書に選ばれるほどだから、ほれぼれするような文章に加え、物語がしんみりと面白く、久しぶりに感動して読んでしまった。唐の怪奇物語”宣室志”の脚色である”人虎伝”を下敷きに書かれたもので、優秀な官吏だったが、思うところあり、帰郷し、詩作にふける李徴の物語。詩人としては認められず、苦しい生活の日々。ある日、突然、発狂し、闇に消える。それから一年後、友人の官吏が山中で、虎になっている李徴と出会う。一日に数時間だけ人間の心に帰る。そこで友人に語り掛ける告白がしみじみと味わい深い。
この短編集には、ほかに7編収められているが、”李陵”もとても面白かった。前漢時代の実在の軍人の歴史小説で司馬遷も登場する。そして、今、二冊目の”光と風と夢/わが西遊記”に入っている。これもまた、面白くて、にわかファンから本物のファンになりつつある。
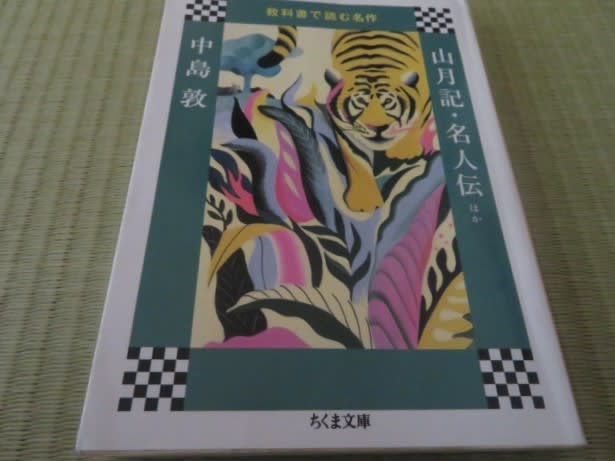
中島敦(1909-1942)が短い生涯のなかで遺した作品は20数編、著書はわずか2冊を数えるのみです。南洋庁の役人としてパラオ赴任中の1942年(昭和17)2月に文壇デビューを果たしたものの、作家生活は1年に満たず、その年の12月には志半ばにして亡くなりました。しかし、「山月記」「光と風と夢」「李陵・司馬遷」など中島が紡ぎ出した物語は、若い世代を含め今も多くの人々に愛され、読み継がれています。
中島敦の生誕110年を機に行う本展では、中島の短くかつ起伏に富んだ人生を「旅」と捉え、33年の生涯を振り返ります。そして、その珠玉の作品が今日見せる様々な広がりを紹介します(以上、公式サイトより)。
展覧会場には若い女性が多かったが、彼女らは文豪女子(笑)であることが後でわかった。なんと、”文豪女子”出現のきっかけとなった朝霧カフカ原作、春河35画のアクション漫画”文豪ストレイドッグス”に中島敦が主人公で出ているのだそうだ。ほかにも太宰、中也、芥川、乱歩らが出てきて、それぞれの文豪にちなむ作品の名を冠した異能力を用いて戦う。中島は、山月記のように無意識に虎に変身することができる異能力をもつとのこと。 これも一度、読んでみたい。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!