
今までの のしてんてん作品
新春の邂逅展まで、いよいよあと2か月となりました。
のしてんてん龍は、まだ道半ばですが、少しずつ進んでいる実感はあります。
邂逅展に向けて(一歩進みました)
で闇と龍が空間をつくるという理解を得ましたが、登らねばならないステップは常にその上にあります。
今私がひっかかっている問題は、今までの のしてんてん絵画から跳び出して龍を描きだしたことそれ自体にあります。
今までの絵は、表題の作品のように「私の心象風景」であって、どんなものを描いても比較するものは何もないのですから、オンリーワンであり得ました。
ところが龍はそういう訳にはいかないということが段々に分かってきたのです。
ご存じのとおり龍は想像上の生き物で形に決まったものはありませんから、好きな姿を思いうかべればいいようなものですが、それが案外難しいということが今更ながら分かってきたといえばいいでしょうか。
想像上の生き物でありながら、人間の頭脳に生まれた歴史は長く、そのイメージはもはやゆるぎない実存と言っていいでしょう。
そしてそれは、いかに人は(自分は)既成概念のかたまりだったのかという自虐的な驚きとつながります。
進むにつれて、今までのように心に思い浮かんだ龍を描けばいいと思っていた安易さが見えるようになりました。
つまり、恥ずかしい話ですが、
心のままに描いた龍は、のしてんてん龍ではないことに気付かされたのです。
それはかつてどこかで見た誰かの描いた龍の記憶の残片でしかないということの発見でした。
これは今までに体験したことのない創作上の大きな壁だったのです。
眼、爪、鱗、・・・・
ぼーっとして描けば、それはかつてどこかで見た龍の模倣となってしまう。恐ろしい世界だとあらためて気づかされたわけですね。
逆に言えば、すでに得た龍の姿で満足して深く考えないうわべだけの龍を描いているということです。
描く以上は、この世に二つとない龍でなければ意味はないわけですね。
既成概念を捨て、真っ白な自分に還って龍を描く。
方法はそれしかないのですが、
既成概念は、手袋をてれこに使うことに気付くだけで5年もかかる思い込みの心だと理解して、これではいけないと心の芯にようやく火がともったように思います。
まずは己の欠点を知ったことを進歩と考えて、次なる作品の習作を描いてみました。
真実をつかまえようと身構える伏し龍。
規則正しい魚のような鱗を捨てようと描いたものです。
(サムホール)
少し自由になったと喜んだ次の日、
オイオイ、待てよ、このウロコ、この姿勢、狩野信政の天井画じゃないの?!

明らかに、信政の模倣ですよね。
あの世で笑う信政の顔が見えるようです。(どんな顔か知りませんが、面白いもので頭脳は勝手にそんな顔も創り出すのです。)
のしてんてん龍の道は厳しい・・・・というお話でした。。


新年の正月初詣、今年は奈良にいらっしゃいませんか。
ついでに邂逅展というスケジュールをお勧めします。
一度に11人の個展を楽しむことが出来ま^す^。^
邂逅展に向けて(龍の創造2)

























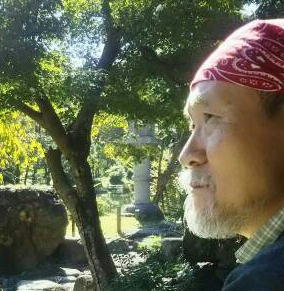

それは菩提に続く道なのですね。
けれど、気付く気付かないにかかわらず、その思考は簡単に能動態にとって代わる。
それだけ体にしみこんだ思考方法なのだということを実感しています。
修行とは、己の中にあるこの思考方法に気付き続けることではないでしょうか。
そうすることで発心を促し続ける。
ありがとうございます。
修行の中においても発心があります。
内発に従うことが中動態。
そして一番重要なことは、その先で出会う喜びだけが本物の心の喜び。
すなわち菩提ということですね。
真の内発には真似も何もない。たとえ同じ絵を描いても内発から出たものは己。
逆に真似をしないという意識で描いたものは、いかに独創的でも己とは遠い。
理屈はいらない。ただ発心に従えばいい。
そういうことなのですね。
一枚、眼から鱗が取れた気がいたします。
ご教示に心より感謝申し上げます。
具体を越えねばならないのですね。
内発としてではなく、外から与えられたものです。
発心は中動態です。
喜びに変わる一つ前です。
そして他方、そうなることを願うこと。
作家はこの二心で揺れ動きます。
願うことはいわば能動態であり、思いが強くなればなるだけ「作るもの」としての比重が大きくなる。
しかし一方、そうならざるを得ないことは、中動態の土壌ですよね。
そう考えると、「発心」とは中動態への入り口ということでしょうか。
生まれてくるものを無条件に受け入れ、心をもって判断する。
心が喜ぶか、喜ばないか。
それだけです。
塞き止めようのない成り行く勢いの中で
作られたものとして、作っていく。
成り行く勢いの中で、そうならざるを得ないこととしての「発心」ではないでしょうか。
それが実願するかどうかは分かりませんが
発心にはその志向性が含まれていますね。
いわば指向性の旅ということでしょうか。
それは結果、己を最大限に引き出せということだったのですね。
作られたものは作者を離れて公のものになる。Unknownさんのおっしゃるように、創造は人間の財産として積み上げられて行きますね。それが人の歴史というものかもしれません。
すると作る側に立っているものは、樹の生長点のようなもので、常にないところに身をひろげて行かねばならない。そこに具体の理念の素晴らしさがあると私などは思っております。
成長点が、すでにあるものの真似をするだけでは樹は細いままで成長しないですよね。
私が密かに思っているのは、真似を己の養分として新しい芽を育てるということ。
そしてそれが、Unknownさんのいわれてることだと理解しました。
龍を描きだした以上、最大限私の中で生まれる龍を見てみたい。そんな人生の楽しみ方、ワクワク感です^ね^
しかし、作られたものなくして作るものというものがあるのではなく、作るものは、また作られたものとして作るものを作って行く。』