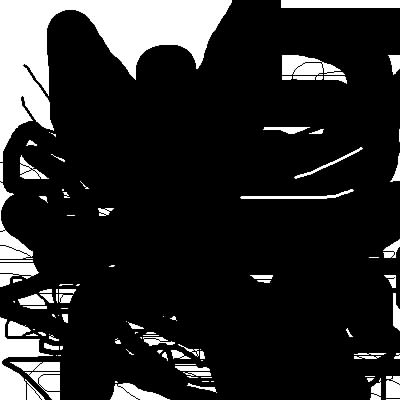
地下道
狭い闇の中を、小さなランプの灯りに照らされた四人の人影が、黙々と歩いていた。先頭には剣を腰に下げた男、その後ろにたくましい体格の大男、次に華奢な体つきの女と男が続いていた。
「大丈夫か。」
二番手を歩く男、バックルパーが先頭に太い声をかけた。
「間違いない。左右は違っても、この国の地下道も我らの国のものと全く同じだ。ここを行けば、必ず王宮の地下室に通じている。私にはそれが分かる。」
宰相ゲッペルが答えた。作戦が功を奏して、噴水の赤い玉を手に入れた。しかし将軍ゲッペルも抜け目のない策士だった。赤い玉を奪われるとすぐに兵を動かして王城の守りを固めたのだ。
『城に入る入り口はすべて封鎖された。王城に至る道を通ってはならぬ。 』
首尾よく赤い玉を手に入れて気をよくしていたそれぞれの心の中にそんな言葉が生まれて来た。パルガからのメッセージだった。
「しかしそれでは、王城には入れないぞ。赤い玉を取った意味がない。どうするんだ。」バックルパーが声を出して言った。
『地下道・・』皆の頭にひとりでにそんな考えが生まれて来た。
「そうだわ、地下道を通って行けばいいのよ。」エグマが言った。
「そうだ、あの地下室のトンネル、一つは王立図書館とつながっていると言ってましたね。生の国で、俺達は王立図書館の地下室に入ったことがあります。そこから不気味な声も聞いています。だから、この国でも、図書館の地下に行けば、きっとその入り口があると思うんです。」
「確かに、私も生の国では何度か使ったことはある。その入り口は分かる。しかしそこに行くには鍵が必要だ。」
「ユング、お前なら分かるだろう。元図書館の職員だ。一緒に来てくれ。」バックルパーが言った。
「いや、俺は一緒に行けない。鍵の置き場所を書く。これを持って行け。鍵はそこにある。」ユングは紙に簡単な図を書いて、鍵の置き場所を示した。
「お前はどうするんだ。」
「俺はこの国の人間だ。ようやくこの国に革命の好機が訪れたのだ。この市民の力を正しい道に導かねばならぬ。」
「なるほど、よく分かった。」バックルパーはまじまじとユングを見た。
「幸運を祈る。」ユングもバックルパーの目を真っすぐに見た。
「お前もな」
二人はしっかりと抱き合った。
「二度と会えないかもしれない。ユング。」
「何を言っているバックルパー。我々はすでに別れを済ませているんだぞ。バケツ一杯ほどの涙を流してくれた。今その礼を言えるだけ幸せだ。」
「ユング。」
「バックルパー。」
「いい人生だったよ。」
「俺もだ、ありがとうユング。」
「さあ、時間がない。俺は行く。見ていてくれ、必ずこの国の虐げられた民を解放して見せる。お前も自分の成すべきことをやれ。」
「ユング、最後だ。」そう言ってバックルパーは手を差し出した。
ユングとバックルパーは別れの握手を交わした。そしてそのままユングは身を翻して走り去り、迷走を続けて混乱している民衆の群れの中に消えた。
「さあ、行きましょう。」
ダルカンが皆を促し、バックルパー達は王立図書館の方に進んだ。図書館の入り口はすでに民衆によって打ち壊されていた。図書館の閲覧室も司書室も書類が散乱して、本棚は折り重なって倒れていた。誰かが火をつけたのか、折り重なった書架の下からチロチロ炎が赤い舌を出していた。
「鍵の場所は分かるか」ゲッペルがバックルパーに訊いた。
「大丈夫だ。ここまで民衆の手が及んでいない。」バックルパーはユングの書いた図を見ながら戸棚を捜し当て、中から鍵を取り出した。
「行くぞ!」バックルパーは皆に号令をかけた。
こうして四人は地下道に入り込んだのだった。その地下道は、ゲッペルが何度か通った事があるという、その記憶通りに続いていた。四人はゲッペルを先頭に王宮の地下室へと急いでいた。長いトンネルだった。
「もう少しゆっくり歩いてくれない。」エグマが息を切らせて訴えた。
後ろを見るとエグマが一人かなり遅れて続いていた。ダルカンが立ち止まりエグマを待った。
「大丈夫か。」
「ついて行くのが大変だわ。」
「少し休もう。」バックルパーとゲッペルも立ち止まってエグマの方を見た。
「疲れたわ、ごめんなさい。」エグマは肩で息をして、地下道に座り込んだ。
四人はしばらく無言で坑内にとどまった。そして再び立ち上がり先に進もうとした時だった。ゲッペルが意外な声を上げた。
「何だこれは。」
「どうしたんだ。」バックルパーがゲッペルを見た。
ゲッペルは先に立って進もうとした体勢のまま凍り付いたように見えた。
「何かあったのですか。」ダルカンもエグマも立ち上がった。
「見ろ、」
ゲッペルがランプをかざした先の方に、地下道の壁が照らし出された。その壁にはぽっかりともう一つの入り口が口を開けていたのだ。
「別れ道なの。」エグマが言った。
「こんなものはなかった。」ゲッペルが唸った。
「じゃあ、どっちの道か分からないのですか。」
「ねえ、ちょっと、これってどういうこと!」エグマが悲壮な声を上げた。
エグマは後ろを見ていた。四人が立っている地下道の後ろの方も別れ道になっていたのだ。
「私達、どの穴から来たの。」エグマが泣きそうに言った。
「確かに一本道だったぜ。急いで歩いていたから見落としたのか。誰か気づいたものはいないのか。ゲッペル、どうなんだ。」バックルパーが言った。
「おかしい。この地下道は一本道のはずなのだ。」
「するとまやかしか。悪魔の仕業か。」
バックルパーはそう言って前方に現れた二本の地下道を調べた。試しに片方の入り口から入って見た。トンネルはずっと続いていた。そして引き返そうと立ち止まり後ろを振り返ったバックルパーは驚きの声を上げた。目の前にまたもやトンネルが二つに枝分かれしていた。何だこれは、バックルパーは一瞬うろたえて何をすべきか分からなかった。歩いて来たときには確かに一本道だった。慎重に調べながら歩いたから間違いはなかった。それなのに、立ち止まって振り返ると、そこに別れ道が出来ていた。そんなばかな。一体どちらのトンネルから来たのか分からなかった。
「おーい!」バックルパーは二つのトンネルに向かって声を上げた。
「どうしたバックルパー、何か見つけたか。」右のトンネルからゲッペルの声がした。
「いや、そちらに帰ってから話そう。それより皆、決して離れるんじゃないぞ!勝手に動くな。」
そう言ってバックルパーは声のするトンネルの入り口を選んで元の場所に戻った。調べてみると、もう一方のトンネルも同じだった。自分の進む方向から目をそらすと、とたんにトンネルは枝分かれした。奇妙なトンネルの迷路に迷い込んだ四人が、トンネルのそんな性質を理解したのは長い時間迷ってさまよった揚げ句だった。
一生出られないのかもしれない。そう思うと、エグマは涙があふれて来た。四人は疲れ果てて地下道の地面に座り込んだ。四人の前には六つのトンネルの入り口が見えていた。トンネルの数は増えるばかりだった。
「もうだめだわ。」とうとうエグマは泣き出した。
「エグマ、泣いたって始まらないよ。」ダルカンも半分泣きながら言った。
「私達、こんな訳の分からない所で死んでしまうの。そんなの嫌よ。」
すでに四人は、完全に道を失っていた。どこから来たのかさえ分からないのだ。どこに行けばいいのか分かるはずもなかった。
「どこから来て、どこに行くのか。まるで人生のようだな。」バックルパーが冷ややかに笑った。
『ヒャッ、ヒャッ、ヒャッ、』将軍ゲッペルの勝ち誇ったような笑い声が宰相の頭の中で響いた。
「ちくしょう、はかられたか。」ゲッペルが思わず声を上げた。
「どうしたんだ、ゲッペル」バックルパーが訊いた。
「これは将軍の罠だったのだ。王城への道をふさいだのは我々をここにおびき寄せるためだったのだ。迂闊だった。」宰相は唇を噛んだ。
「何ですって!」ダルカンが叫んだ。
「ここから出られないなんていやだよ。」エグマはダルカンにしがみついた。
「ヒャッ、ヒャッ、ヒャッ、」今度は皆の耳に将軍の笑い声が届いた。
「愚か者め、今頃気付いても遅いわ。一生そこでさまよってのたれ死にするがいい。ヒャッ、ヒャッ、ヒャッ、」不気味な笑い声と共に将軍の声は消えた。
「おのれ、卑怯な。」バックルパーはうなった。
「出してよ、ここから出してちょうだい!」エグマは我を忘れて叫んだ。
「お願い、出してちょうだい!」
「エグマ!」ダルカンは声でエグマを押さえた。
「そんなことを言っても無駄だよ。」
「じゃあどうすればいいのよ。」エグマは絶望感で押しつぶされそうになっていた。
「とにかく黙るんだ。」ダルカンはエグマを抱きしめた。
ダルカンの胸でエグマは泣き始めた。
「静かに、」ゲッペルが全身を耳のようにして言った。
「どうした、」
「何か聞こえないか。」ゲッペルが耳をそばだてて神経を集中させた。
地下道の中が急に静まり返った。そのとき四人の耳に、かすかな旋律が聞こえて来た。それはあまりに小さく、かすかなものだったので、誰もが耳鳴りではないかと疑った。しかしその音は確かに四人のもとに届いているのだった。四人は息をこらしてその音の聞こえる方向を探った。心地よい旋律だった。
「まるで神様の音楽みたい。」
かすかな音が、確かに一つの地下道から聞こえていることを突き止めてエグマが言った。 「気持のいい音だな。」
「これも罠か。」ゲッペルが言った。
「罠なら、受けて立とうじゃないか。」バックルパーが言った。
「僕もそう思います。」ダルカンが言った。
「そうだな、取り合えず手掛かりは他にない。行くか。」ゲッペルが立ち上がった。
四人はいくつも口を開いている地下道の入り口から音楽の聞こえるトンネルを選んで足を踏み入れた。四人はその音楽に導かれるように進んだ。途中何度か別れ道が現れたが、その度にその心地よい旋律が道を示してくれた。
「俺達、このまま天国に行ってしまうのじゃないか。」ダルカンが言った。
「天国ならいいのだがな。」ゲッペルが返した。
「とにかく、気を緩めるな何が起こるか分からない。」バックルパーが口を挟んだ。 その音は次第に大きく聞こえるようになっていた。その旋律は人の声のようにも思われた。それが聖歌隊のコーラスのように深く心の底の方から揺り動かされるような歌声となり、やがてたくさんの人々の声が織り重なる重厚な合唱となっていった。
「この歌声は一体、何なのだろう。」
次第にはっきりと聞こえるその何人もの歌声、そのコーラスの音には一抹の危険も感じられなかった。黄泉の国の地下道から聞こえる、まるで天国のような旋律。その声に導かれて、四人は悪魔の迷路を幸福感に満たされたまま進んで行った。
出口が近いのだろうか、今やはきりと、そのコーラスの歌詞さえ分かるようになった。
たとえどんなに苦しくとも
たとえどんなに惨めな日々も
たとえどんなに暗い闇でも
たとえどんなに寒い夜でも
勇気を持ちなさい
勇気を持ちなさい
勇気を持ちなさい
もうすぐ日が昇る
たとえどんなにつらい時でも
希望を持ちなさい
希望を持ちなさい
希望を持ちなさい
もうすぐ朝がくる
エグマは胸の底から熱いものが込み上げてくるのを感じた。心がバラバラに分解されてその歌声の中に溶け込み、心地よく揺り動かされるような感覚を味わっていた。エグマの目から自然に涙が込み上げて来て、前を歩くバックルパーの姿が歪んで見えた。先程流した絶望の涙とは対照的な至福の涙だった。
「おお!これは!」
ゲッペルが思わず立ち止まった。
「何だこれは、」バックルパーも凍り付いたように動かなかった。
「何なのこれは、一体どうなってしまったのよ。」エグマが叫んだ。
最後にダルカンがその光景を見た。
四人はしばらく呆然と立ち尽くした。次の言葉を発する者はいなかった。
次を読む



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます