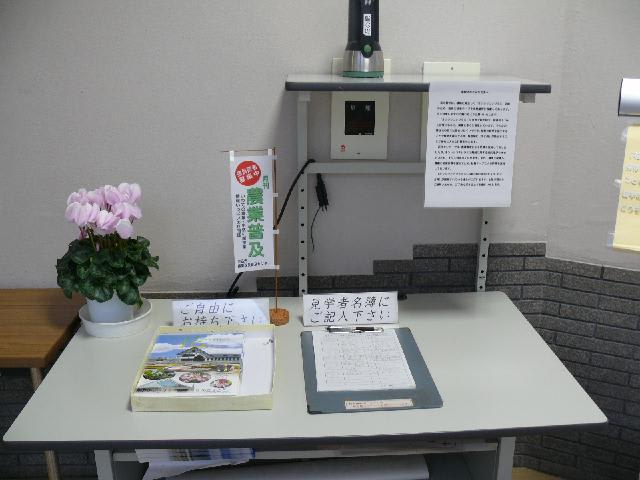2010年1月8日(金)、世界の椿館・碁石(大船渡市末崎町字大浜280-1)の大温室内の「早咲き椿」コーナーに植えられている”炉開き(ろびらき)”という名の椿が花を咲かせていました。入場するとき頂いたパンフレットには「早咲き椿:椿は通常冬から春にかけての開花ですが、秋から花を楽しめるものもあります。炉開き、舞、東方朔、西王母など。」と書かれています。
椿”炉開き(ろびらき)” ツバキ科 ツバキ(カメリア)属 Camellia rusticana ×Camellia sinensis cv.Robiraki
産地:新潟。花の特徴:淡桃~桃色の一重、平開咲き、茶芯、極小輪。花期:9~4月。葉形:長楕円、小形。樹形:叢生、密生、強い。来歴:ユキツバキとチャの自然雑種。栃尾市の民家より甲政治が採取、1980年に加藤英世の命名・発表。[以上、誠文堂新光社発行、日本ツバキ協会編「日本ツバキ・サザンカ名鑑」より]
http://www.hanahiroba.com/niwaki-tsubaki_robiraki.htm [炉開き(ロビラキ)花ひろばお買い物]
http://www.nagominoniwa.net/2006/060921.html [「和みの庭」のツバキたち:椿 炉開き(ロビラキ)]
http://yukasa.i-yoblog.com/e208259.html [フラワーセラピーの店遊華茶:椿「炉開き」]
http://kazuyoo.mo-blog.jp/gardening/2010/01/post.html [gardening:椿炉開きとシランの実]
http://konekonote.exblog.jp/10438724/ [子猫のかくれんぼ:椿:炉開き]
http://aquiya.skr.jp/zukan/Camellia_cvs.html [草木図譜:ツバキ属の交配種]