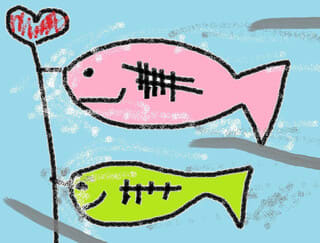
またの年の八月に、内裏へ入らせまたふに、夜もすがら殿上にて御遊びありけるに、この人のさぶらひけるも知らず、その夜は下に明かして、細殿の遣戸を押しあけて見出したれば、暁がたの月の、あるかなきかにをかしきを見るに、沓の声聞こえて、読経などする人もあり。読経の人は、この遣戸口に立ち止まりて、ものなど言ふに答へれば、ふと思ひ出でて、「時雨の夜こそ、片時忘れず恋しくはべれ」と言ふに、ことながらう答ふべきほどならねば、
何さまで思い出でけむなほざりの木の葉にかけし時雨ばかりを
とも言ひやらぬを、人々また来あえば、やがてすべり入りて、返ししたりしなども、後にぞ聞く。「『ありし時雨のやうならむに、いかで琵琶の音のおぼゆるかぎり弾きて聞かせむ』となむある」と聞くに、ゆかしくて、われもさるべきをりを待つに、さらになし』
「木の葉にかけし時雨ばかりを」という感情の放り出し方が好きである。この時雨に対し、琵琶の音で「おぼゆるかぎり」返そうというのが、えらく積極的に思えるが、そんな機会が全くない、というところが、この日記の劇である。源氏の君みたいなものとの邂逅はむろん現実にはありえないのだが、この作者、源氏ではなく、現実におけるすれ違いの多さというか運のなさをはじめから意識的なのかもしれない。
確かに、すれ違いというのは、我々の人生の基本形である。だから、我々はせめて主体的で自由でなければやってられない。すれ違いでしかも統制されているとか、冗談じゃない。
コロナに限らず、なんか困ると憲法をいじくりたがるという人たちがたくさんいるが、憲法を校則みたいに捉えているのではなかろうか。はなから自由に振る舞う勇気のない奴が校則いじくってみたところで何もかわらないどころか、むしろ、自由たれという命令が天から振ってこないことで、他人の自由は抑圧してもよいという馬鹿が威張るようになるだけだ。
こういう輩がいけないのは、我々が現在の快・安心だけを望んでいるわけではないということが分からない異常状態にあるからである。他人に謙譲表現ばかり繰り返すことは、みずからの快を優先しているということであって、どうせ自分に負荷かかかる状態は全力で人に回そうとするし、人によって態度を変える。かかる人間には、他人(ひいては自分)の状態に対する明らかな蔑視がある。原因は、たぶん過去や現在のうまくいかないシーンの抑圧である。自由というのは、そういうシーンの抑圧をやめることである。
娯楽は若い人間の特権だ。歳をとってくると、人生に意味をつけなければならなくなってくる。娯楽の余裕はない。そしてその意味は大して意味はないが、意味づけを要求する意味の礫だけは次々に襲いかかってくる。更級日記の作者を襲ったのもそういう事態かもしれない。――更級日記はしかし、確かに娯楽になっている。自由があると思うのである。
校則に対する反発のような気分が、案外憲法への反発にもなっているところが、我々の深刻なところである。自分のなかのさまざまな礫を無視するために、自分の状態を自分を抑圧する社会の軛に求めるのである。
自己嫌悪とは自分への一種の甘え方だ、最も逆説的な自己陶酔の形式だ。(小林秀雄「現代文学の不安」)
「一種の」「方」、「最も」「逆説的」、「形式」これをとっても意味が通じるような気がするが、これはすべて必要だとかんがえるべきなのである。それではじめて、自己に対する陶酔を回避できる。だからほんとは彼の文章は一部を切り取れない。文章全体、彼の著作全体がこういう言葉の雲で組織されており、それが全体でひとつのものである。柳田國男の「内言」じゃないが、一生かけてそれを作り上げようとしたところがあるわけである。普通の浪漫派はそうでなくてツイッターのbotに向いている箴言型である。自分の戦時中でもいまでもそういう浪漫派に威勢のいい左も右も真ん中も入ってしまう。箴言は憲法の様に我々を外部から縛る。小林や柳田は内側から縛ることを考えたにすぎない。昨日、「国民文学論」の議論を読んでいてそう思った。









