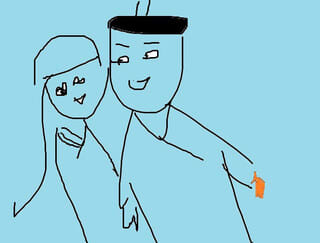
よろづにいみじくとも、色好まざらん男は、いとさうざうしく、玉の巵の当なき心地ぞすべき。露霜にしほたれて、所定めずまどひ歩き、親のいさめ、世のそしりをつつむに心の暇なく、あふさきるさに思ひ乱れ、さるは独り寝がちに、まどろむ夜なきこそをかしけれ。さりとて、ひたすらたはれたる方にはあらで、女にたやすからず思はれんこそ、あらまほしかるべきわざなれ。
こういう言い方自体が、なんとなくもてない男の言い訳っぽい感じである。確かに、むかしから「色好み」でないためにいまいちだなあ、という男がいたのだ。よくわからないが、色好み自体が権力と関係する生々しさを持つと同時に、ただでも「まどひ歩く」ことが多い世知辛さを裏返した様に輝かすものであった。それは、自らがっつくような恋であったら権力闘争と同じだが、「女にたやすからず思はれる」ような、向こう側からひそかにやってくる様な、自分とは関係ないような恋であったほうが、世界が輝いている感じがする。
こんな考えは曲解に近いかも知れないが、そのセンスはやはり、第二段の華美な権力を批判するところとおんなじだと思うのである。
そのうち、かれこれ二十分も経ちましたろうか。お俊は折り折り団扇で蚊を追っていましたが『オオひどい蚊だ』と急に起ち上がりまして、蚊帳の傍に来て、『あなたもう寝たの?』と聞きました。
『もう寝かけているところだ』と私はなぜか寝ぼけ声を使いました。
『ちょっと入らして頂戴な、蚊で堪らないから』と言いさま、やっと一人寝の蚊帳の中に入って来たのでございます。
――国木田独歩「女難」
こういう場面を思い出したが、たしかにやってくる女がよいとはいっても、この女なんか絶対に蚊をどこかにひっつけているに違いない。恋はいろんなものをくっつけてやってくるのは明らかで、源氏物語をよめば、ほとんど源氏にやってきたのは恋ではなかったような気がするのだ。









