
そういえば「富江」とか「着信アリ」とか観たことがない。「富江」のマンガは少し読んだことがある。楽しい作品であった。それにしても、楳図かずおによってホラーの定型を与えられている吾々は、普通デッサンの狂いかと思われる絵の部分にホラーを感じるようになっているのかもしれず、「富江」の場合も、最初の方が怖かった。
中学生の頃、ホラーにはまり込む人が多いという話を聞いたが、私はそうでもなかった。むしろ、男子は中学生になるとホラーが本当に怖くなって避けているような気がする。ジェットコースターが怖いのと同じである。
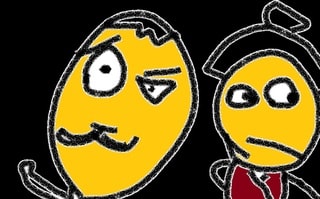
学者とかもの書きをやってる人にとっては、辛くて目を背けたくなるようなドラマであった、と思う。漱石が確かに、ちょっとあれなところがある人であったのは作品からも見えるが、その「あれ」の大部分は、文章を書く職業の人間が共有している「あれ」である。別に漱石の家が特別だったわけではなく、だいたいあんな感じなのであって、彼の世代にだだをこねるような感じで出てきた「新しい男」や「新しい女」たちによっても、あんまり事態は変わらなかった。今日、丁度「夢十夜」の「第四夜」を分析していたのだが、気が沈んでならなかった。作品は整然としているなあ……

タイのぷみぽんさんが死去したのだが、うちの首相が、周りが黒い服なのにひとりだけ青い服で心が一ミリもこもってない言葉を述べていたのが印象的であった。やはりわたくしは、昔日本が大凶作のときに米を送ってくれてわたくしの大学時代を救ってくれた国として、感謝しておるのである。同時に、王様がいても、国内が平和になるとは限らないサンプルとして興味深かった…。日本が敗戦していない場合、ああいう感じになっていたのかもしれないのだ。
とりあえず、当時タイ米がまずいとか言ってた輩はただちに喪に服せ
次のわちらろんこんさんは、三回も結婚しているそうである。うちの陛下に比べて「人間」宣言していると言ってよかろう。かわりにペットの犬が陸軍大将になっていると噂である。さすがにわたくしもこの噂には怯んだが、「ペットの犬が陸軍大将」は、どこの国でもそうであると気づいたので安心である。
2ちゃんねるで、「竹田が次期天皇になって華原朋美が航空幕僚長になる感じかww 」とか言っている人がいたが、嗤っている場合ではなく、もっとまともな場合の方が原爆を落とされたりするのである。竹田や華原は確かにかなり変わってると思うが、国会でめそめそ泣いたり領収書を自分で書いたりしてないだろうが…

いまいち気乗りしない仕事をやっつけていると、ブランショの『終わりなき対話』の全訳がでるという情報が来たので、少し元気になる。
『3月のライオン』はいつまでやるつもりなのか知らないが、最初の方の不幸の連発による破滅を「ありがとう」みたくやれないこのご時世、かかる物語を終わらせるには、
ノーベル文学賞は、村上春樹ではなくボブ・ディランだったらしい。やはり村上は今からでも遅くはない、安倍晋三とドナルド・トランプに激しく喧嘩を売るしかない。村上春樹は世界で人気だとかいうけど、あの内容を「日和りやがってさすが日本人」とか思っている人がどれだけいるかもうちょっと考えた方がいいのである。外国語に訳すとあの脱力した緊張感がどういう風になってしまうのか分からんから何ともいいがたいのであるが……。ちなみに、ボブ・ディランは、「風に吹かれて」しか知らなかった。ごめんなさい。なんか、今聞いてみるとソ連の人民がうたってるような抑鬱感がありますね……。アメリカの50年代はたぶん最悪だったんだなあ……
ていうかボブ・ディランは文学か?文学関係者は何様なんだ民衆音楽を馬鹿にすんのか!だいたいポリティカルすぎるだろが選考が!いつもそうだろ!AKBの歌詞とどこが違うんだ!違うに決まってるだろ!文学研究者は音楽研究に侵入してくるんじゃねえよ!音楽研究とか旧態依然としすぎなんだよいまはゲーム研究だよ美学だよ!クラシック音楽に対するコンプレックスお疲れ様です!ボブ・ディランはさっさと電話に出ろよ!夏目漱石と比べてどうよ!時代が違うんだよ!大衆小説と大衆音楽の区別を説明せよ!素人は音楽を語るなよ!
というかんじのいつもの争いがいま起こっていると思うが、とりあえず、文句を言う前に
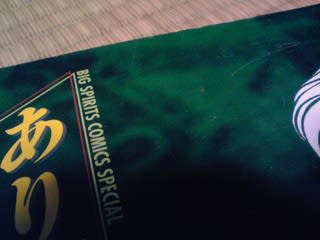
1968年がなんちゃらとか言う人は言うのであるが、いずれ我々の世代が「1995年革命説」などを唱え始めるであろうから、わたくしが先に言っておこうと思う。ウィンドウズ95の年だからIT革命の年だという人は多いが、この年が、阪神淡路大震災、地鉄サリンエヴァンゲリオン、イチローコギャル私の卒論700枚、山本直樹ありがとう、の年であることは見逃せない。大学院に行ったせいか、この年の前と後では私にとって世界が違う。ちょうど山本直樹氏が『ありがとう』を書いたのもこの頃で、物語の最後に、急速に家族の「解散」に向かう流れは、何ものかに背中を押されているような切迫感がある。勿論、それはある種の気休めであることも言うまでもなかった。家族や父権が、簡単に安楽死するとはかぎらない。むしろ「死」によって復活するのである。言うまでもなく、家族も危機だったが、それ以上に社会が壊れて身近な「壊れた人間」の暴力を防ぎきれなくなっているからである。

授業で考える予定なのだが、「バカ」の思想というのが戦後世界の肝ではなかろうか……。この問題設定自体にはイロニーはない。宮澤賢治の「でくのぼう」とかの側に行かない「バカ」の系譜というのがある。「バカボン」は仏教が入っているという説もあるのだが……。

さま山荘の事件を、山本直樹が描くことの意味をよく考えていなかったが、この事件の本当の悲惨さは、かわぐちかいじに描いていただいて初めて明らかになるように思えてならない。


















