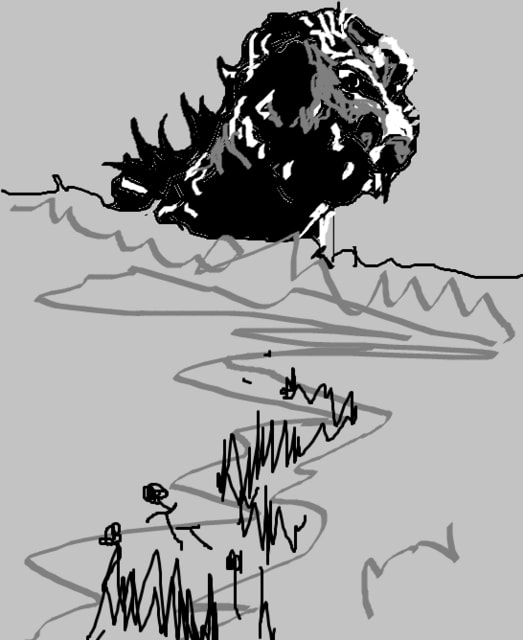阪神タイガース18年ぶりの優勝おめでとうございます。
逆に考えると、順位表をひっくりかえして中日優勝。18年というと、いまの大学一年生が生まれた時以来だからえらく昔であるが、わたしなんか最近の出来事のようにおぼえている。今回の阪神優勝で実は一番喜んでいるのは中日ファンで、最近では、阪神が優勝すると次の年は中日が優勝しているのである。
星野阪神優勝→落合中日優勝→岡田阪神優勝→落合中日優勝→落合中日日本一
この流れが来ている。そもそも今年だって、いまからでも遅くはない、今中とウッズが復帰すれば中日は優勝できるといへよう。
たぶん、阪神の選手は、もと李徴の可能性があるから、暗黒時代、劣等感を刺激してやるだけでイケる。
今頃知ったのだが、阪神の優勝は禁句で「あれ」と呼ばなければならなかったらしいのだ。いいだしっぺは監督らしいが、もともとは、「Vやねん」という優勝記念雑誌かなにかを優勝する前に発売してしまったときがあり、美事V逸したのでそれを意識したのであろう。その意味でも、阪神は優勝という言葉を吐いてしまった時点で、もう優勝はない。来年は中日優勝。
三島由紀夫「仮面の告白」には、NGワードを示す「あの事」という言い方が出てくるけれども、それを阪神優勝におきかえてみると、よりカオスな話になる。三島は、なぜこの「あれ」路線を放棄し、なんでも裸的になればよいと思ってしまったのであろうか。天皇制など、「あれ」みたいな話である。★秀実ではないが、天皇制を隠語に、である。
それにしても1950年以降、V9ごろまでの巨人の優勝確率というのはすごい。ほとんど巨人が優勝している。この調子じゃ、巨人優勝ていうのはほとんど心のインフラ整備みたいになってたのかもしれない。つまり、心の安定が巨人優勝という見える化を要求していたのである。三島が自衛隊に突撃したのも、この巨人優勝が続く時代であった。日本国民は、くたばれジャイアンツと三島の天皇陛下万歳が、単に見える形で同時に生起する世の中がやってきたことに気付くべきであった。