昨日まではベートーベンのチェロソナタを聴いていた。私は弦楽器の音色がすぐに耳に入るので、ピアノが後景に退いてしまう。今回はピアノに注目しながら聴いている。ビアノのソロの曲ならばピアノの音を愉しめるのだが、弦楽器とのソナタとなると、どうしても弦楽器ばかりを追ってしまう。そして弦楽器の響きが気に入ったかどうかでその演奏の良し悪しを判断してしまう。
もっとピアノに造詣が深ければ、そんなことはないかもしれないが、それは致し方ない。
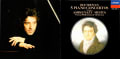


本日からはベートーベンのピアノ協奏曲を聴き始めた。
まずは第3番と第4番から。第3番は1803年頃に出来上がっている。
その前年に交響曲第2番、この年に交響曲第3番「エロイカ」が出来ている。
第4番のピアノ協奏曲はベートーベン35歳の年の1805~6年にかけて出来上がり、1806年には交響曲第4番とヴァイオリン協奏曲が出来上がった年である。
交響曲第4番は私はまだその良さがわからないでいるが、ヴァイオリン協奏曲とこの第4番のピアノ協奏曲はどこか似ているようで好みである。ピアノとオーケストラが対等に扱われるなど、ベートーベンにとっても、西洋の近代音楽史上でも画期となった曲とされる。
長大な第1楽章、美しい旋律の第2楽章、第2楽章から第3楽章への切れ目のない連続、際立って明るく軽快な第3楽章の躍動感、旋律性の強い主題など共通点もある。第2楽章では静かなピアノと重々しいオーケストラの対話掛け合いがピアノ主導で次第に静かに収束していく冒頭の緊張感がとても惹かれる。



















