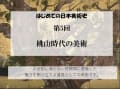5月6日に続いて、ドビュッシーに「挑戦」している。演奏はミシェル・ベロフのピアノ。曲は「版画」「映像第1集」「映像第2集」「忘れられた映像」「喜びの島」「マスク」が収められている。ドビュッシーの書法が確立されて以降の作品ということになる。
以前は、冒頭の数曲だけを聴いて、音の氾濫に圧倒されていつも「敗退」していた。数回このCDを聴こうとしたものの、最後まで聴いたことがない。ドビュッシーへの「苦手」意識が肥大。「食わず嫌い」が続いた。
今回は、これまでよりは落ち着いて最後までこれらの曲が収められているCDを聴くことが出来ている。前回、初期の作品を聴いてこれまでのイメージを少し刷新できた。そんなこともあり、今回は音符の氾濫の中から、メロディーを追うイメージで音の流れを探るように聴いている。しかしこれはこれでなかなかエネルギーのいる聴き方である。
ドビュッシーの作品というのは、私には聞き流しながら気楽に聴くということを拒否される。
細かく散りばめられた音符のどれもが等価に聴こえて、緊張を強いられる。そしてどの音符も強弱だけの差で、急・緩の差が極く小さいように聴こえる。
その中でも「忘れられた映像」は初期の作品、ドビュッシーの書法が確立される直前の曲であるらしく、メロディーを聴くように音の流れを追うことのできる場面がところどころに顔を出す。
やはりまだまだドビュッシーの曲を理解できない私である。