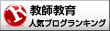×
子ども減っても不登校は過去最多「教室内ストレス」に親ができること
10月28日 14:39

少子化の中で不登校になる割合はどんどん高くなっている(※写真はイメージ)
(AERA dot.)
文部科学省が「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題」(2017年度速報値)を発表し、不登校の子どもは過去最多を更新した。自身も不登校経験者で、多くの当事者を取材してきた不登校新聞の編集長・石井志昂さんが考えるその理由とは。
* * *
文科省の発表によると、昨年度の不登校の子どもの数は5年連続で増加し、16年ぶりに過去最多を更新しました。
不登校の子どもの数は14万4031人(前年度比1万348人増)。小学生の不登校は3万5032人(同4584人増)、中学校は10万8999人(同5764人増)。小学生の不登校は前年度比15%アップと近年でも上り幅が大きなほうとなっています。
もう少し踏み込んで言うと、少子化の中で不登校になる割合はどんどん高くなっているということです。
2001年度の全児童生徒数は1128万8831人でした。かたや2017年度は982万851人と、146万人以上減少し、もっとも少なくなっています。つまり、統計史上、子どもの数が過去最低となるなかで、不登校は過去最多を更新したのです。
なぜ不登校は増えているのか。増加の要因について文科省はこう話しています。
「複合的な要因が絡み合っているので、原因を特定することは難しい」。
私も同意見です。しかし、ここ数年の傾向のなかで、不登校増の新しい要因として考えられる背景を何点か提示したいと思います。
■認知度の高まりと不登校の増加
千葉県習志野市にあるフリースクール「ネモ」理事長の前北海さんは「若い世代の親は『死ぬぐらいなら休んで』という感覚の親も多い。学校もフリースクールとの連携を求めるようになってきた」と、近年の変化について感じていると言います
新しい要因のひとつ目は「不登校に対する認知度の高まり」ではないかと思っています。
北海道札幌市にあるフリースクール「札幌自由が丘学園」のスタッフである新藤理さんも「不登校に対する認識や関心の高まりは肌で感じている」と言います。
背景には「9月1日の子どもの自殺」や「教育機会確保法の成立」をもとに、学校を休むことの重要性や、フリースクールなどの学校外の居場所に対する情報など、メディアを通じて報道される機会も増えてきました。
フリースクールで働く二人の声は、不登校が増加する原因のなかでも、ポジティブな声だと思います。
■“教室内ストレス”が高まる影響とは?
二つ目に考えられる新しい要因は「教室内ストレス」の高まっていることです。こちらはネガティブな要因です。
小・中学校の場合、年間を通じ、クラスメートは固定です。いじめの対象がころころ変わるような教室であった場合、ストレスフルな状態で1年間すごすことになるわけです。
今回の調査結果では「いじめの認知件数」も過去最多を更新しました。全国の学校が認知したいじめの数は、41万4378 件(前年度比9万1235件増)でした。4分の3の学校ではいじめが認知されました。
いじめの増加は、軽微な事案(冷やかし、からかいなど)もいじめとして報告するよう文科省が通達したことも影響したと思いますが、依然としていじめは教室内ストレスのひとつになっていると言えます。
ストレスという点においては、「ブラック校則」もその一端に挙げられます。「下着の色をチェックされる」「頭髪の色は黒を強制される」など、近年社会問題にもなっていますし、クラスの環境がいじめの頻度と関係するとする論文(鈴木智之「学校における暴力の循環と『いじめ』〜大学生を対象にした回想形式の調査結果を起点として」)もあります。
このように「いじめ」「ブラック校則」などの教室内ストレスが高まりは、不登校増の新しい背景だと考えられます。
■不登校の増加は「子どもが変わった」から?
一方、不登校増加の新しい背景とは言えないこととして挙げたいのは「子どもの変化」です。
たとえば、私は1982年生まれ。同世代には、「西鉄バスジャック事件」(2000年)や「秋葉原連続通り魔事件」(2008年)など事件を起こした加害者と同世代であり、「キレる世代」と呼ばれたこともあります。
今回の調査でも、暴力行為に及ぶ中高生が前年より減るなか、小学校では2万3440 人と、前年度より3590人増えていました。報道によれば、教育委員会のなかには「ガマンできない子どもが増えたからではないか」と分析しているところもあるそうです。
では、子どもは変わったのでしょうか。ある公立の小学校教員によれば「子どもがこの数年で悪くなったと感じたことはない」と語っています。
また発達心理学者・浜田寿美男さんも子どもの変化について次のように述べています。
『たかだか50年で、子どもが生物学的変化を遂げるなんてことはあり得ません。変わったのは子どもを取りまく社会状況であり、それが子どもの抱える生きづらさとも関係しているのだと思います』(『不登校新聞』380号 (2014.2.15号) 講演録)
■保護者が知っておきたいこと
「最近の子どもは変わった」とは思いませんが、「教室内ストレス」や「認知度の高まり」など子どもを取り巻く環境は変わりつつあると感じています。
では、もしもわが子が学校を行きしぶったり、不登校になったりした場合はどうしたらいいのでしょうか。
親の方には大前提として知っていただきたいことがあります。
「不登校は親に防げるものではない」ということです。先ほど述べたように、不登校の背景として「親の育て方が悪くて不登校になった」ということはありません。また本人の「怠け」や「弱さ」ゆえに不登校になるわけでもありません。
教室のなかには常にいじめが飛び交っています。「いじめに遭わない子育て」も存在しません。不登校やいじめは「子どもの世界」で起きていることであり、先生や親など大人が容易に介入できるものではないからです。
しかし親は何もできないわけではありません。親は「子どもを守る」ことができます。
ところが、実際に子どもが不登校になると、親や先生が子どもを追い詰めてしまうケースのほうが多いのです。
子どもはいじめを受けていても「学校へ行きたくない」とは言いづらいものです。自分がなぜ行きたくないのか、それを言葉で説明するのも難しかったりします。はっきりと「行きたくない」とは言わず、その理由も語らないとき、周囲は「甘やかしてはいけない」と登校を催促し、子どもを追い詰めてしまいます。
親が不登校やいじめを防ぐことはできませんが、子どもが学校で苦しんでいるとき、親が子どもの味方になってその命を守ることができます。親が「子どもの命を守るんだ」と舵を切れば、自ずと具体的な道筋も見えてくる。子どもが不登校になった親の多くが、そう考えて動いているのです。(文/石井志昂)
学校に無理に子供を登校させても、問題は解決しません。
又陰湿な虐めを受けます。
虐められる方が、悪いと言っても虐められる子供が、また虐められる複雑な虐めの実態です。
不登校が、悪いとは、言えません。
親御さんは、不登校になっても自分の子供を信じて、焦らずに暖かい目で見守ってあげてください。生きることのほうが、肝心です。
子ども減っても不登校は過去最多「教室内ストレス」に親ができること
10月28日 14:39

少子化の中で不登校になる割合はどんどん高くなっている(※写真はイメージ)
(AERA dot.)
文部科学省が「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題」(2017年度速報値)を発表し、不登校の子どもは過去最多を更新した。自身も不登校経験者で、多くの当事者を取材してきた不登校新聞の編集長・石井志昂さんが考えるその理由とは。
* * *
文科省の発表によると、昨年度の不登校の子どもの数は5年連続で増加し、16年ぶりに過去最多を更新しました。
不登校の子どもの数は14万4031人(前年度比1万348人増)。小学生の不登校は3万5032人(同4584人増)、中学校は10万8999人(同5764人増)。小学生の不登校は前年度比15%アップと近年でも上り幅が大きなほうとなっています。
もう少し踏み込んで言うと、少子化の中で不登校になる割合はどんどん高くなっているということです。
2001年度の全児童生徒数は1128万8831人でした。かたや2017年度は982万851人と、146万人以上減少し、もっとも少なくなっています。つまり、統計史上、子どもの数が過去最低となるなかで、不登校は過去最多を更新したのです。
なぜ不登校は増えているのか。増加の要因について文科省はこう話しています。
「複合的な要因が絡み合っているので、原因を特定することは難しい」。
私も同意見です。しかし、ここ数年の傾向のなかで、不登校増の新しい要因として考えられる背景を何点か提示したいと思います。
■認知度の高まりと不登校の増加
千葉県習志野市にあるフリースクール「ネモ」理事長の前北海さんは「若い世代の親は『死ぬぐらいなら休んで』という感覚の親も多い。学校もフリースクールとの連携を求めるようになってきた」と、近年の変化について感じていると言います
新しい要因のひとつ目は「不登校に対する認知度の高まり」ではないかと思っています。
北海道札幌市にあるフリースクール「札幌自由が丘学園」のスタッフである新藤理さんも「不登校に対する認識や関心の高まりは肌で感じている」と言います。
背景には「9月1日の子どもの自殺」や「教育機会確保法の成立」をもとに、学校を休むことの重要性や、フリースクールなどの学校外の居場所に対する情報など、メディアを通じて報道される機会も増えてきました。
フリースクールで働く二人の声は、不登校が増加する原因のなかでも、ポジティブな声だと思います。
■“教室内ストレス”が高まる影響とは?
二つ目に考えられる新しい要因は「教室内ストレス」の高まっていることです。こちらはネガティブな要因です。
小・中学校の場合、年間を通じ、クラスメートは固定です。いじめの対象がころころ変わるような教室であった場合、ストレスフルな状態で1年間すごすことになるわけです。
今回の調査結果では「いじめの認知件数」も過去最多を更新しました。全国の学校が認知したいじめの数は、41万4378 件(前年度比9万1235件増)でした。4分の3の学校ではいじめが認知されました。
いじめの増加は、軽微な事案(冷やかし、からかいなど)もいじめとして報告するよう文科省が通達したことも影響したと思いますが、依然としていじめは教室内ストレスのひとつになっていると言えます。
ストレスという点においては、「ブラック校則」もその一端に挙げられます。「下着の色をチェックされる」「頭髪の色は黒を強制される」など、近年社会問題にもなっていますし、クラスの環境がいじめの頻度と関係するとする論文(鈴木智之「学校における暴力の循環と『いじめ』〜大学生を対象にした回想形式の調査結果を起点として」)もあります。
このように「いじめ」「ブラック校則」などの教室内ストレスが高まりは、不登校増の新しい背景だと考えられます。
■不登校の増加は「子どもが変わった」から?
一方、不登校増加の新しい背景とは言えないこととして挙げたいのは「子どもの変化」です。
たとえば、私は1982年生まれ。同世代には、「西鉄バスジャック事件」(2000年)や「秋葉原連続通り魔事件」(2008年)など事件を起こした加害者と同世代であり、「キレる世代」と呼ばれたこともあります。
今回の調査でも、暴力行為に及ぶ中高生が前年より減るなか、小学校では2万3440 人と、前年度より3590人増えていました。報道によれば、教育委員会のなかには「ガマンできない子どもが増えたからではないか」と分析しているところもあるそうです。
では、子どもは変わったのでしょうか。ある公立の小学校教員によれば「子どもがこの数年で悪くなったと感じたことはない」と語っています。
また発達心理学者・浜田寿美男さんも子どもの変化について次のように述べています。
『たかだか50年で、子どもが生物学的変化を遂げるなんてことはあり得ません。変わったのは子どもを取りまく社会状況であり、それが子どもの抱える生きづらさとも関係しているのだと思います』(『不登校新聞』380号 (2014.2.15号) 講演録)
■保護者が知っておきたいこと
「最近の子どもは変わった」とは思いませんが、「教室内ストレス」や「認知度の高まり」など子どもを取り巻く環境は変わりつつあると感じています。
では、もしもわが子が学校を行きしぶったり、不登校になったりした場合はどうしたらいいのでしょうか。
親の方には大前提として知っていただきたいことがあります。
「不登校は親に防げるものではない」ということです。先ほど述べたように、不登校の背景として「親の育て方が悪くて不登校になった」ということはありません。また本人の「怠け」や「弱さ」ゆえに不登校になるわけでもありません。
教室のなかには常にいじめが飛び交っています。「いじめに遭わない子育て」も存在しません。不登校やいじめは「子どもの世界」で起きていることであり、先生や親など大人が容易に介入できるものではないからです。
しかし親は何もできないわけではありません。親は「子どもを守る」ことができます。
ところが、実際に子どもが不登校になると、親や先生が子どもを追い詰めてしまうケースのほうが多いのです。
子どもはいじめを受けていても「学校へ行きたくない」とは言いづらいものです。自分がなぜ行きたくないのか、それを言葉で説明するのも難しかったりします。はっきりと「行きたくない」とは言わず、その理由も語らないとき、周囲は「甘やかしてはいけない」と登校を催促し、子どもを追い詰めてしまいます。
親が不登校やいじめを防ぐことはできませんが、子どもが学校で苦しんでいるとき、親が子どもの味方になってその命を守ることができます。親が「子どもの命を守るんだ」と舵を切れば、自ずと具体的な道筋も見えてくる。子どもが不登校になった親の多くが、そう考えて動いているのです。(文/石井志昂)
学校に無理に子供を登校させても、問題は解決しません。
又陰湿な虐めを受けます。
虐められる方が、悪いと言っても虐められる子供が、また虐められる複雑な虐めの実態です。
不登校が、悪いとは、言えません。
親御さんは、不登校になっても自分の子供を信じて、焦らずに暖かい目で見守ってあげてください。生きることのほうが、肝心です。