本日、 。
。
今日はプランター菜園のお仕事をしました。
プランターは身近にはじめられる自然菜園です。
またの機会にご紹介出来ればと思っております。

今年2回目のシャロムヒュッテでの「あずみの自然農塾」です。
桜が咲いたのにもかかわらず寒い週末でした。

翌日植える準備で、前もってキャベツ、レタス、エンドウ、ソラマメなどの苗に水をたっぷりあげておくと、
植えた後の根の張りがよくなります。

ジャガイモも切り口が乾くように、前もって切っておき干しておくのが大切です。
段取り八分で、前もって行うことをしっかり準備しておくと、自然農はとてもスムーズに自然に沿って栽培できます。


お米の種モミも前日に、水で沈むものだけにしてザルに上げておくことで、種まきしやすくなります。

参加者ほぼ全員が空き地だと思った場所こそ、自然農の耕さない田んぼです。
今は、ムギとレンゲなど冬草が田んぼ全面覆っていて、緑色です。

田んぼの一角で、ワラを敷いたところがあります。
去年の生徒さんと作ったお米の苗代です。

ワラをめくり

根切りしながら整地していきます。

お米の種モミは小さいので、ちょっとしあ凸凹もないように丁寧に整地します。

土の塊を手でもみ崩し、

手で鎮圧して完了です。
自然農は、そのタイトルからして自然奔放なイメージが先行しがちですが、はじめはとても繊細な仕事を要します。
自然の中で食べ物が育つために、最低限の手助けをし、食べ物が自然に適応して育つきっかけをつくります。

手の指と指の間から種を均一に降ろしていきます。


種が重ならないように、播いた後手で調整します。

土をかけた後、鎮圧し、寒い安曇野ではクン炭を撒き、

更に切った切りワラ、

切らない去年のワラ、

そして、不織布も重ねます。
夏草である稲はとても寒さに弱いため、急な冷え込みに耐えられるよう、ワラの蓑(ダウンジャケット)を着せてあげます。

夜は、一品持ち寄りのポトラックパーティーでした。
想いのこもった一品に舌鼓を打ちながら、だんだんに和が広がっていきます。
自然農塾では、栽培だけでなく、交流やシェアリングを大切にし、感性も高めていきます。
感性を高め合うことで、自然の中でどうしたらいいのかわかる身体を磨いて行けるからです。
今月播いたお米の田植えは、6月。
無事、育ってくれますように~。
 ◆お知らせ
◆お知らせ
せた農こと、「せたがや自然農実践倶楽部」からお知らせです。
前回『東京で自然農をはじめよう!』で講師をさせていただいたことをきっかけに、二子玉川にあるせた農の畑にお迎えして『自然農講座パート1:春の種まき編』を行います。
4/29(月・祝)『東京で自然農をはじめよう!自然農講座パート1:春の種まき編』
来月の菜園スクールは、
5/18(土)&19(日)シャロムヒュッテで「あずみの自然農塾」
5/26(日)「Azumino自給農スクール 自然菜園実践コース」
 。
。今日はプランター菜園のお仕事をしました。
プランターは身近にはじめられる自然菜園です。
またの機会にご紹介出来ればと思っております。

今年2回目のシャロムヒュッテでの「あずみの自然農塾」です。
桜が咲いたのにもかかわらず寒い週末でした。

翌日植える準備で、前もってキャベツ、レタス、エンドウ、ソラマメなどの苗に水をたっぷりあげておくと、
植えた後の根の張りがよくなります。

ジャガイモも切り口が乾くように、前もって切っておき干しておくのが大切です。
段取り八分で、前もって行うことをしっかり準備しておくと、自然農はとてもスムーズに自然に沿って栽培できます。


お米の種モミも前日に、水で沈むものだけにしてザルに上げておくことで、種まきしやすくなります。

参加者ほぼ全員が空き地だと思った場所こそ、自然農の耕さない田んぼです。
今は、ムギとレンゲなど冬草が田んぼ全面覆っていて、緑色です。

田んぼの一角で、ワラを敷いたところがあります。
去年の生徒さんと作ったお米の苗代です。

ワラをめくり

根切りしながら整地していきます。

お米の種モミは小さいので、ちょっとしあ凸凹もないように丁寧に整地します。

土の塊を手でもみ崩し、

手で鎮圧して完了です。
自然農は、そのタイトルからして自然奔放なイメージが先行しがちですが、はじめはとても繊細な仕事を要します。
自然の中で食べ物が育つために、最低限の手助けをし、食べ物が自然に適応して育つきっかけをつくります。

手の指と指の間から種を均一に降ろしていきます。


種が重ならないように、播いた後手で調整します。

土をかけた後、鎮圧し、寒い安曇野ではクン炭を撒き、

更に切った切りワラ、

切らない去年のワラ、

そして、不織布も重ねます。
夏草である稲はとても寒さに弱いため、急な冷え込みに耐えられるよう、ワラの蓑(ダウンジャケット)を着せてあげます。

夜は、一品持ち寄りのポトラックパーティーでした。
想いのこもった一品に舌鼓を打ちながら、だんだんに和が広がっていきます。
自然農塾では、栽培だけでなく、交流やシェアリングを大切にし、感性も高めていきます。
感性を高め合うことで、自然の中でどうしたらいいのかわかる身体を磨いて行けるからです。
今月播いたお米の田植えは、6月。
無事、育ってくれますように~。
 ◆お知らせ
◆お知らせせた農こと、「せたがや自然農実践倶楽部」からお知らせです。
前回『東京で自然農をはじめよう!』で講師をさせていただいたことをきっかけに、二子玉川にあるせた農の畑にお迎えして『自然農講座パート1:春の種まき編』を行います。
4/29(月・祝)『東京で自然農をはじめよう!自然農講座パート1:春の種まき編』
来月の菜園スクールは、
5/18(土)&19(日)シャロムヒュッテで「あずみの自然農塾」
5/26(日)「Azumino自給農スクール 自然菜園実践コース」

























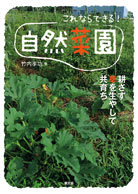






































 のち
のち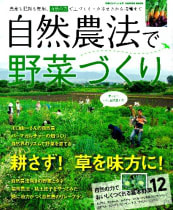



















 雷雨。
雷雨。











































 はこちら
はこちら







