仕事が一段落したとはいえ、相変わらずの宵っ張り、
おかげで、朝起きたら、眠くて眠くて・・悪循環のままです~
なんとか、もう少し、早く寝るようにしないと~
さて、土曜日は、栗東市六地蔵の、和中散本舗に行ってきました。
昨年4月から、毎月、第1土曜日に開けているんですね。

旧東海道に面して建つ、大きなお屋敷。
江戸時代、この地で薬製造販売をしていた豪商大角弥右衛門家の店舗兼住居。
昔は、間口で税金を納めたので、(だから町家は間口が狭くて奥が長い)
これだけ広いというだけで、お金持ちというのがわかりますね!
寛永年間(1624~1644年)の建築とか。

屋号は「ぜさい」。
薬を売るだけでなく、草津宿と石部宿の「間の宿」として、
公家・大名などの休憩所も務めたそうです。
「和中散」は薬の名前で、徳川家康が腹痛をおこした時に、
これを飲んで治ったことから、家康が命名したとか。

店の間。
この日は、街道歩きの人をもてなさそうと、
赤い毛氈を敷いて、お茶の接待、栗東あられの販売などをしています。
入館料は400円。

店の間には、いろいろな昔の道具や看板などが置かれています。

釜は、お湯を沸かし、薬を飲むのに使われたとか。
煎じたり、お茶のようにして飲んだんでしょうかねぇ。

薬類を入れた引き出しタンスですね。

お賽銭箱、ではなく、売り上げのお金いれ、だそうです。
後ろ側に、引き出しをひくとお金を取り出せるようになってるとか。

看板。
店の間の右手に、薬を製造する仕事場があります。
大きな木製の動輪や歯車の付いた製薬用石臼がありました。

動輪は、大き過ぎてカメラに納まりません。
直径4m、人が二人入って、動かしたとか。

動輪から歯車、石臼をまわし、薬草を砕いたんですね。

これほど大きな動輪や薬製造用の石臼の道具が、
今も残っているのは、ここぐらいだと言われています。
店の間の左側、上手に、門があり、奥への玄関となっています。
このあたりは梅ノ木村といわれたところで、
「梅ノ木立場(うめのきたてば)」が置かれていました。
この「間の宿」も、梅の木本陣と呼ばれたとか。

玄関の間がこちら。

本陣側にある門の内側。
大名や公家などやんごとない方はこちらから入ったそうで、
明治期になって来られた「明治天皇御駐踵聖跡」の石碑がありました。

玄関の欄間が二重になっていました。豪華な欄間です。
表側は、めでたい鶴と亀が彫られてます。

裏側は、松と波、でしょうか~
奥の間へいくと、やんごとない方が休憩された上段の間がありますが、
その前に、目に入ってきたのが、りっぱなお庭でした。

冬とはいえ、手入れされたお庭。りっぱなつくばいもあります。

日向山を借景した池泉鑑賞式庭園の庭。小堀遠州作とか。
国の名勝に指定されているそうです。
左手は茶室。
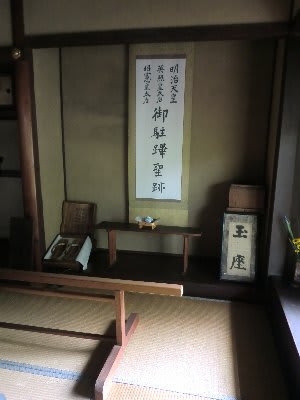
上段の間、床の間には、3回訪れられたという明治天皇が、
お庭を歩くのに使った大きなぞうりも置かれてました。
上段の間には、曽我蕭白(そがしょうはく)の襖絵があるらしいのですが、
貴重な文化財なので、市の歴史博物館で保存してあるそうです。
ひととうり見学して、お茶をいっぷく。
おひな様に見立てたお菓子とお煎茶で。

街道の向かい側にあるのは、馬止め。井戸も見えます。
現在もこの建物の奥に、大角家のお住まいがあるそうですが、
店の間、製薬場、台所、居間と玄関及び屋敷、正門、隠居所などが、
国の重要文化財に、住宅全体が国の史跡に指定されているそうです。
旧東海道をウオーキングする人が増え、
ここを見学したいという声が、多く聞こえるようになったので、
月に一度、開場することにしたそうです。
普段は、予約見学のみ。
以前、この梅ノ木立て場のことを、記事にしたことがあります。
和中散本舗の建物は、『東海道名所図会』にも描かれるほどで、
図書館で借りて、チェックしました~
また、行ってみたいですね~
おかげで、朝起きたら、眠くて眠くて・・悪循環のままです~
なんとか、もう少し、早く寝るようにしないと~
さて、土曜日は、栗東市六地蔵の、和中散本舗に行ってきました。
昨年4月から、毎月、第1土曜日に開けているんですね。

旧東海道に面して建つ、大きなお屋敷。
江戸時代、この地で薬製造販売をしていた豪商大角弥右衛門家の店舗兼住居。
昔は、間口で税金を納めたので、(だから町家は間口が狭くて奥が長い)
これだけ広いというだけで、お金持ちというのがわかりますね!
寛永年間(1624~1644年)の建築とか。

屋号は「ぜさい」。
薬を売るだけでなく、草津宿と石部宿の「間の宿」として、
公家・大名などの休憩所も務めたそうです。
「和中散」は薬の名前で、徳川家康が腹痛をおこした時に、
これを飲んで治ったことから、家康が命名したとか。

店の間。
この日は、街道歩きの人をもてなさそうと、
赤い毛氈を敷いて、お茶の接待、栗東あられの販売などをしています。
入館料は400円。

店の間には、いろいろな昔の道具や看板などが置かれています。

釜は、お湯を沸かし、薬を飲むのに使われたとか。
煎じたり、お茶のようにして飲んだんでしょうかねぇ。

薬類を入れた引き出しタンスですね。

お賽銭箱、ではなく、売り上げのお金いれ、だそうです。
後ろ側に、引き出しをひくとお金を取り出せるようになってるとか。

看板。
店の間の右手に、薬を製造する仕事場があります。
大きな木製の動輪や歯車の付いた製薬用石臼がありました。

動輪は、大き過ぎてカメラに納まりません。
直径4m、人が二人入って、動かしたとか。

動輪から歯車、石臼をまわし、薬草を砕いたんですね。

これほど大きな動輪や薬製造用の石臼の道具が、
今も残っているのは、ここぐらいだと言われています。
店の間の左側、上手に、門があり、奥への玄関となっています。
このあたりは梅ノ木村といわれたところで、
「梅ノ木立場(うめのきたてば)」が置かれていました。
この「間の宿」も、梅の木本陣と呼ばれたとか。

玄関の間がこちら。

本陣側にある門の内側。
大名や公家などやんごとない方はこちらから入ったそうで、
明治期になって来られた「明治天皇御駐踵聖跡」の石碑がありました。

玄関の欄間が二重になっていました。豪華な欄間です。
表側は、めでたい鶴と亀が彫られてます。

裏側は、松と波、でしょうか~
奥の間へいくと、やんごとない方が休憩された上段の間がありますが、
その前に、目に入ってきたのが、りっぱなお庭でした。

冬とはいえ、手入れされたお庭。りっぱなつくばいもあります。

日向山を借景した池泉鑑賞式庭園の庭。小堀遠州作とか。
国の名勝に指定されているそうです。
左手は茶室。
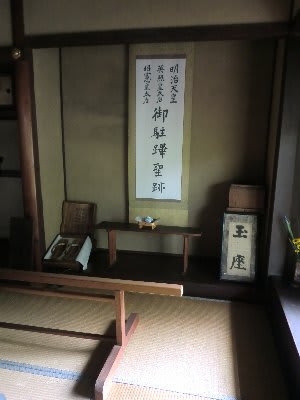
上段の間、床の間には、3回訪れられたという明治天皇が、
お庭を歩くのに使った大きなぞうりも置かれてました。
上段の間には、曽我蕭白(そがしょうはく)の襖絵があるらしいのですが、
貴重な文化財なので、市の歴史博物館で保存してあるそうです。
ひととうり見学して、お茶をいっぷく。
おひな様に見立てたお菓子とお煎茶で。

街道の向かい側にあるのは、馬止め。井戸も見えます。
現在もこの建物の奥に、大角家のお住まいがあるそうですが、
店の間、製薬場、台所、居間と玄関及び屋敷、正門、隠居所などが、
国の重要文化財に、住宅全体が国の史跡に指定されているそうです。
旧東海道をウオーキングする人が増え、
ここを見学したいという声が、多く聞こえるようになったので、
月に一度、開場することにしたそうです。
普段は、予約見学のみ。
以前、この梅ノ木立て場のことを、記事にしたことがあります。
和中散本舗の建物は、『東海道名所図会』にも描かれるほどで、
図書館で借りて、チェックしました~
また、行ってみたいですね~




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます