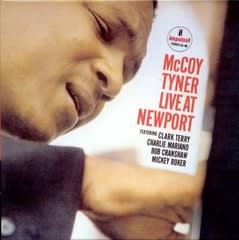連日のポカポカ陽気で、今日の昼飯には早々と冷やし中華を食べてしまったです。
いや、なにより驚愕したのは、こんな時期にメニューに入れている店の根性! 美しいですね。
ということで――
■The George Benson Cookbook (Columbia)

1976年に出した「ブリージン」のメガヒットで、一躍トップスタアとなったジョージ・ベンソンが、その10年前に出していたリーダー盤です。もちろん、この頃はジャズギタリストとしての持ち味が強く出た作風ながら、ウェス・モンゴメリーの再来としての位置付けというか、かなりポップなソウルジャズとかボーカリストとしての才能も聞かせる内容になっています。
なによりもメジャーなコロムビアと契約していたところが、スタア性の証でしょうか。
録音は1966年8~10月、メンバーはジョージ・ベンソン(g,vo)、ロニー・スミス(org)、マリオン・ブッカー(b)、ジミー・ラブレス(ds)、ロニー・キュー(bs)、そしてベニー・グリーン(tb) という、なかなか興味津々の顔ぶれです――
A-1 The Cooker
いきなりテンションの高いリフがギターとバリトンサックスのユニゾンで演じられますが、このテーマが高速4ビートでジョージ・ベンソンのアドリブフレーズに直結する物凄さです。いやはや、全く奔放、ワイルドにして緻密なギターソロは圧巻! ウェス・モンゴメリーに加えてグラント・グリーンの影響がモロ出しなのも嬉しいですねぇ♪
演奏は中間部で緊張感の強いブレイクやバリトンサックスとのユニゾンリフいう仕掛けもあり、ジミー・ラブレスのドラミングも白熱化して悶絶の連続です。
ちなみにロニー・キューバのバリトンサックスは、スピード感とアタックの強さを両立させた優れもの♪ 白人らしいスマートさもありながら、新時代のジャズを強く感じさせてくれます。
A-2 Benny's Back
前曲の続篇のようなジョージ・ベンソンのオリジナル曲で、仕掛けの多いユニゾンリフをすりぬけて吹きまくるベニー・グリーンのオトボケトロンボーン、そしてシャープなロニー・キューバのバリトンサックスが大暴れします。
またロニー・スミスのオルガンも待ってましたの出番で荒れ狂い、もちろんジョージ・ベンソンのグイノリのギターソロには唖然とさせられます。基本に忠実な伴奏のコード弾きも味わい深いですよ。
う~ん、それにしても猛烈なスピード♪ 小川ローザの世界ですね。
A-3 Bossa Rocka
タイトルどおり、真性ボサロックという和みの演奏です。
ジョージ・ベンソンのギターはウェス・モンゴメリーに比べると、些かの硬さがありますが、自身が作曲した魅惑のテーマメロディを上手く展開させていくのは流石♪ ロニー・スミスのオルガンも涼やかですし、ジミー・ラブレスのドラミングがイナタイ味わいで、たまりません。
正体不明のタンブリンも良いアクセントになっていますね。
A-4 All Of Me
有名スタンダードを遠慮なく、ノーテンキに歌うジョージ・ベンソン!
強いアクセントが付いたアップテンポの4ビートは抜群のノリで、ロニー・キューバの豪快なバリトンサックス、心地良いギターのコードワーク、さらに自分が一番楽しんでいるジョージ・ベンソンのボーカルは、本当に憎めませんね。
A-5 Farm Boy
これまたノーテンキなソウルジャズ♪ ミニスカお姉ちゃん達のゴーゴーダンスが目に浮かんでくるような楽しさです。
ジョージ・ベンソンのアドリブはちょっと過激なフレーズも弾いていますが、むしろ伴奏でのコードワークが最高♪ キューバ&スミスのダブルロニーも浮かれた調子ですし、ジミー・ラブレスのイモ寸前ドラミングが強烈な存在感!
まさに1960年代後半というか、昭和40年代前半の雰囲気がムンムンして、私のような者には何時までも聴いていたい演奏です。
B-1 Benson's Rider
これもボサロックでファンキーを演じたようなアクの強い名演です。
ただし演奏全体が、些かねじれたようなノリですから、好き嫌いがあるかもしれません。はっきり言えば、バラバラ寸前のところさえあります。
しかしジョージ・ベンソンのギターソロは硬派ですし、手抜きはいっさい無し! さらにロニー・スミスのオルガンがイナタイ味わいで、けっこう泣けてきます。ジョージ・ベンソンのギターが上手い合の手と絡みで、これも飽きませんね。
う~ん、ちょいとゾクゾクしてきました。
B-2 Bayou
またまた高速4ビートの正統派ジャズ路線という猛烈な演奏です。
痛快なテーマアンサンブルに続いて飛び出すロニー・キューバのバリトンサックスがツッコミ鋭く、どうにもとまらないという山本リンダ現象! するとジョージ・ベンソンも指が勝手に動いてしまったようなアブナイ雰囲気で、凄まじいフレーズの嵐を聞かせてくれます。ピッキングも神業だと思います。
しかし、正直、疲れます……。
B-3 The Borgia Stick
ちょっとジャズクルセダーズが演じそうなソウル色が強い新主流派のテーマが新鮮なところですから、ジョージ・ベンソンのアドリブも極めて真っ当な世界を追求しています。
それが物足りなくもあり、逆に凄いところなのかもしれませんが……。
重苦しいアレンジが裏目に出たような……。
B-4 Return Of The Podigal Son
これは私の大好きな演奏で、曲はフレディ・ハバードもやっている日活モードのジャズロック♪ このテーマメロディとグルーヴは、モロに昭和40年代前半の味わいですよ♪ あぁ、何度聴いても、グッとシビレます。思わず、ピーコック・ベイビィ~♪ と歌ってしまいそうですね。
ジョージ・ベンソンのアドリブも感情的な部分と歌うメロディのバランスが素晴らしく、リズム隊のドC調な雰囲気がズバリ、素晴らしい名演の秘密ですねっ♪ わずか2分半ほどのトラックですが、それが逆に最高だと思います。
B-5 Jumpin' With Symphony Sid
オーラスはビバップ時代から演奏されている隠れ名曲♪ 高名な司会者にして興行師でもあったシンフォニー・シッドに捧げてレスター・ヤングが書いた楽しいリフ曲ですから、快適なリズム隊にノセられて、まずはベニー・グリーンがホンワカしたトロンボーンを存分に聞かせてくれます。
そしてジョージ・ベンソンが4ビートの楽しさを追求すれば、ロニー・キューバはビバッブ丸出しの潔さ! ロニー・スミスもそれに追従すれば、今度はホーン陣がバックからは味わい深いリフを被せてくるという王道路線が楽しいところです。
ということで、楽しい演奏がぎっしりなんですが、些かプロデュースがとっ散らかった按配で、アルバム全体に統一感が不足している感じです。しかしそれだけバラエティ……。
個人的には「Farm Boy」とか「Return Of The Podigal Son」のような演奏をメインにして欲しかったですねぇ。
とはいえ、やっぱりジョージ・ベンソンは凄いです。アドリブソロも強烈ですが、バッキングの楽しさ、エグサ、そして上手さには感動を覚えます。
そして車の中でも聴きたいので、CDが欲しい1枚ですね。