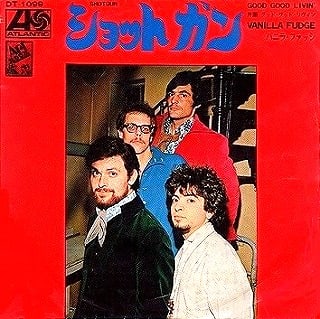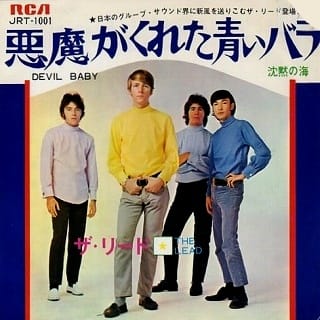■二人の絆 / Harold Melvin & The Blue Notes (PIR / CBSソニー)

もちろん自分だけじゃ~ない事は分かっているんですが、最近のサイケおやじは仕事諸々の困難重圧に潰されそうな本音を隠そうと必死です。
そこで、一番欲しいものは心の安寧というか、なにかホッとする瞬間を求めてしまうんですねぇ。
例えば本日ご紹介のシングル曲「二人の絆 / If You Don't Know Me By Now」は、今やディスコのチークタイムでは定番化しているフィリーソウルの「甘茶」の名唱なんですが、これが日常でも煮詰まった状況の中に流れてくると、意想外に心が和んでしまうんですから、やっぱり不滅の名曲はそうなるだけの絶大な価値を秘めているんでしょう。
歌っているハロルド・メルヴィン&ブルー・ノーツは、1950年代から活動していたベテランの黒人R&Bコーラスグループとはいえ、結果的にブレイクしたのは、この「二人の絆 / If You Don't Know Me By Now」が大ヒットした1972年以降でしょう。
特に我国では、同じフィリーソウルの人気上昇期に流行りまくったオージェイズの「裏切者のテーマ」やスリー・ディグリーズの「荒野のならず者」と並んで、そのイメージを決定的にする大きな役割を果たしていたと思います。
というか、「二人の絆 / If You Don't Know Me By Now」によって、演じているハロルド・メルヴィン&ブルー・ノーツはもちろんの事、所謂「甘茶」の魅力に目覚めたファンも数知れず、それがまたフィリーソウルを飛び越えてのディスコブームに繋がる下地になったという、結果論的な推察も可能だと思うばかり♪♪~♪
ちなみに、その「甘茶」とは、黒人音楽愛好者のマニア用語であって、一般的には「スウィートソウル」を指すわけですが、特に1970年代の黒人ソウルグループが演じる甘~い曲調のスローバラード、時にはムードコーラスに限りなく近いものまでも含む総称と、サイケおやじは解釈しておりますので、念の為。
で、肝心の演じているハロルド・メルヴィン&ブルー・ノーツは既に述べたとおり、長いキャリアゆえに結成当時からのメンバーチェンジも当然あって、1972年頃にはハロルド・メルヴィン、テディ・ペンダーグラス、ベルナルド・ウィルソン、ローレンス・ブラウン、ロイド・パークスという5人組になっていたわけですが、後に知ったところでは、彼等は自ら楽器を演奏して歌うバンドスタイルのグループとしてドサ回りをやっていたという、なにか苦節の裏話もリアルですねぇ。
それが当時、フィラデルフィアを本拠地として新しいソウルミュージックを作り出さんとしていたケニー・ギャンブル&レオン・ハフの新会社たるPIR=フィラデルフィア・インターナショナル・レコードと契約する事により、既にリードシンガーとして個性を発揮していたテディ・ペンダーグラスの魅力が大きく開花♪♪~♪
グループとしても時代の流行の先を行く洗練を表現出来るようになったのは、ブルー・ノウツが本来からフィラデルフィア出身であった事に加え、ハロルド・メルヴィンがケニー・ギャンブルと幼馴染だったという縁も深いところでしょうか。
とにかくイントロからグッとムードが高まる濃厚なストリングと甘いメロデイのコーラスをキメとして、テディ・ペンダーグラスの男の道の如き力強いリードは、同時に絶妙の泣きを含んでいるんですから、たまりません。
もしも 今でも
俺のことを分かっていないのなら
この先だって ずぅ~っと お前には
理解なんて 出来はしないさ
と歌われる内容は、実は朝帰りでもした男の夫婦喧嘩の末の苦しい言い訳らしく思えるんですが、それが「甘茶」ならではの美メロとコーラスに彩られる時、結局はメイキンラヴにしか解決策を見出せない、まあ、当たり前の成り行きに♪♪~♪
そんな愛情も、日常の中の事件が二人の絆を強くするんでしょうかねぇ……。
根本的に自分の事しか見えていない自己完結型のサイケおやじには、どうにもそんな境地には辿りつけない分だけ、それも「甘茶」の魅力と憧れるわけですよ。
それでも、この「二人の絆 / If You Don't Know Me By Now」の威力は絶大で、発売翌年には世界中でメガヒットを記録し、さらにはイーグルスの「Take It To The Limit」やシカゴの「If You Leave Me Now」等々、モロパクリの白人ロックパラードが世に出ていくのですから、決して侮れる世界ではありません。
特にストリングアレンジの確固たる個性は、そのイーグルスにおいてはコーラスワークも含めて、絶大な影響下にある事は言うまでもないはずです。
ということで、今となっては「二人の絆 / If You Don't Know Me By Now」だけが突出している感も強いハロルド・メルヴィン&ブルー・ノーツではありますが、もちろん十八番の「甘茶」に加えて、彼等はアップテンポの所謂フィリーダンサーも素晴らしいんですよねぇ~~♪
そのあたりも何れはご紹介していく所存ではありますが、グループとしては1970年代後半を絶頂期としてメンバーチェンジが相次ぎ、看板スタアのテディ・ペンダーグラスが独立して以降は、些か精彩を欠いています。
しかし、それでもブルー・ノーツが現在も存続しているのは、やはりスウィートソウルな世界に絶対的な強みがあるからでしょう。当然ながら「二人の絆 / If You Don't Know Me By Now」と同質の味わいを持ったヒット曲を多数放っているのですからねぇ~♪
そしてこれから「甘茶」の世界を楽しまれんと決意されている皆様には、とにかく1970年代のハロルド・メルヴィン&ブルー・ノーツ、そして「二人の絆 / If You Don't Know Me By Now」を堪能して欲しく思います。
まちがいなく、ホッと和みますよ♪♪~♪