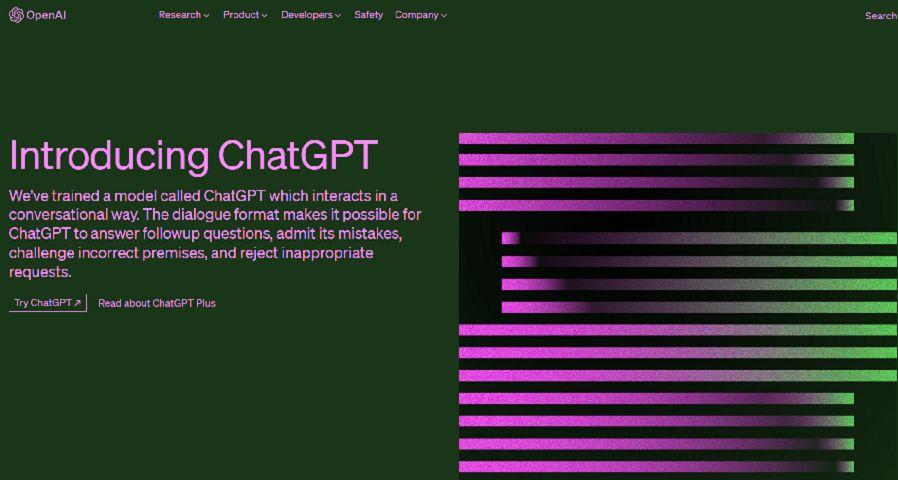【こちら特報部】:利用者急増中のChatGPT…この勢いは本物なのか 日本のAI研究者が予測する未来の姿は
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【こちら特報部】:利用者急増中のChatGPT…この勢いは本物なのか 日本のAI研究者が予測する未来の姿は
質問を入力するだけですぐに自然な言葉で説得力のある回答が返ってくる、対話型の人工知能(AI)ソフト「チャットGPT」。昨年11月に公開されると、わずか2カ月で利用者が1億人を超えた。この勢いは本物か。4月に行われたAIの専門家による対談では、チャットGPTが世界を変えうる可能性があると評価。一方、海外では利用を一時停止したり、著名な企業家らがAI開発の休止を求めたりするなど、その反応は割れている。(岸本拓也、西田直晃)
チャットGPT 米新興企業オープンAIが開発した人工知能(AI)を使った対話型ソフト。ネット上の膨大な文章や画像データをAIに読み込ませて訓練する大規模言語モデル(LLM)と呼ばれる技術が使われ、質問を打ち込むと、自然な言葉で回答してくれる。生成AIとも言う。昨年11月に無料公開され、急速に利用が広がった。最新版の「GPT—4」は米司法試験で上位10%の成績を出した。一方、もっともらしい回答をするが、内容が全くの虚偽の場合もあり、イタリアなど使用を制限する国も出ている。
◆盛り上がり「ネットやスマホが出てきたとき以来」
対談するパークシャテクノロジーの上野山勝也社長(左)と、東大の松尾豊教授=東京都内で(パークシャ提供)
「スピードが大事だと言ってきたはずなのに、最近のビッグテック(巨大IT企業)のスピードを見ていると、自分は何て遅いんだと再認識している」
4月4日、都内で行われた対談。日本を代表するAI研究者である東大大学院の松尾豊教授は、最近のチャットGPTを巡る動きの早さに驚いているという。周囲のAI研究者たちの反応について、「騒然としている。いろんな意味で変わり目にある」とも語った。
チャットGPTが公開された昨年11月以降、国内外のさまざまな企業がこの技術を利用した関連サービスの開発を進めている。オープンAIに投資している米マイクロソフトは1月、今後さらに数十億ドル規模の投資を行うと表明した。それに対抗して米グーグルが2月に対話型AI「バード」を発表し、フェイスブックを運営する米メタも年内に商用化する構えだ。
AI界隈は今、チャットGPTを軸に空前の対話型AIブームに沸く。だが、松尾氏は「一時的なトレンドではない」と言い切る。対談相手で、対話型AIサービスを手掛けるパークシャテクノロジー(東京)の上野山勝也社長も「これくらい新しいフロンティアが広がっているのは珍しい。ネットやスマホが出てきたとき以来ではないか」と指摘した。
松尾氏は、チャットGPTの特徴を「(技術的に)やっていることは、次の単語を予測して表示しているだけ。しかし、相当複雑な概念も学習していて、プロンプト(指示文)でうまく引き出すと、良い答えが返ってくる。これは従来なかった技術だ。これから世の中に広がっていくことは間違いない」と説明した。
◆「失言で辞職」がなくなる?
チャットGPTを運営するOpenAIのウェブサイト(スクリーンショット)
チャットGPTなど、文章や画像を生成するAIは、ネット上の膨大なデータを読み込ませて訓練する大規模言語モデル(LLM)と呼ばれる技術が使われている。条件を設定すれば、詩や小説といった創作物を作ることもできる。
上野山氏が「ネット上のデータを集めて圧縮して新しいモデルに置き換えるのは、新しい知性を生み出していると言えるのか」と問うと、松尾氏は「生み出していると思う」と断言。「確かに学習データはネット上のものだが、大体の創造性というのは(既存知識の)類型化とその混ぜ合わせだ。そう考えると、チャットGPTがやっているのはかなり創造的と言える」との見方を示し、こう続けた。「逆に人間にしかできないのは、目的に照らして知能を使うこと。人間がうれしいことや楽しいこと、世の中のためになる目的を考え、AIとのコンビで新たな知を生み出していける」
対談で松尾氏は、チャットGPTが差別などの問題発言をしないように調整されていることから、コミュニケーションが変わる可能性にも触れた。一例として政治家がARグラスを使い、そこにリアルタイムで表示されるチャットGPTが作った文章を読み上げるようになり、「失言して大臣が辞めることが昔話になるかも」と話した。
仕事のあり方も変えそうだという。松尾氏が2月の自民党の会議で示した資料では、ワードやエクセルなどのマイクロソフトのオフィス製品がすべて変わり、「人間が自分で打つ時代が終わり、情報の集約や要約、可視化まで(チャットGPTなどのAIによって)自動化されていく可能性」に言及。「ホワイトカラーの仕事のほとんどすべてに何らかの影響がある可能性が高い」と結論づけ、2〜3年で身近に変化が生まれるとの見通しを示した。
世界的な大変化を前に日本企業はどう対応すべきかという点について、松尾氏は対談で、「新時代なので今この瞬間は何をやっても良い。期せずしてみんながよーいドンの状態。グーグルなどのビッグテックもこれはやばいと思って全力で走りだした。日本も大きな構想をもってやった方が良い」と積極的に利用や開発に取り組むことを勧めた。
◆開発停止を求める声も続々
聞こえてくるのは期待の声だけではない。高性能すぎるがゆえの慎重論も目立っている。
AI開発の一時停止を求める署名活動に賛意を示した起業家のイーロン・マスク氏=2020年3月、米ワシントン(AP・共同)
「巨大なAI実験を停止せよ」。3月下旬、米国の非営利団体「フューチャー・オブ・ライフ・インスティチュート」はこう銘打った書簡を公開した。賛同者は続々と増え、4月7日時点で1万6000超の署名が集まった。顔触れは、ツイッターを買収したイーロン・マスク氏、米アップル共同創業者のスティーブ・ウォズニアック氏ら。影響力の強い経営者やAI研究者が名を連ねる。
書簡では、より進化したAI開発について、少なくとも半年間の休止を要求。「人間と競合する知能があるAIは、人類と社会に深刻な危険をもたらしうる」と定義し、「プロパガンダ(政治宣伝)や真実でない情報を社会にあふれさせるべきなのか」「全ての仕事を自動化するべきなのか」と訴えた。過熱するAI開発の現状を「制御できない競争に陥っている」と指摘した上で、「半年間の休止期間を活用し、外部の専門家が関わる形で、高度なAI開発についての安全規定を共同で構築すべきだ」と呼びかけている。
◆適切な規制の仕組みが必要
規制を求める声は出版・教育界からも。思考力の養成を妨げ、論文や作文での不正利用が横行しかねないためだ。米科学誌サイエンスはチャットGPTが作った論文は「盗作」と扱う考えを示した。ニューヨーク市は公立学校での利用をすでに禁じ、文部科学省は2023年度内にも学校での取り扱い指針を設ける方針という。
7日時点では、イタリアだけが使用そのものを禁じている。ITジャーナリストの星暁雄氏は「EU諸国は個人情報管理を厳しく規制する一般データ保護規則(GDPR)がある。イタリアはプライバシー侵害の可能性を問題視しており、周辺国にも波及する可能性がある」と述べる。
「リスクを放置するのは非常に危険だが、オープンAI社最高経営責任者のサム・アルトマン氏も『必要な規制はある』と言っている。一私企業の裁量に任せず、早期に適切な仕組みを構築することが求められる」
◆デスクメモ
みんながAIを使い、世にはAIによる文章があふれ、それをまたAIが学習し、誰かの問いに答える。それが重なっていった時、AIによるAIの思想・表現・言葉が世の主流になっていくのかもしれない。そうなったとき「人間にしかできないこと」はどれくらい残っているのか。(歩)
元稿:東京新聞社 主要ニュース 社会 【話題・連載・「こちら特報部」】 2023年04月10日 12:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

















 </picture>
</picture>
 </picture>
</picture> </picture>
</picture>
 </picture>
</picture>