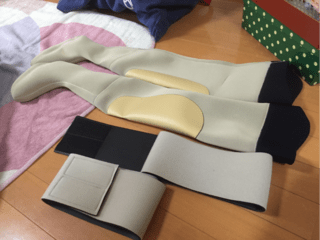RAT24発行
さて、二ヶ月に一度の恒例、偶数月の20日前後に発行されている。私が参加させていただいているデザイン誌「RAT」24号が発行されました。
今回のテーマは「冒険」
何を書くか悩みながら、娘が生まれてからやってきた様々な試みについて、まとめてみることにしました。
こうした文字制限のある原稿に、自らの過去を整理するという作業。ものすごく自分と向き合う上で有効ですね。
やるうちに、第三者的に自らの経験や当時の状況を眺め、俯瞰できます。
また、その上であらためて。当時のことに思いを馳せ、様々な気づきを得たりします。
まさに、この雑誌の寄稿のための原稿作りが、自らの振り返りになっているわけです。
このことに気がつくたびに、この雑誌に寄稿する機会を作っていただいた編集長の北野さんに感謝する気持ちになります。
なかなかできないことのように思います。
ともあれ、今回も。私以外の方々の作品も素晴らしい作品ぞろい。裏表紙には久々に夜空の写真が出ています。
「冒険」っていろんな意味があるんだなぁ。
そんなことを考えながら、ゆっくり読みたいなと思います。
今は、いましばらく。
私はゆっくり読む余裕がないんですけれどもね。(^O^)
明日は6時起きでレジャープールに行きます。
相変わらず忙しい。
やれやれです。



さて、二ヶ月に一度の恒例、偶数月の20日前後に発行されている。私が参加させていただいているデザイン誌「RAT」24号が発行されました。
今回のテーマは「冒険」
何を書くか悩みながら、娘が生まれてからやってきた様々な試みについて、まとめてみることにしました。
こうした文字制限のある原稿に、自らの過去を整理するという作業。ものすごく自分と向き合う上で有効ですね。
やるうちに、第三者的に自らの経験や当時の状況を眺め、俯瞰できます。
また、その上であらためて。当時のことに思いを馳せ、様々な気づきを得たりします。
まさに、この雑誌の寄稿のための原稿作りが、自らの振り返りになっているわけです。
このことに気がつくたびに、この雑誌に寄稿する機会を作っていただいた編集長の北野さんに感謝する気持ちになります。
なかなかできないことのように思います。
ともあれ、今回も。私以外の方々の作品も素晴らしい作品ぞろい。裏表紙には久々に夜空の写真が出ています。
「冒険」っていろんな意味があるんだなぁ。
そんなことを考えながら、ゆっくり読みたいなと思います。
今は、いましばらく。
私はゆっくり読む余裕がないんですけれどもね。(^O^)
明日は6時起きでレジャープールに行きます。
相変わらず忙しい。
やれやれです。