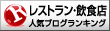本日発売の村上春樹の新作「女のいない男たち」。
前作「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」に私はおおいに失望したので
今回の短編集を楽しみにしていたのでした。
夕食後読み出して、読み終わったばかりでまだ感想はまとまっていないのですが
感じたことをを少しばかり書いてみます。
印象としては「1Q84」以前の春樹ワールドが少し戻って来たような気がします。
前書きで著者が”ビートルズの「サージェントペパーズ」やビーチボーイズの「ペットサウンド」
のようなコンセプトアルバムを意識して書いた”と言っているだけあって
短編の題名も「ドライブ・マイ・カー」とか「イエスタディ」とか、昔懐かしいのが揃っている。
「イエスタディ」という短編には、その歌を関西弁に訳して歌う男が出てくるのですが
前書きによると”歌詞の改作に関して著作権代理人から示唆的要望を受けた”のだそうです。
なので大幅にカットされてしまって
”昨日は/あしたのおとといで
おとといのあしたや”
だけしか出ていません。
関西弁の「イエスタディ」のフル・バージョンが見たかったな…
「ドライブ・マイ・カー」の北海道中頓別(なかとんべつ)町の問題は
新聞で読んで知っていました。
小説の中で、中頓別町出身の女性が火の付いたたばこを車の窓から捨てた際、
「たぶん中頓別町ではみんなが普通にやっていることなのだろう」と主人公が思うのです。
それに関して、「町民の防災意識は高い。『車からのたばこのポイ捨てが普通』というのは事実ではなく、
町をばかにしている。」と中頓部町の町議が異議を申し立てたというもの。
で、本作では町名は別の架空のものとなっていました。
北海道の小さな過疎の町が、春樹の小説によって世界的に有名になった方が面白いのじゃないかと
私は思ってしまうのですが。
「シェエラザード」には、私の前世はヤツメウナギだったという女性が出てくる。
ヤツメウナギ、以前、下町の有名な鰻屋に私が行った時にそのメニューがあったので
どんなものかと調べたことがあったのです。
画像を見て、そのグロさに驚きました。
口が巨大な吸盤のようになっている。
この女性は「私にははっきりとした記憶があるの。水底で石に吸い付いて、
水草にまぎれてゆらゆら揺れていたり、上を通り過ぎていく太った鱒を眺めたりしていた記憶が」
と事もなげに言うのです。

ヤツメウナギ Wikipediaより
表題作「女のいない男たち」には
”新しい消しゴムを迷いもなく半分に割って差し出す”14歳のエムという女の子と
”西風が吹くだけで勃起してしまう”14歳の僕が出てきます。
この短編集全体を無理にまとめたような作品で私には不満が残るのですが
春樹の初期の作品の匂いが少々楽しめるような気がします。
”僕のハックルベリー・フレンド。川の曲りの向こうに待っているもの…。
でもそんなものはみんなどこかに消えてしまった。
後に残されているのは古い消しゴムの片割れと、遠くに聞こえる水夫たちの哀歌だけだ。”
しかしこの作品、短かすぎ。
せっかく十四歳のみずみずしさ、そしてそれを懐かしむ切ない思いを
久しぶりに思い出したような気がしたのに。
「女のいない男たち」
http://www.amazon.co.jp/%E5%A5%B3%E3%81%AE%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E7%94%B7%E3%81%9F%E3%81%A1-%E6%9D%91%E4%B8%8A-%E6%98%A5%E6%A8%B9/dp/4163900748