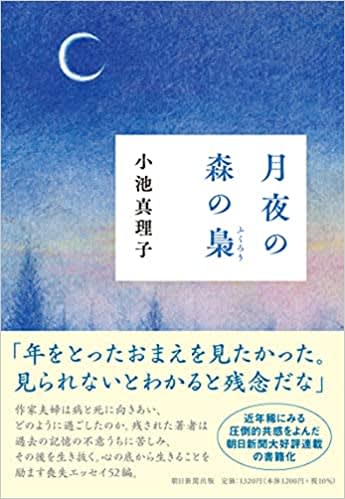
37年一緒に過ごした伴侶・藤田宜永を亡くした小池真理子の、悲しみに満ちた喪失エッセイ。
肺癌の宣告を受けてから2年弱で亡くなるまで、作家夫婦はどのように病や死と向き合ったのか。
”昨年の年明け、衰弱が始まった夫を前にした主治医から「残念ですが」と言われた。「桜の花の咲くころまで、でしょう」と。以来、私は桜の花が嫌いになった。見るのが怖かった。”
どの章も悲しみに溢れていますが、若い頃は人は老いるに従って色々なことが楽になるに違いないと思っていたが、それはとんでもない間違いだった、老年期の落ち着きは殆どの場合見せかけのものに過ぎず、大抵の人は心の中でどうにもしがたい感受性と日々、闘って生きているという文章が、印象的でした。
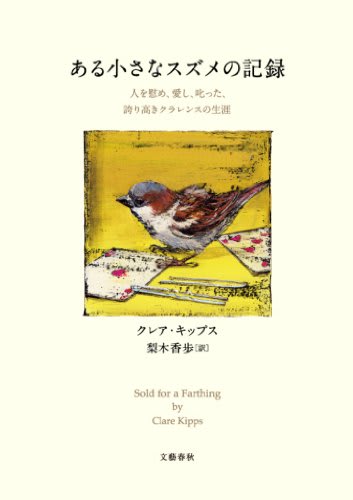
戦時下の1940年7月、ロンドン郊外で生まれたばかりの子雀が老婦人に拾われた。
脚と翼に障害を持って瀕死の状態の雛であったが、著者の献身的な愛情に包まれてすくすくと育っていく。
その雀との12年間の愛情記録物語。
雀が人に懐き、毎晩一緒のベッドで休み、求愛ダンスを見せ、芸を披露して爆撃下の市民の慰めとなり、著者がピアノを弾くと一緒に歌うなんて。
信じられませんが、写真も残っているのです。
そしてこの本を書き始めたのが、雀が12歳を過ぎて病気と老衰によって弱って行った頃で、そして死んだ後に書き終えたというのです。
後書きによれば、これを訳した梨木香穂も、その最中に12年間過ごした愛犬を亡くしたということ。
だからなのか、全体に少々堅苦しい文体ながらも抑えたユーモアが漂う中に、漠とした悲しみが満ちている気がします。
人は愛するものを失くしても、生きて行かなければならないのね…
そしてこの本を書き始めたのが、雀が12歳を過ぎて病気と老衰によって弱って行った頃で、そして死んだ後に書き終えたというのです。
後書きによれば、これを訳した梨木香穂も、その最中に12年間過ごした愛犬を亡くしたということ。
だからなのか、全体に少々堅苦しい文体ながらも抑えたユーモアが漂う中に、漠とした悲しみが満ちている気がします。
人は愛するものを失くしても、生きて行かなければならないのね…



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます