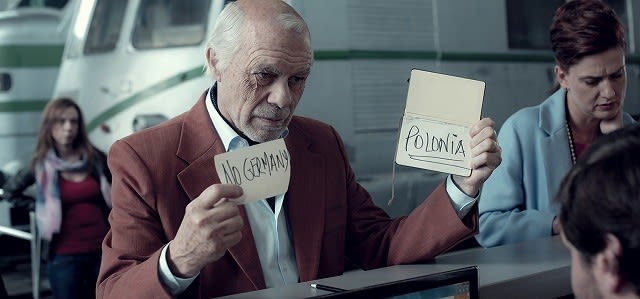村上龍の「限りなく透明に近いブルー」が芥川賞を取って評判になったのは
私が高校生の時でした。
福生の横田基地の近くの米軍住宅で、酒やドラッグやセックスに明け暮れる
退廃的な若者たちを描いた小説。
私はちっとも好きではなかったのですが、その斬新なタイトルも内容も
あまりにも衝撃的でした。
で、東京の西の端っこのその街に、いつか行ってみたいと思っていたのです。
私が高校生の時でした。
福生の横田基地の近くの米軍住宅で、酒やドラッグやセックスに明け暮れる
退廃的な若者たちを描いた小説。
私はちっとも好きではなかったのですが、その斬新なタイトルも内容も
あまりにも衝撃的でした。
で、東京の西の端っこのその街に、いつか行ってみたいと思っていたのです。


この不格好な機体(UH-60J救難ヘリコプター)の左下に出ている長いパイプのようなものは
空中で給油する際に使うのだそうです。
こちらの機体の左下に出ている燃料パイプに連結して。
操縦できるように方向舵が付いてるのですって。

飛びながらそんなことまでできちゃうのか、というレベルの私に
軍機オタクの友人が色々と解説してくれて、非常に便利。

こんな派手な戦闘機も。
福岡自衛隊の60周年記念八咫烏号塗装機 だそうです。

こんな楽しい戦闘機も。
莫大な軍事費を使って遊んじゃってもいい訳ね。

ジェットエンジンの部分に歌舞伎の隈取の顔がついています。
昨日は想定外に暑く、広大な敷地には陽射しをさえぎるものは殆どなく、
何万人もの人混みの中で歩き廻った結果は2万歩強。
接してくれた米軍のお兄ちゃんたちは明るくニコニコとしていて
「限りなく…」の中の暴力的・退廃的なイメージは微塵もなかったのでした。