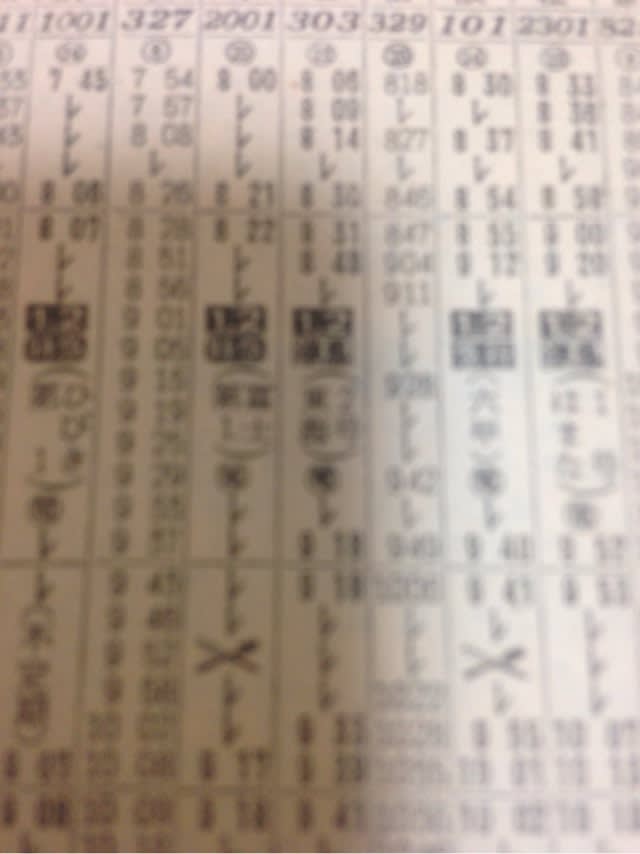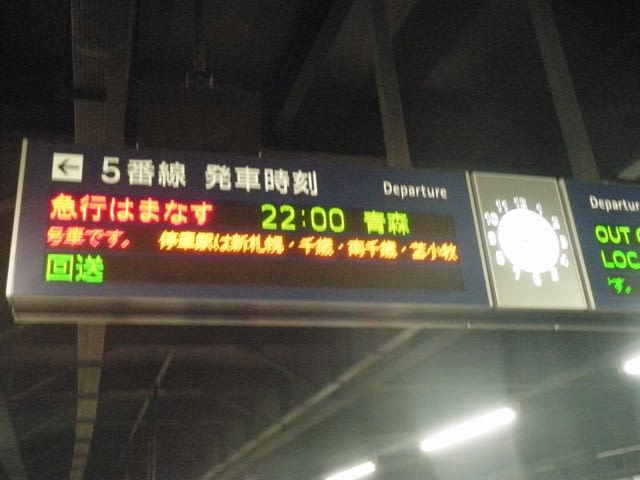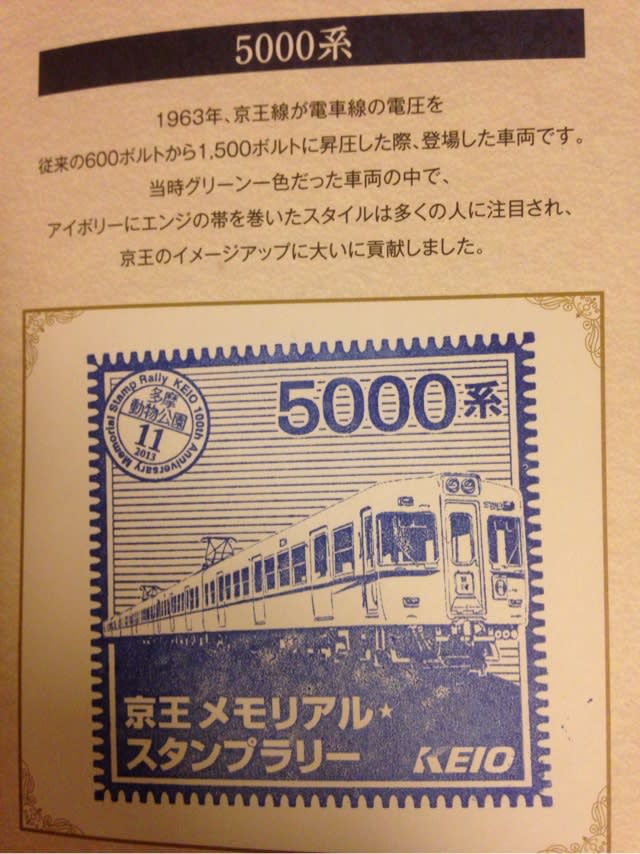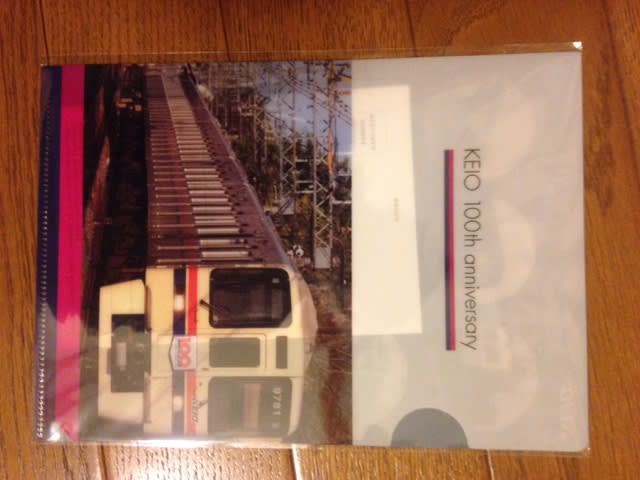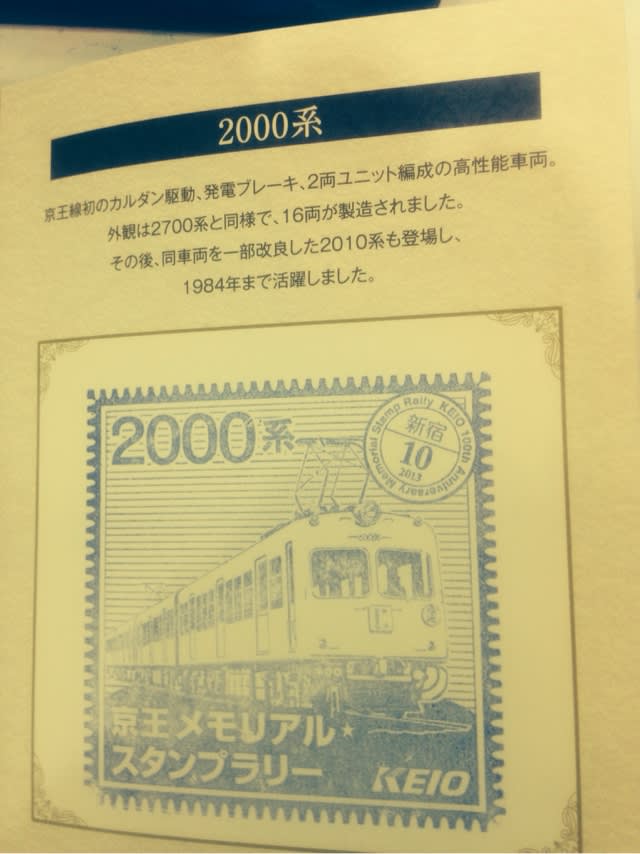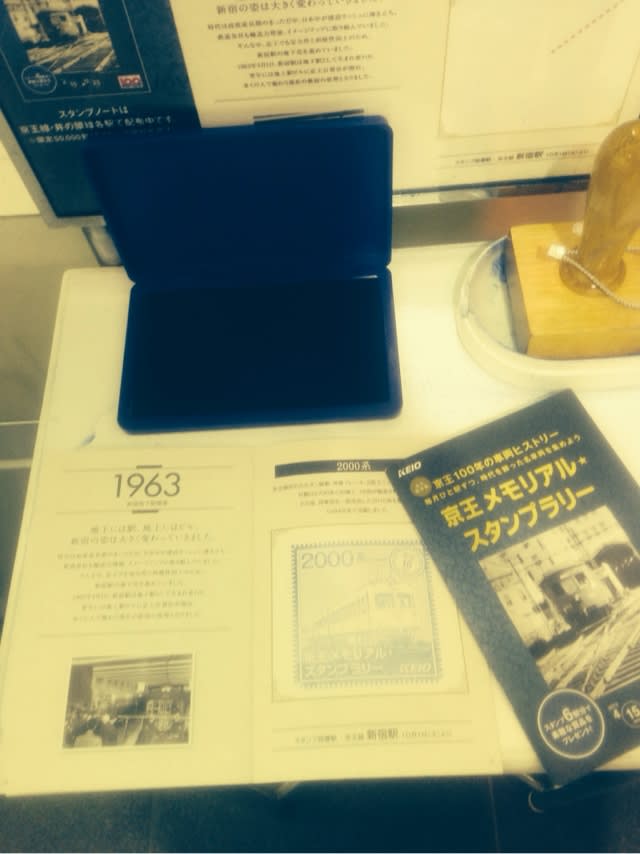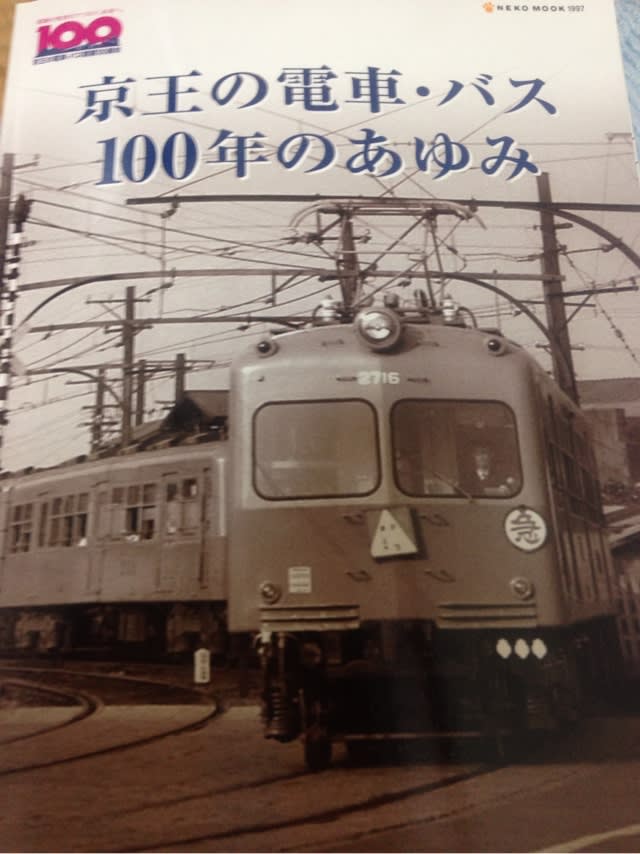鉄道シリーズ その17。北から徐々に降りてきた博物館シリーズだが、やはり神田須田町にあった交通博物館を抜きにしては語れない。この交通博物館は鉄道開通50周年を記念して東京駅近くに1921年10月14日にできたもので一旦、関東大震災で消失したが、1936年旧万世橋駅跡に新館として造られた。今の名前になったのは1948年で特色としては鉄道だけでなく徳川大尉が初めて日本で空を飛んだアンリ・ファルマンという飛行機や円太郎といわれたバスなども展示されていた。はじめてこの博物館を訪れたのは小学4年生のときだったように記憶している。詳細はあまり覚えていないが、今もある鉄道模型のジオラマがあまりに大きく色々な車両が走っていたことは覚えている。

入口にには弁慶号と新幹線の0系が仲良く並んでおり、中に入るといろいろな形の信号やスイッチバック、ループ線の仕組み、ブレーキや架線の役割など鉄道関係の事象を模型などで分かりやすく解説してあった。もちろん目を引いたのはいろいろな蒸気機関車C57、D51、9856号機関車、日本には走っていなかった巨大なマレー式機関車、客車は御料車や電車などとにかく鉄道関係があった1階だけで疲れてしまうくらいあった。2階や3階には鉄道以外は籠からトヨタのオート三輪、国鉄バスの第一号まで展示されていた。

最後に訪れたのは2006年2月。3月の閉館を前に旧万世橋駅ホームの公開の際に見学に行った。ちょうど今は万世橋エキュートとなっている所まで階段を上って行ったことが懐かしい。なお、博物館とホーム跡の位置関係は最後の写真のとおりである。当日は昼食に神田の藪で昼食を取ったがその店も火事で焼けてもうないことも寂しい。