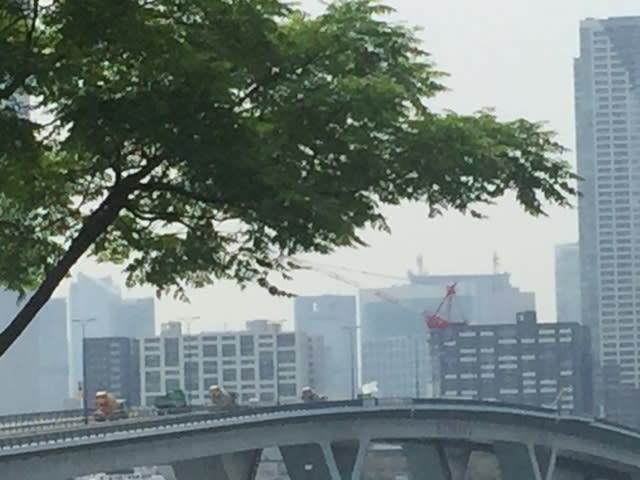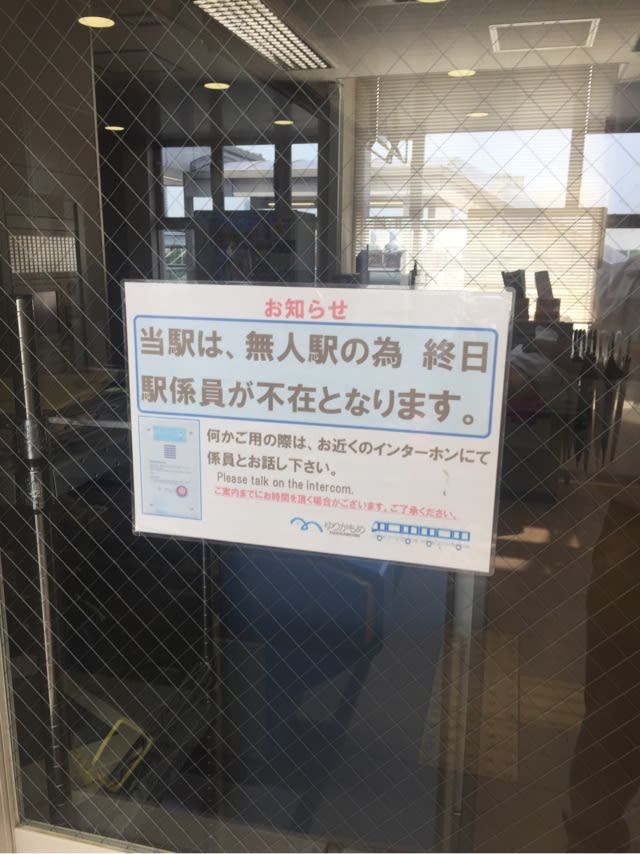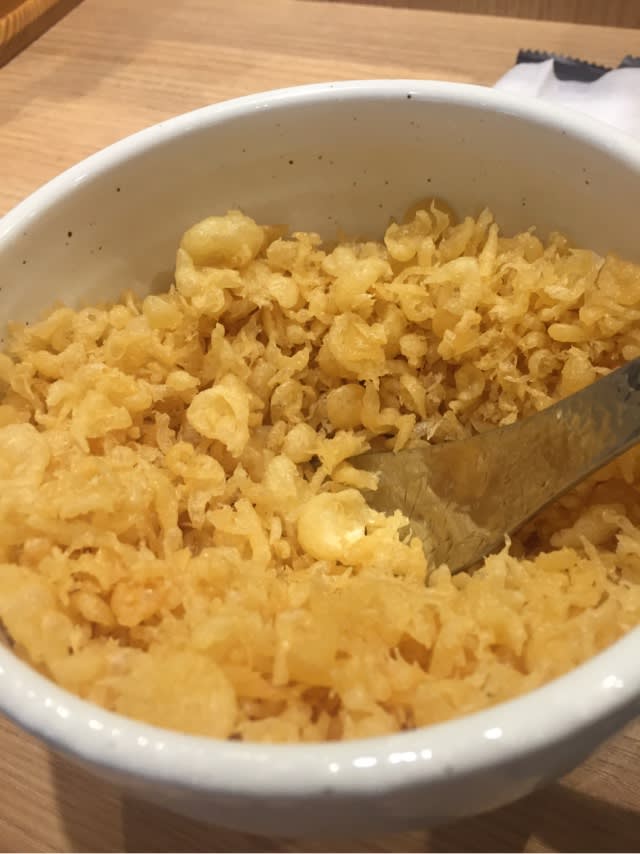『江戸城・皇居を巡る』その9。今回は江戸城から少し離れ、外濠を歩いて見る。江戸城のすぐ周りにあるのが内濠に対し、それを囲むように広がっていたのが外濠である。しかし、内濠はほぼ残されているのに対して、外濠は神田川のように川として残る以外は飯田橋〜四谷の3ヶ所(牛込濠、新見付濠、市ヶ谷濠)、赤坂見附付近(弁慶濠)を残すのみである。


今回はそのうち市ヶ谷濠を歩いて見る。JR四谷駅麹町口で降りて双葉学園の方に行く。


石垣がまだ残されているが、江戸時代にはここに四谷門があった。双葉学園の向かい側に石垣が二重になっているが、これが枡形門の櫓台の跡である。


跨線橋を渡り、外濠通りの手前を右に曲がると外濠公園の入口に出る。この公園こそ市ヶ谷濠の一部であり、今は埋められ濠の形はないが、外堀通りに比べ低くなっており、位置関係は残されている。


いまはアジサイが見頃で、また、反対側には遊具の向こうに総武線各停の線路があり、間近にレモンイエローの電車を見ることができる。

そして、グラウンドの横を抜けるとまた外堀通りに出る。


その先に残された市ヶ谷濠の端の部分があるが、夾竹桃が茂り、濠はよく見えない。かつてはこの辺りはボート場があったが、今は中華料理屋になっている。


市ヶ谷駅に向かうように左に曲がり、市ヶ谷橋を少し登ると市ヶ谷濠の全景がよく見える。ただ、その先端までは確認できず、市ヶ谷濠の先端を見るには車窓から眺めるしかないようである。