丹沢山塊の 日本百名山
日本百名山 である丹沢山
である丹沢山  (標高 1567m)へ。
(標高 1567m)へ。
塔ノ岳の山頂は見晴らし最高である。  南側には大きく広がる『相模湾』が目に入り、南東方向には『江の島』や『三浦半島』が見える。
南側には大きく広がる『相模湾』が目に入り、南東方向には『江の島』や『三浦半島』が見える。
 西には霊峰『富士山』、北側にはこれから目指す『丹沢山』そして『蛭ヶ岳』が眺められる。
西には霊峰『富士山』、北側にはこれから目指す『丹沢山』そして『蛭ヶ岳』が眺められる。

山頂の方位盤の回りには木製のベンチが沢山設置され、好きな景色を眺めながら休憩が取れる。

休んだら目的の『丹沢山』へ向かう。塔ノ岳 出発 11時20分。
出発 11時20分。
尊仏山荘の左側から北側に延びる縦走路に入って行く。

木製階段を下り、登り返して整備された木道を進むと日高に着く。通過 11時35分。

日高の先も平坦道や緩やかなアップダウンの登山道で、とても歩き易い。

もう時期が遅かったようだが、まだヤマザクラを見ることができた。

それと、これから本格的に咲き始めるシロヤシオ(ゴヨウツツジ)を発見、疲れている時に綺麗な花に迎えられると、疲れを忘れる。

この辺りの登山道の両脇はクマザサに覆われ、綺麗な山である。

鞍部に下り着き、ゆるい登りに差し掛かる所が竜ヶ馬場である。 通過 12時05分。
通過 12時05分。
 テーブルベンチが沢山あるので、爽やかな
テーブルベンチが沢山あるので、爽やかな  風に当たりながら休憩する
風に当たりながら休憩する のは最高です。 左手には大山が確認できます。
のは最高です。 左手には大山が確認できます。

竜ヶ馬場から先は、緩やかなアップダウンを過ぎ、ブナ林を登り詰めると目的の丹沢山に到着である。 
 しずくちゃん
しずくちゃん  形の丹沢山と記された石碑がむかえてくれた。到着 12時35分。
形の丹沢山と記された石碑がむかえてくれた。到着 12時35分。

- 誕生日
- 大昔からいます(年齢はヒミツ♪)
- 生まれたところ
- 丹沢の山奥
- 性別
- 女の子

- すきな食べ物
- おいしい水を使った食べ物
- 得意なこと
- 空を飛んで、山や川を見に行くこと
- お仕事
- かながわの水源環境を守るための取組を応援・PRすること
- きらいなもの
- 光の入らない暗い森、大好きな森を燃やしてしまう火

- 山頂からの展望は良くないが
 、広いのに驚いた。若い頃登ったことがあるけど、覚えている所は何もなかった。
、広いのに驚いた。若い頃登ったことがあるけど、覚えている所は何もなかった。 休憩と昼食を済ませた。
休憩と昼食を済ませた。 
山頂の東側には立派なみやま山荘  があり、トイレも設置され南寄りには1等三角点がある。
があり、トイレも設置され南寄りには1等三角点がある。

大倉 駐車場から塔ノ岳を経由して丹沢山までは、一寸厳しかったが
駐車場から塔ノ岳を経由して丹沢山までは、一寸厳しかったが  花に迎えられると頑張れる。
花に迎えられると頑張れる。

目的の山頂を散策して休憩もし、 お腹を満たし、13時05分 塔ノ岳に向け 出発 。
出発 。
13時20分、西側からガスが上がってきた。

竜ヶ馬場通過、13時25分。塔ノ岳が見えてきた。

塔ノ岳着、14時10分。ここからはラインがつながるので下山報告を送った。出発 14時半。

金冷シ通過、14時43分。 花立山荘通過、15時。 堀山の家 15時35分~45分。
駒止茶屋通過、15時56分。 見晴茶屋通過、16時24分。 観音茶屋通過、16時40分。
大倉駐車場着、17時05分。
※ 訪問、ありがとうございます。












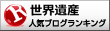


 鳳凰山
鳳凰山![[ザノースフェイス] ロングパンツ アルパインライトパンツ メンズ アーバンネイビー 日本 L (日本サイズ...](https://m.media-amazon.com/images/I/31Jmyqja4CL._SL160_.jpg)
 白根三山
白根三山 (北岳・間ノ岳・農鳥岳)の展望台である夜叉神峠に到着する。
(北岳・間ノ岳・農鳥岳)の展望台である夜叉神峠に到着する。

 夜叉神峠には小屋があり、小屋前は広場になっており、小休止
夜叉神峠には小屋があり、小屋前は広場になっており、小休止 しながら白根三山が眺められる。でも、この時は曇りで、野呂川の深い谷を隔てて対峙する白根三山を望むことは出来なかった。
しながら白根三山が眺められる。でも、この時は曇りで、野呂川の深い谷を隔てて対峙する白根三山を望むことは出来なかった。

 であれば北岳(標高 3192m)が望めるはずが、残念だった。
であれば北岳(標高 3192m)が望めるはずが、残念だった。
 山火事跡から緩い登りが始まり、シラビソの樹林帯に入り、
山火事跡から緩い登りが始まり、シラビソの樹林帯に入り、 右手より千頭星山からの登山道と合流し苺平に着く。
右手より千頭星山からの登山道と合流し苺平に着く。

 とした空気は気持ち良かった。 苺平からは辻山(標高
とした空気は気持ち良かった。 苺平からは辻山(標高  登山道が下りになって来ると、南御室小屋
登山道が下りになって来ると、南御室小屋
 清水
清水
 水場の有ることから、小屋周辺は樹海の中のオアシスといった感じで、西側の平坦地はキャンプ指定地になっており賑やかな所である。
水場の有ることから、小屋周辺は樹海の中のオアシスといった感じで、西側の平坦地はキャンプ指定地になっており賑やかな所である。

 花崗岩の大きな岩塊と白い砂礫の砂払岳に到着する。
花崗岩の大きな岩塊と白い砂礫の砂払岳に到着する。

 鳳凰三山
鳳凰三山

 砂払岳を下った鞍部にはダケカンバに囲まれた中に薬師岳小屋が迎えてくれる。
砂払岳を下った鞍部にはダケカンバに囲まれた中に薬師岳小屋が迎えてくれる。

 ガスっていましたが、晴れていれば白い砂礫が眩しく
ガスっていましたが、晴れていれば白い砂礫が眩しく 薬師岳から約50分ほどで、鳳凰三山の最高峰『観音岳』に到着です。
薬師岳から約50分ほどで、鳳凰三山の最高峰『観音岳』に到着です。
 カラマツやダケカンバが厳しい自然に耐え成長している光景がいたるところで見ることができる。
カラマツやダケカンバが厳しい自然に耐え成長している光景がいたるところで見ることができる。
 ワク
ワク ワク
ワク 稜線上からは右に甲府市街、正面には
稜線上からは右に甲府市街、正面には 赤抜沢ノ頭に立つと、
赤抜沢ノ頭に立つと、 目の前に
目の前に 石のお地蔵様が並ぶ賽ノ河原
石のお地蔵様が並ぶ賽ノ河原 に下り、見上げる地蔵ヶ岳は迫力満点である。
に下り、見上げる地蔵ヶ岳は迫力満点である。
 白ザレの鞍部まで下り、急斜面を登り二つ目のピークが高嶺山頂である。中央の雪渓は大樺沢で雲に隠れた中央のピークは北岳。
白ザレの鞍部まで下り、急斜面を登り二つ目のピークが高嶺山頂である。中央の雪渓は大樺沢で雲に隠れた中央のピークは北岳。 高嶺から先はダケカンバが点在する急斜面の露岩帯が続き、慎重に下れば、やがて傾斜も緩くなりハイマツ帯をジグザグに下れば白鳳峠である。
高嶺から先はダケカンバが点在する急斜面の露岩帯が続き、慎重に下れば、やがて傾斜も緩くなりハイマツ帯をジグザグに下れば白鳳峠である。








 ここからは槍沢が大きく開け、氷河地形であるU字谷の姿が良く観察できる。登山道は槍沢の左岸に沿って延び、お花畑を楽しみながら緩やかに
ここからは槍沢が大きく開け、氷河地形であるU字谷の姿が良く観察できる。登山道は槍沢の左岸に沿って延び、お花畑を楽しみながら緩やかに 槍ヶ岳へ槍沢のピストンではつまらないので、ヒュッテ西岳からの東鎌尾根の水俣乗越に向けての急登に取り付いた。
槍ヶ岳へ槍沢のピストンではつまらないので、ヒュッテ西岳からの東鎌尾根の水俣乗越に向けての急登に取り付いた。 尾根近くは急登で厳しかったが、ニッコウキスゲの群落に癒され頑張れた。
尾根近くは急登で厳しかったが、ニッコウキスゲの群落に癒され頑張れた。 」とホッとしたが、水俣乗越は西岳と槍ヶ岳を結ぶ尾根の最低鞍部であり、ここから槍に向けてもうひと頑張りである。
」とホッとしたが、水俣乗越は西岳と槍ヶ岳を結ぶ尾根の最低鞍部であり、ここから槍に向けてもうひと頑張りである。

 窓と呼ばれる鞍部へは木製階段を降り、その後 更に鉄ハシゴを下る。
窓と呼ばれる鞍部へは木製階段を降り、その後 更に鉄ハシゴを下る。
 ハシゴと太いクサリの続く岩場に来ると、以前 職場の仲間と共に通過する時、仲間の一人が恐怖心からだろうか
ハシゴと太いクサリの続く岩場に来ると、以前 職場の仲間と共に通過する時、仲間の一人が恐怖心からだろうか ハシゴの途中で上にも下にも動けなくなり
ハシゴの途中で上にも下にも動けなくなり 、皆で確保しながら通過した記憶がよみがえります。
、皆で確保しながら通過した記憶がよみがえります。 その時は必死でしたが、楽しい思い出です。
その時は必死でしたが、楽しい思い出です。
 ので遠望は利かない。なので一路槍ヶ岳を
ので遠望は利かない。なので一路槍ヶ岳を
 易くなっているので慎重に行動する。
易くなっているので慎重に行動する。



 山頂にひっそりと小祠が祀られている。この祠は雷を
山頂にひっそりと小祠が祀られている。この祠は雷を 避けるために釘は一本も使われていないそうです。
避けるために釘は一本も使われていないそうです。

 体を休め、翌日は大喰岳(3101m)から中岳(3084m)を通り南岳手前から天狗池に下り、槍沢コースを戻った。
体を休め、翌日は大喰岳(3101m)から中岳(3084m)を通り南岳手前から天狗池に下り、槍沢コースを戻った。 翌日は前日よりも
翌日は前日よりも




 石鎚登山ロープウェイからの表参道成就コースや
石鎚登山ロープウェイからの表参道成就コースや 石鎚スカイラインを利用した土小屋コース、
石鎚スカイラインを利用した土小屋コース、 面河渓
面河渓 堂ヶ森からの縦走コースなど個性豊かなコースがあります。
堂ヶ森からの縦走コースなど個性豊かなコースがあります。




 「アケボノツツジ」
「アケボノツツジ」













 花々が咲き競っています。
花々が咲き競っています。 ブナやダケカンバなど広葉樹林の中を緩やかに登って
ブナやダケカンバなど広葉樹林の中を緩やかに登って 以前は笹を切り開いた道で歩きにくかったが、今は木道が敷かれて、ずっと歩き易くなっている。
以前は笹を切り開いた道で歩きにくかったが、今は木道が敷かれて、ずっと歩き易くなっている。 視界が開けて原見岩(トカゲ岩)と呼ばれる大岩のある湿地状の一面にお花畑が広がっている。
視界が開けて原見岩(トカゲ岩)と呼ばれる大岩のある湿地状の一面にお花畑が広がっている。
 燧ケ岳や日光白根山などの日光
燧ケ岳や日光白根山などの日光 本来は尾瀬ヶ原や燧ケ岳の眺めが最高の場所であるが、この日は雲が低く薄っすらとしか見ることができず、非常に残念であった。
本来は尾瀬ヶ原や燧ケ岳の眺めが最高の場所であるが、この日は雲が低く薄っすらとしか見ることができず、非常に残念であった。



 7~8月は高山植物が咲き競い登山者の目を楽しませてくれるのだが
7~8月は高山植物が咲き競い登山者の目を楽しませてくれるのだが


 尾根の左側に下って登り返せば至仏山山頂に到着。鳩待峠から3時間50分でした。
尾根の左側に下って登り返せば至仏山山頂に到着。鳩待峠から3時間50分でした。
 山頂には、周りの山々の展望表示盤と二等三角点があり、さえぎる物が無く眺望は最高である。
山頂には、周りの山々の展望表示盤と二等三角点があり、さえぎる物が無く眺望は最高である。
![[モンベル] アウトドア ソックス メンズ 1129429 サンセットオレンジ 日本 L-(日本サイズL相当)](https://m.media-amazon.com/images/I/51A553pnNiL._SL160_.jpg)
 名山の名に恥じない高さと風格ある山姿は、どこから見ても、その名の通り笠の形をしている。
名山の名に恥じない高さと風格ある山姿は、どこから見ても、その名の通り笠の形をしている。
 槍穂高連峰の西側に並行するように稜線が延びており、縦走中は常に槍穂高連峰の大パノラマが楽しめます。
槍穂高連峰の西側に並行するように稜線が延びており、縦走中は常に槍穂高連峰の大パノラマが楽しめます。 稜線上には お花畑が点在し、途中には圏谷(カール)が見られ変化に富んだ、気持ちの良い山歩きが
稜線上には お花畑が点在し、途中には圏谷(カール)が見られ変化に富んだ、気持ちの良い山歩きが 弓折岳からは大ノマ岳との鞍部の大ノマ乗越を目指して、急な傾斜をジグザグに下り、下り着いた所が大ノマ乗越。
弓折岳からは大ノマ岳との鞍部の大ノマ乗越を目指して、急な傾斜をジグザグに下り、下り着いた所が大ノマ乗越。 大ノマ岳に向け急斜面に取り付くが、山頂まで登り切らず山頂直下の南側を巻いて進む。槍穂高連峰や黒部五郎岳、三俣蓮華岳の方から笠ヶ岳を望むと緩やかな稜線歩きで笠ヶ岳に行けそうに見えるが、イザ
大ノマ岳に向け急斜面に取り付くが、山頂まで登り切らず山頂直下の南側を巻いて進む。槍穂高連峰や黒部五郎岳、三俣蓮華岳の方から笠ヶ岳を望むと緩やかな稜線歩きで笠ヶ岳に行けそうに見えるが、イザ


 急登をジグザグに登りテント場に出て、更に石畳の登路を詰め山荘前のテラスに登り切れた時はホッ
急登をジグザグに登りテント場に出て、更に石畳の登路を詰め山荘前のテラスに登り切れた時はホッ
 独立峰の笠ヶ岳なのに登頂時は雲に覆われ、何も見えなかったことが非常に残念であった。
独立峰の笠ヶ岳なのに登頂時は雲に覆われ、何も見えなかったことが非常に残念であった。
 一気に標高差1600m強を下るので、皆さんの膝への負担を考慮しながら無事下山した。
一気に標高差1600m強を下るので、皆さんの膝への負担を考慮しながら無事下山した。




 ここはキャンプ指定地でもあり、水場やトイレがある。
ここはキャンプ指定地でもあり、水場やトイレがある。
 薬師平はハクサンイチゲやミヤマキンポウゲなどが咲くお花畑に木道が伸びている。
薬師平はハクサンイチゲやミヤマキンポウゲなどが咲くお花畑に木道が伸びている。 愛知大学の遭難碑があるあたりから、登山道は左に折れて、ハイマツ帯の尾根東側の小さな窪地を緩やかに登って行く。
愛知大学の遭難碑があるあたりから、登山道は左に折れて、ハイマツ帯の尾根東側の小さな窪地を緩やかに登って行く。 やがて薬師岳への尾根に向けて登りとなり、稜線に出ると前方に立派な薬師岳山荘が目に飛び込む。
やがて薬師岳への尾根に向けて登りとなり、稜線に出ると前方に立派な薬師岳山荘が目に飛び込む。
 稜線の西側斜面から避難小屋跡の見えるピークに向けて巻きながら登って行くと東南尾根と合流する稜線に出る。
稜線の西側斜面から避難小屋跡の見えるピークに向けて巻きながら登って行くと東南尾根と合流する稜線に出る。 大ケルンと避難小屋跡の建つ稜線に出て、左へ進路を取ると間もなく薬師岳山頂に到着。
大ケルンと避難小屋跡の建つ稜線に出て、左へ進路を取ると間もなく薬師岳山頂に到着。 避難小屋跡から山頂付近は尾根幅が広く、悪天候時の下りでは主稜線を間違えないよう、夏であろうとも十分な注意が必要であります。
避難小屋跡から山頂付近は尾根幅が広く、悪天候時の下りでは主稜線を間違えないよう、夏であろうとも十分な注意が必要であります。 頂上からは北アルプスを一望する大展望が得られる予定でしたが、この日は
頂上からは北アルプスを一望する大展望が得られる予定でしたが、この日は
 この半埦状の圏谷群は洪積世(氷河時代)の氷河の作用で形成されたもので、日本アルプスの圏谷の中でもっとも、その形態が見事な氷河遺跡であるとの事であります。
この半埦状の圏谷群は洪積世(氷河時代)の氷河の作用で形成されたもので、日本アルプスの圏谷の中でもっとも、その形態が見事な氷河遺跡であるとの事であります。




 要所、要所には鎖や鉄梯子が設置され、慎重に歩を
要所、要所には鎖や鉄梯子が設置され、慎重に歩を

 吊り尾根自体はそう難しい箇所は有りませんが、岳沢側の急斜面に沿った道であり、ここまでの疲労度に応じては、慎重な歩運びが求められます。 吊り尾根から見た左:前穂、右の2つのピークは明神岳
吊り尾根自体はそう難しい箇所は有りませんが、岳沢側の急斜面に沿った道であり、ここまでの疲労度に応じては、慎重な歩運びが求められます。 吊り尾根から見た左:前穂、右の2つのピークは明神岳  上高地側の景色は最高ですが、足元から目を逸らすことは出来ません。
上高地側の景色は最高ですが、足元から目を逸らすことは出来ません。
 南陵ノ頭から槍ヶ岳(標高 3180m
南陵ノ頭から槍ヶ岳(標高 3180m 南陵ノ頭に抜ける鎖場を慎重に越えると、岩屑がなだらかに積みあがった様な奥穂の頂稜部に出る。その先に祠や方位盤のある山頂が目の前に聳える。
南陵ノ頭に抜ける鎖場を慎重に越えると、岩屑がなだらかに積みあがった様な奥穂の頂稜部に出る。その先に祠や方位盤のある山頂が目の前に聳える。 頑張って奥穂高岳山頂を踏んだのは、上高地を出発し休憩を含めて9時間50分後であった。 山頂の方位盤
頑張って奥穂高岳山頂を踏んだのは、上高地を出発し休憩を含めて9時間50分後であった。 山頂の方位盤 








 温泉のマイクロバスで、宿から1時間半、中ノ岐林道を走って頂き、標高 1270mの平ヶ岳中ノ岐登山口まで入って頂いた。
温泉のマイクロバスで、宿から1時間半、中ノ岐林道を走って頂き、標高 1270mの平ヶ岳中ノ岐登山口まで入って頂いた。

 登山口を5時35分に
登山口を5時35分に 、乗鞍岳、四阿山、黒部五郎岳、富士山など、皆さん元気に歩かれました。
、乗鞍岳、四阿山、黒部五郎岳、富士山など、皆さん元気に歩かれました。
 灌木と岩稜とハイマツ帯を過ぎオオシラビソの林を抜けると、池ノ岳の平坦な頂上部にある、姫ノ池の地塘群が現れる。
灌木と岩稜とハイマツ帯を過ぎオオシラビソの林を抜けると、池ノ岳の平坦な頂上部にある、姫ノ池の地塘群が現れる。 付近には湿原が広がり、キンコウカ
付近には湿原が広がり、キンコウカ そして、湿原越しに雄大な平ヶ岳の本峰が、直ぐ目の前に望める。
そして、湿原越しに雄大な平ヶ岳の本峰が、直ぐ目の前に望める。
 山頂西側の湿原には池塘が点在し、剱ヶ倉山方面へ木道は続くが行き止まりであり、その周辺にはチングルマが咲き誇り、360度の展望が楽しめる。
山頂西側の湿原には池塘が点在し、剱ヶ倉山方面へ木道は続くが行き止まりであり、その周辺にはチングルマが咲き誇り、360度の展望が楽しめる。



 《焼岳》
《焼岳》 である《焼岳》の、ご紹介です。
である《焼岳》の、ご紹介です。 その後も1925年、1962年に噴火を
その後も1925年、1962年に噴火を 規制緩和がされた後、深田久弥の日本百名山ブームにより、登山者は増加傾向にあり、
規制緩和がされた後、深田久弥の日本百名山ブームにより、登山者は増加傾向にあり、 が続いており、温泉旅館側からの新中ノ湯ルートを登りました。
が続いており、温泉旅館側からの新中ノ湯ルートを登りました。 青空に噴き上げる真っ白な噴煙が確認でき、双耳峰である南峰と北峰の中間鞍部を目指す。
青空に噴き上げる真っ白な噴煙が確認でき、双耳峰である南峰と北峰の中間鞍部を目指す。 だが、またいつ火山活動を再開するとも限らず、皆さんで声を掛け合い噴煙直下は足早に
だが、またいつ火山活動を再開するとも限らず、皆さんで声を掛け合い噴煙直下は足早に 通過した。 稜線歩きをしていると、遠く穂高連峰が目に飛び込んで来た。
通過した。 稜線歩きをしていると、遠く穂高連峰が目に飛び込んで来た。 山頂付近は危険区域となっており、現在も南峰や火口湖および噴気孔近くは立ち入り禁止となっています。
山頂付近は危険区域となっており、現在も南峰や火口湖および噴気孔近くは立ち入り禁止となっています。 火山岩に記された丸印をたどると、道はいよいよ活火山の道らしくなり、硫黄の臭気が強くなる。
火山岩に記された丸印をたどると、道はいよいよ活火山の道らしくなり、硫黄の臭気が強くなる。

 下りは焼岳小屋に向けて、まず中尾峠を目指す。
下りは焼岳小屋に向けて、まず中尾峠を目指す。 眼下に緑
眼下に緑 が見えてくると、大きな岩からザラザラした砂礫の道に変わり、中尾峠近しである。
が見えてくると、大きな岩からザラザラした砂礫の道に変わり、中尾峠近しである。 中尾峠では、飛騨側の中尾
中尾峠では、飛騨側の中尾 落石の発生しそうな
落石の発生しそうな




