軍事依存経済 宇宙編⑪ 星空守る研究者・市民
日本の宇宙技術は30年前にも米国から狙われたことがあります。レーガン大統領が1983年に打ち出した「戦略防衛構想」(SDI構想)への動員です。
宇宙に迎撃兵器を配備し、敵国が発射した核ミサイルを撃ち落とす―。「スターウォーズ計画」と呼ばれた同構想は、核の戦場を宇宙空間まで広げるものでした。
長野県の東京大学東京天文台(現・国立天文台)野辺山宇宙電波観測所に86年、1通の研究会の案内が届きます。案内状には研究会のスポンサーとして米航空宇宙局(NASA)と並んで米国防総省SDI局の名前が書かれていました。
野辺山には82年にミリ波観測で世界最大となる45メートルの電波望遠鏡が完成。原始星をとりまく回転ガス円盤や新星間分子の発見など、画期的な成果を次々とあげていました。それが米軍の目にとまったのです。
SDl反対の会
研究会のテーマは波長が1ミリ以下の電波(サブミリ波)を観測する受信機の開発でした。サブミリ波による観測が実現すれば、観測精度を高めることができます。同時に、SDIが必要とする敵国のミサイル発射検出にも有効な技術でした。
対応をめぐり天文台で熱い討論が繰り返されました。そのなかから87年、「SDIに反対する天文学研究者の会」が発足します。事務局を務めた国立天文台の御子柴廣(みこしば・ひろし)研究技師は「サブミリ波は魅力的な研究テーマだったが、一度でも軍と関係を持てばどんどん深みにはまっていく。何度も議論し危険性を伝えていこうとなった」と振り返ります。
主に日本天文学会会員の研究者を対象としたSDI反対署名には4カ月で510人が署名しました。当時の同学会の特別会員(主に研究者)数は604人。日本の天文学者の約8割が賛同したのです。88年の東京天文台から国立天文台への改組の際には、有志によって「国立天文台職員の私たちは、一切の軍事研究に協力してはなりません」との声明が発表され、職員156人が賛同しました。

愛用の望遠鏡の前でSDI反対署名を手にする本田実さん=1989年10月17日(「星尋山荘」ホームページから)
「孤立させない」
研究者の運動に市民が応えます。同年、天文愛好家らが市民向けにSDI反対署名を開始。署名用紙の背景には銀河の写真を配し、すい星発見者として世界的に知られた本田実氏(1913~90年)はじめ著名アマチュア天文家の顔写真が並びました。天文ファンに共感が広がり、最終的に約1万2000人分が国連へ送られました。
「天文学者を孤立させてはいけないという思いだった。署名には国内の名だたる望遠鏡メーカーの社長の名前もずらりと並んだ」
当時、運動の中心となった「岡山☆星空を愛する会」の大野智久さん(67)は、反響の大きさを語ります。
93年、国立天文台野辺山宇宙電波観測所は「観測装置共同利用における軍事研究排除の方針」を決定します。研究者と市民の共同が、国立天文台を組織として軍事研究禁止をうたうところまで進めたのです。
米国は同年、SDI構想の放棄を表明します。しかし、構想の一部はミサイル防衛(MD)の形で引き継がれるなど、宇宙の軍事化は続いています。NPO日本スペースガード協会が岡山県で実施している小惑星の観測に米軍が注目し、データ提供を求めるなど、その波は民間にも及んでいます。
大野さんは、宇宙の軍事化に危機感を抱くとともに、SDI反対で示された研究者と市民の共同が改めて輝きを増していると強調します。新しい星の発見に生涯をかけた本田さんの言葉に、天文愛好家の願いが凝縮されていると訴えます。
「私たちは、何万年も何千年もかけてたったいま届いたばかりの星の光を見ている。そんな宇宙を汚しちゃいけない。私は、なにものにもじゃまされずに星を見続けていたいだけなんです」
(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2016年2月24日付掲載
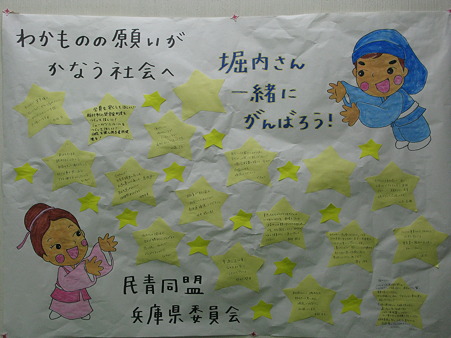
青年の願いを堀内さんへ_01 posted by (C)きんちゃん
「星に願いを」じゃありませんが…。
宇宙を軍事産業の場にしないために、地道な闘いがありました。闘いはこれからも続きます。
日本の宇宙技術は30年前にも米国から狙われたことがあります。レーガン大統領が1983年に打ち出した「戦略防衛構想」(SDI構想)への動員です。
宇宙に迎撃兵器を配備し、敵国が発射した核ミサイルを撃ち落とす―。「スターウォーズ計画」と呼ばれた同構想は、核の戦場を宇宙空間まで広げるものでした。
長野県の東京大学東京天文台(現・国立天文台)野辺山宇宙電波観測所に86年、1通の研究会の案内が届きます。案内状には研究会のスポンサーとして米航空宇宙局(NASA)と並んで米国防総省SDI局の名前が書かれていました。
野辺山には82年にミリ波観測で世界最大となる45メートルの電波望遠鏡が完成。原始星をとりまく回転ガス円盤や新星間分子の発見など、画期的な成果を次々とあげていました。それが米軍の目にとまったのです。
SDl反対の会
研究会のテーマは波長が1ミリ以下の電波(サブミリ波)を観測する受信機の開発でした。サブミリ波による観測が実現すれば、観測精度を高めることができます。同時に、SDIが必要とする敵国のミサイル発射検出にも有効な技術でした。
対応をめぐり天文台で熱い討論が繰り返されました。そのなかから87年、「SDIに反対する天文学研究者の会」が発足します。事務局を務めた国立天文台の御子柴廣(みこしば・ひろし)研究技師は「サブミリ波は魅力的な研究テーマだったが、一度でも軍と関係を持てばどんどん深みにはまっていく。何度も議論し危険性を伝えていこうとなった」と振り返ります。
主に日本天文学会会員の研究者を対象としたSDI反対署名には4カ月で510人が署名しました。当時の同学会の特別会員(主に研究者)数は604人。日本の天文学者の約8割が賛同したのです。88年の東京天文台から国立天文台への改組の際には、有志によって「国立天文台職員の私たちは、一切の軍事研究に協力してはなりません」との声明が発表され、職員156人が賛同しました。

愛用の望遠鏡の前でSDI反対署名を手にする本田実さん=1989年10月17日(「星尋山荘」ホームページから)
「孤立させない」
研究者の運動に市民が応えます。同年、天文愛好家らが市民向けにSDI反対署名を開始。署名用紙の背景には銀河の写真を配し、すい星発見者として世界的に知られた本田実氏(1913~90年)はじめ著名アマチュア天文家の顔写真が並びました。天文ファンに共感が広がり、最終的に約1万2000人分が国連へ送られました。
「天文学者を孤立させてはいけないという思いだった。署名には国内の名だたる望遠鏡メーカーの社長の名前もずらりと並んだ」
当時、運動の中心となった「岡山☆星空を愛する会」の大野智久さん(67)は、反響の大きさを語ります。
93年、国立天文台野辺山宇宙電波観測所は「観測装置共同利用における軍事研究排除の方針」を決定します。研究者と市民の共同が、国立天文台を組織として軍事研究禁止をうたうところまで進めたのです。
米国は同年、SDI構想の放棄を表明します。しかし、構想の一部はミサイル防衛(MD)の形で引き継がれるなど、宇宙の軍事化は続いています。NPO日本スペースガード協会が岡山県で実施している小惑星の観測に米軍が注目し、データ提供を求めるなど、その波は民間にも及んでいます。
大野さんは、宇宙の軍事化に危機感を抱くとともに、SDI反対で示された研究者と市民の共同が改めて輝きを増していると強調します。新しい星の発見に生涯をかけた本田さんの言葉に、天文愛好家の願いが凝縮されていると訴えます。
「私たちは、何万年も何千年もかけてたったいま届いたばかりの星の光を見ている。そんな宇宙を汚しちゃいけない。私は、なにものにもじゃまされずに星を見続けていたいだけなんです」
(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2016年2月24日付掲載
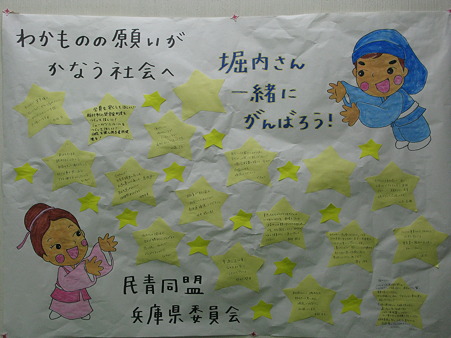
青年の願いを堀内さんへ_01 posted by (C)きんちゃん
「星に願いを」じゃありませんが…。
宇宙を軍事産業の場にしないために、地道な闘いがありました。闘いはこれからも続きます。











