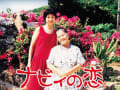キルメン・ウリベ「ムシェ 小さな英雄の物語」(金子奈美訳、白水社、2015、2300円)という本を読んだ。大変感動的な本で、多分知らない人が多いと思うから書いておきたい。新聞の書評で気になって買ったんだけど、自分でも買ったまま忘れていた。年末に部屋を整理したら出てきて、この本は何だっけと思った。最近は単行本はあまり買わないけど、2千円を超えるけど買ってて良かったと思った。

キルメン・ウリベ(1970~)と言われても、知らない人にはどこの国の人だか見当もつかないと思う。アフリカのどこかの国、あるいは中東や東欧の小国だと言われたら信じてしまいそうだ。著者は国籍で言えばスペインになる。でも北東部に自治州を持つバスク人なのである。いま、スペインでも非常に注目される詩人、小説家だそうで、2008年に出た「ビルバオ-ニューヨーク-ビルバオ」が評判を呼び、日本でも翻訳された。今回の「ムシェ 小さな英雄の物語」は2012年の作品で、世界で広く読まれているという。日本で初めてバスク語から直接翻訳された本だという話。
話はスペイン内戦時代のビルバオ(バスク州の州都)に始まる。共和国時代に自治権を獲得したバスクは、フランコ反乱軍に攻め込まれる。ドイツの爆撃で知られるゲルニカもバスクだった。ビルバオで孤立する州政府は、子どもたちを外国に疎開させることを決意する。こうして多くの子どもたちが、内戦下のビルバオを逃れてヨーロッパ各地に渡った。この物語は、その国際疎開を題材にした歴史秘話であり、受け入れたベルギーの「小さな英雄」に対する紙碑である。
ベルギー西北部にあるヘントに生きる若者、ロベール・ムシェがこの物語の主人公である。この本は歴史ノンフィクションなのか、それとも小説なのか、最初はよく判らないんだけど、基本的なストーリイは歴史的事実である。でも、小説として書かれていて、作者は登場人物の心の中を語っている。歴史小説では、信長や信玄が自分の感情を語ったりするが、それと同じかなと思う。でも、作者自身も中に登場したりしていて、なかなか新しい小説のあり方を追求している。
ロベールには親友のヘルマンがいる。しかし、ロベールは貧しい生まれで、高校の途中で父が倒れて学業を中断しなければならない。ロベールはのちに社会主義者となり、スペイン内戦に新聞から派遣され、ヘミングウェイやマルローとあったこともある。そんなロベールは、若いけど疎開児童を引き取り、カルメンチュがやってくる。二人の心の交流が生まれるが、やがてフランコ政府は疎開児童をスペインに戻すことにする。第二次大戦を間近にして、カルメンチュは帰っていく。
その後のロベール、そしてヘルマンはどうなったか。ロベールには一人娘がいて、カルメンチュの思い出にちなんでカルメンと名付けられた少女は、母の遺した父に関するさまざまの書類を大切に取っている。それをもとにして、ロベールの人生を追跡するのが、この本ということになる。話は入り組んでいるんだけど、ロベールとヘルマンの友情と断絶、ロベールの戦傷と結婚、戦時下の抵抗と逮捕、ドイツの収容所での日々…と続いていく。一体、ロベールの運命はどうなっていくのだろうか。これから読む人のために、それは書かないことにする。とっても心に響く「小さな英雄」の物語が、そこにあった。
第二次世界大戦に関して、多くの本が書かれている。ナチス・ドイツの行ったことは、今でも振り返られている。日本でも何本もの映画が公開されている。ヨーロッパではむしろ、いまこそ振り返ろうとしているのに対して、日本では歴史への無知を恥ずかしがらない風潮さえある。そんな日本の中で、この小さな物語はどれほど読まれることだろう。地元の図書館にもあるのではないかと思うから、ぜひ読んで見て欲しい。歴史の大きなデッサンばかりではなく、実際に生き社会を支えている「小さな英雄」こそ、われわれが「発見」しないといけない。そんな感動本である。
最後にちょっと、バスク人について。今でも「謎の民族」と言われ、周囲を隔絶した言語を話すとされるバスク人。ピレネー山脈の両側に渡り、スペイン、フランスに居住している。今ではインド・ヨーロッパ語系の人々が移動してい来る以前の、原ヨーロッパ人の文化を受け継ぐ人々ではないかと言われているらしい。イエズス会を作ったロヨラとザビエルがバスク人だということは有名だけど、ウィキペディアを見ると南米に多くのバスク系の人々がいる。なんとチェ・ゲバラとエバ・ペロンはバスク系アルゼンチン人。チリで社会主義政権を率いたアジェンデ、それをクーデタで倒したピノチェト、クーデタ直後に亡くなったノーベル文学賞詩人のネルーダ。3人ともにバスク系チリ人として掲載されているのには驚いた。

キルメン・ウリベ(1970~)と言われても、知らない人にはどこの国の人だか見当もつかないと思う。アフリカのどこかの国、あるいは中東や東欧の小国だと言われたら信じてしまいそうだ。著者は国籍で言えばスペインになる。でも北東部に自治州を持つバスク人なのである。いま、スペインでも非常に注目される詩人、小説家だそうで、2008年に出た「ビルバオ-ニューヨーク-ビルバオ」が評判を呼び、日本でも翻訳された。今回の「ムシェ 小さな英雄の物語」は2012年の作品で、世界で広く読まれているという。日本で初めてバスク語から直接翻訳された本だという話。
話はスペイン内戦時代のビルバオ(バスク州の州都)に始まる。共和国時代に自治権を獲得したバスクは、フランコ反乱軍に攻め込まれる。ドイツの爆撃で知られるゲルニカもバスクだった。ビルバオで孤立する州政府は、子どもたちを外国に疎開させることを決意する。こうして多くの子どもたちが、内戦下のビルバオを逃れてヨーロッパ各地に渡った。この物語は、その国際疎開を題材にした歴史秘話であり、受け入れたベルギーの「小さな英雄」に対する紙碑である。
ベルギー西北部にあるヘントに生きる若者、ロベール・ムシェがこの物語の主人公である。この本は歴史ノンフィクションなのか、それとも小説なのか、最初はよく判らないんだけど、基本的なストーリイは歴史的事実である。でも、小説として書かれていて、作者は登場人物の心の中を語っている。歴史小説では、信長や信玄が自分の感情を語ったりするが、それと同じかなと思う。でも、作者自身も中に登場したりしていて、なかなか新しい小説のあり方を追求している。
ロベールには親友のヘルマンがいる。しかし、ロベールは貧しい生まれで、高校の途中で父が倒れて学業を中断しなければならない。ロベールはのちに社会主義者となり、スペイン内戦に新聞から派遣され、ヘミングウェイやマルローとあったこともある。そんなロベールは、若いけど疎開児童を引き取り、カルメンチュがやってくる。二人の心の交流が生まれるが、やがてフランコ政府は疎開児童をスペインに戻すことにする。第二次大戦を間近にして、カルメンチュは帰っていく。
その後のロベール、そしてヘルマンはどうなったか。ロベールには一人娘がいて、カルメンチュの思い出にちなんでカルメンと名付けられた少女は、母の遺した父に関するさまざまの書類を大切に取っている。それをもとにして、ロベールの人生を追跡するのが、この本ということになる。話は入り組んでいるんだけど、ロベールとヘルマンの友情と断絶、ロベールの戦傷と結婚、戦時下の抵抗と逮捕、ドイツの収容所での日々…と続いていく。一体、ロベールの運命はどうなっていくのだろうか。これから読む人のために、それは書かないことにする。とっても心に響く「小さな英雄」の物語が、そこにあった。
第二次世界大戦に関して、多くの本が書かれている。ナチス・ドイツの行ったことは、今でも振り返られている。日本でも何本もの映画が公開されている。ヨーロッパではむしろ、いまこそ振り返ろうとしているのに対して、日本では歴史への無知を恥ずかしがらない風潮さえある。そんな日本の中で、この小さな物語はどれほど読まれることだろう。地元の図書館にもあるのではないかと思うから、ぜひ読んで見て欲しい。歴史の大きなデッサンばかりではなく、実際に生き社会を支えている「小さな英雄」こそ、われわれが「発見」しないといけない。そんな感動本である。
最後にちょっと、バスク人について。今でも「謎の民族」と言われ、周囲を隔絶した言語を話すとされるバスク人。ピレネー山脈の両側に渡り、スペイン、フランスに居住している。今ではインド・ヨーロッパ語系の人々が移動してい来る以前の、原ヨーロッパ人の文化を受け継ぐ人々ではないかと言われているらしい。イエズス会を作ったロヨラとザビエルがバスク人だということは有名だけど、ウィキペディアを見ると南米に多くのバスク系の人々がいる。なんとチェ・ゲバラとエバ・ペロンはバスク系アルゼンチン人。チリで社会主義政権を率いたアジェンデ、それをクーデタで倒したピノチェト、クーデタ直後に亡くなったノーベル文学賞詩人のネルーダ。3人ともにバスク系チリ人として掲載されているのには驚いた。