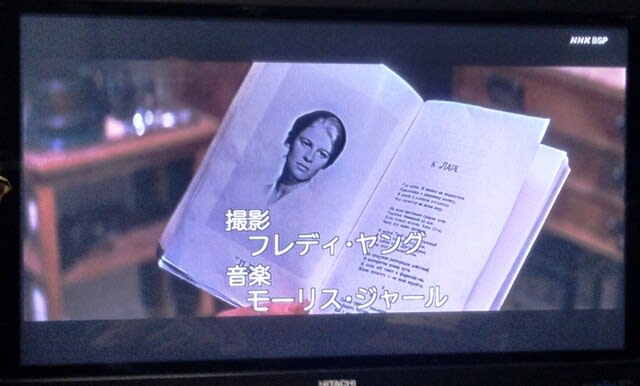2021年3月30日、映画『騙し絵の牙』(松竹、2021年)を見てきた。
TージョイSEIBU大泉シネマ。
練馬区の高齢者生き生き健康券(?)というのの期限が3月31日までだったので、慌てて出かけた。65歳以上の練馬区民なら、年間映画を3本まで1000円引きで見ることができる。今回はシニア1200円のところを200円で見ることができた。
この1年間で、『82年生れ キム・ジヨン』というのと、芦田愛菜の『星の子』を見たのだが、その後はあえて見たい映画がなくて困っていたのだが、先週末から『騙し絵の牙』が上映されることになり、出版社が舞台のドラマだというので、元編集者のぼくとしては、ようやく食指を動かされる映画に出会うことができた。

舞台は、老舗の文芸書出版社の編集部。100年の歴史を誇るオーナー経営の出版社という設定だから、モデルは講談社か新潮社といったところか。先代社長の御曹司が「これたかさん」=惟高さん(?)というあたりは講談社を思わせる。
他社の雑誌編集部から、この会社にやってきた情報誌の編集長(大泉洋)と、部下の若い編集者(松岡茉優)が主人公。松岡は、同社お抱えの作家(国村隼。モデルは誰だろう、彼かな?)の不興を買って文芸誌から情報誌の編集部に異動させられる。しかし、新人作家を見抜く眼力を大泉に認められれて活躍するのだが、やがて社内抗争に巻き込まれてゆく・・・、といったストーリー。
出版社というか出版業界の内幕ものとしては、筒井康隆の『大いなる助走』のほうがはるかにリアリティもあって、ぼくには面白かった。編集会議における作品や作家をめぐる議論なども、『大いなる助走』に比べれば浅いが、この映画のよいところはアクションが多く、展開のテンポがよいところ。2時間弱を飽きさせなかった。
ただし年寄りにはBGMの音楽がうるさかった。音楽といえば、ピアノの新垣隆も出ていた。ぼくはこのピアニストのキャラが好きである。「交響曲広島」騒動は売名行為かと思ったが、まったくそうではなかった。
松岡茉優という俳優はテレビのCMでしか見たことがなく、期待もしていなかったが、まずまずの演技を見せていた。大泉洋や佐藤浩市らのエキセントリックな演技に合わせて、テンション高く青臭い役柄を演じていた。

ぼくが月刊誌の編集者時代に毎月2、3日間、時には徹夜で出張校正に出向いた板橋、小豆沢の凸版印刷の倉庫が映っていて、懐かしかった。
ぼくが編集者をやっていた1970年代当時は、ゲラの出るのが遅かったり、印刷所の担当者とトラぶったり、遅筆の筆者の原稿が出張校正ぎりぎりまで入らなかったりで、毎月やきもきさせられたのだが、今となれば懐かしい。
まだ活版印刷の時代だった。植字工の人が活字を拾って組む現場を、凸版の近くの東洋印刷に見学に行ったりもした。弁当箱のような木箱に、左右逆向きの活字を一本ずつ詰めていく作業である。改行が必要になる加筆などされようものなら、改めて詰め替えなければならない。
あまり頻繁にゲラ刷りに大幅な加筆をする筆者に、いかに作業現場が大変か知ってもらうために、印刷所に連れて行き、現場を見てもらったこともある。それでもその先生はまったく反省することなく、その後も校正刷りに加筆をしつづけた。現在ではどんなに加筆されても、パソコンで簡単に行送りができるようになったが、植字の仕事はもう廃れてしまっただろう。今でも活字で組版をやっている印刷所はあるのだろうか。
松岡の実家は、武蔵小金井で高野書店という昔ながらの小さな書店を経営している。この小さな書店の娘が主人公という設定もよかった。
ぼくは現役の教師時代、週に1日、クルマで川崎市にあるキャンパスに通っていたが、途中の京王線布田駅のすぐ西の踏切を渡らなければならなかった。今では線路は地下化されて踏切はなくなったが、当時の京王線の踏切は朝の通勤時間帯は開かずの踏切で、いつもイライラさせられた。
ある雨の朝、その布田駅踏切の北側で、いつものように踏切待ちで停車していたときのことである。
道路沿いに間口一軒ほどの小さな書店があったのだが、黄色のレインコートを着た2、3歳くらいの女の子が、傘をさした母親に手を引かれてやってきて、書店の店頭に置かれた「めばえ」か何かを買ってもらって、お母さんに手を引かれて雨の歩道を甲州街道の方に遠ざかって行った。開かずの踏切に苛立っていたのだが、いい光景を見たことで気持ちが和んだ。
その後、その書店は閉店してしまい、閉じられたシャッターに閉店の挨拶が貼られたままになっていた。通るたびに寂しい思いがした。あの女の子も小学校高学年か中学生くらいになっただろう。本好きの女の子になっただろうか。今はどこで本を買っているのだろうか。
大泉と松岡の会話の中で、出版社の近くにかつては銭湯があったと語っているシーンがあった。ぼくが務めていた信濃町(地番は左門町)の小さな出版社の近くにも銭湯があり、ゲラが出ないで待たされている夕方に、風呂に行く編集者もいた。
あのシーンの意味は何なのだろう。松岡が銭湯があったことを覚えているエピソードが編集でカットされたのだろうか。
ぼくが元編集者だったことを割り引いても、この映画は面白かった。
高齢者生き生き健康券で見た3本の映画のなかでは一番良かったし、それ以外に見た「パラサイト」や、数年前に見た山田洋次の「小さなお家」や、家族を描いた最近の映画よりもよかった。
個人的には、徹底的に「活字」にこだわり、「本」にこだわり、小さな「書店」にこだわってほしかった。出版社もあんな現代的な本社ビルをもつ会社ではなく、小津安二郎の映画に出てきそうな、小さくて古びた社屋の出版社だとよかったが、残念ながらそういう方向では描いてくれなかった。
でも、現在の出版社はあんなことになっているのだろう。部数が何ぼ、広告料収入が何ぼ、の世界、書店ではなくamazonなどネットでの販売が主流となり、大泉のような編集者が跋扈する業界。文芸誌編集長の佐野史郎を戯画化して演出するあたりに、部数を出した情報誌の編集長側に立った脚本家、監督の立ち位置が窺える。しかし、アンアン、ノンノ、マガジンハウスあたりから始まったかつての情報誌の隆盛も、最近ではネット上での情報流通に負けて陰りがあるという。
本が好きで、本にしか興味がなく、就職の時には迷わず出版社を選んだぼくとしては寂しい思いが残った。まだ日本の出版界にブロックバスター時代が到来する前の1980年代初頭に出版社をやめて、教師に転職したのは正解だったな、と思わせる映画だった。
* * *
T-ジョイ大泉の館内には、先日のテレ東「アド街ック天国 大泉学園」でも紹介されていた高倉健と吉永小百合の腕(+手)のブロンズ像が飾ってあった。テレビを見るまでは気づかないで素通りしていた。ハリウッドの路上にある俳優たちの手形を真似たのだろうが、ハリウッドのほうがよい。
現地に行ったとき、ぼくはソフィア・ローレンの手形にぼくの手を合わせてみた。ソフィア・ローレンと空間を共有している気分になった。

2021年3月31日 記