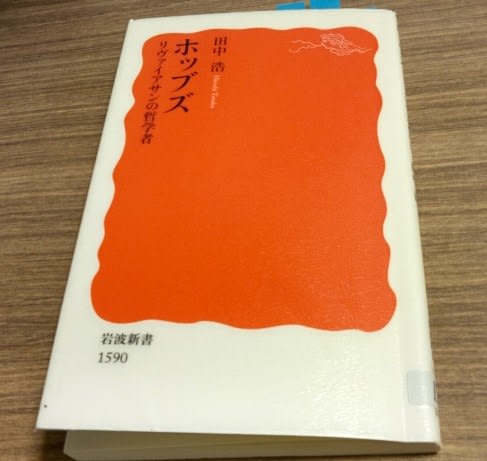田中浩『ホッブズーーリヴァイアサンの哲学者』(岩波新書、2016年)を読んだ。
東京新聞に掲載された記事で、水田洋さんが101歳だったかでご健在ということを知り、以前水田氏が訳したアダム・スミス『グラスゴウ大学講義』(日本評論社)のアンコール復刊を希望したこともあって、懐かしさから、改訳版である『法学講義』(岩波文庫)を読んだ。
そして、どういう動機だったか、ホッブズも読み始めることになった。
この夏の間、『法の原理』(高野清弘訳、ちくま学芸文庫)、『哲学者と法学徒との対話』(田中浩他訳、岩波文庫)、『リヴァイアサン (1) (2)』(第1部、第2部、角田安正訳、光文社古典新訳文庫)、『ビヒモス』(山田園子訳、岩波文庫)、『リヴァイアサン (3)』(第3部、永井道雄他抄訳、中公バックス・世界の名著)と読んできた。
原典を読むと(もちろん翻訳でだが)、ホッブズの豪快さと、その一方での慎重さ、注意深さも伝わってきた。しかし、何を意図した記述なのかが分からなかったり、論旨というか論証の過程が理解できなかったりしたことも少なくなかった。
今回、田中氏の本書を読んで、理解が不十分なとことが解明され、まったく理解できていなかったことなどをたくさん知ることができた。
とくに、ホッブズの生きた時代、彼の生涯と著作との関係、先行する諸著作、その後の思想史上の諸著作(とくにロック)との関係について、多くを知ることができた。
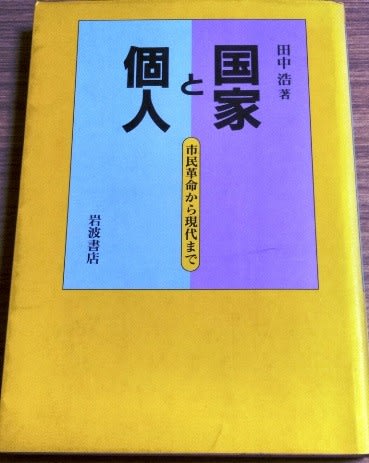
ぼくは教師時代に、専門外の憲法の授業を担当する必要から、日本国憲法の前提である自然権、社会契約論の勉強のために、田中氏の『国家と個人ーー市民革命から現代まで』(岩波書店、1990年)は読んだことがあった。
市民革命の時代、憲法の時代、議会の時代を、『国家と個人』では、ホッブズ、ハリントン、ロックの思想で辿っていた。
本書『ホッブズ』の論旨も基本的には変わっておらず、近代国家原理の始祖ホッブズに欠落していた制度論を、ハリントン、ロックらが補って、近代初期の民主主義(議会主義)の政治理論が完成したという系譜が前著より詳しく論述されている(131頁)。
ホッブズの「自然状態」論が、古代ギリシアの思想家エピクロスの自然状態、自然権、自然法、社会契約論と「ほとんど同じである」という指摘に驚かされた(37頁)。
エピクロスから、キケロらを経て、17世紀にガッサンディによって再生された「社会契約」論を、人民主権に昇華させたのがホッブズの功績であるという(72頁)。
こんなエピクロス評価は、高校世界史ではまったく教えてもらえなかった。柴田三千雄他『新世界史』(山川出版社、1999年。ただし息子が使った教科書)では、エピクロス(派)は、衰退するポリス政治から逃避し、「生の目的は唯一の最高の善たる快楽にある」と説いたとしか書いてない(33~4頁)。
「最高善」、すなわち快楽とは「生きていることそれ自体である」と考えれば、「生命の安全、自己保存」こそコモンウェルス設立の唯一の目的であるというホッブズの理論との親近性も感じられる。
エピクロスの「自然状態」論を読んでみたいが、エピクロスの邦訳ははたしてあるのだろうか。
「自然状態」が古代ギリシアのエピクロスに起源をもつものだったということで、15世紀以降の大航海時代にヨーロッパにもたらされた南洋の諸民族の社会、習俗に関する知見が、近代の社会契約論者の「自然状態」論に影響しているのではないかというぼくの仮説(思いつき)は見事に粉砕されてしまった。
田中氏の本書では、ホッブズの思想の中核としての、自然状態、自然権、社会契約、市民法・自然法論が繰り返し語られる。ただ、この繰り返しは、田中氏が繰り返しているというよりは、ホッブズ自身が『法の原理』から『市民論』そして『リヴァイアサン』に至るまで繰り返し述べていることの反映でもある。
『法の原理』第1部「人間の本性」において、人間にとって最高善は「生命の安全」(自己保存)であり、それを実現するために人々は「力を合成」(社会契約)して「共通権力」を作り、「自然状態」において生まれながらに持っていた「自然権」(生きるためのあらゆる行為を行なう権利)を放棄し、社会契約をした全員の「多数決」によって「代表」(主権者)を選び、主権者の作る市民法に従って平和に生きよ、とホッブズは命じた(33頁。さらに40頁以下で各々について敷衍される)。
この内容は『市民論』においても(78頁。ただしここでの論点は主権者が有する絶対的権力にシフトしている)、『リヴァイアサン』においても見られる(92頁以下)。
「自然状態」論も「社会契約」論も、先行する提唱者があったが、人間の意志(契約)や恐怖など人間の本性(情動)から出発して、国家(commonwealth)が、生命の保存および平和を目的として人間によって作られた人工の被造物である(=社会契約)という結論に導く点が、ホッブズのオリジナルな立論である。
社会契約論の基本ラインは高校時代に知って以来、日本国憲法の基本思想でもあり(前文)、違和感なく受け入れてきた。しかし、主権者権力の絶対性は、ロックは平和な時代の思想家、ホッブズは戦争(内乱)の時代に生きた思想家だったからと言われても、違和感というより反感を禁じえなかった。
ところが原典を読むことで、主権者権力の絶対性が、生命の維持、平和の希求という彼の出発点に由来することがよく理解できた。ホッブズの主権者権力論は、チャールズ1世の絶対王政や同2世の神授王権を支持するためのものではなく、それどころか、クロムウェル政府にすら絶対的主権者としての権力を認めていたことを本書によって知ることができた。
ただし『ビヒモス』は議会主権を否定し、君主とくにチャールズ1世擁護の書のように思うのだが・・・。
ホッブズの主権者権力の絶対性は、ローマ教皇ら非寛容なカトリック教会との戦い、国家を宗教から解放するための理論の支柱でもあった(84頁~)。
本書を読んでも、なお理解できなかったことをいくつか。
1つは、彼の社会契約論において、人民が多数決によって代表者を選び、選ばれた者が主権者となるという過程だが、なにゆえ「多数決」でよいのか、社会契約は全員一致でなければならないのではないのか。多数決だとしたら、敗れた少数派はその社会の構成員にならないのか。
社会契約の中に、どのような理屈によって「多数決=多数者に従う」という合意が含まれるのか。多数決で平和は訪れるのか。いっそ、ホッブズ自身ときおり援用する「くじ」ではいけなかったのか。
2つ。「社会契約」を「力の合成」と言い換えることも、田中氏の本書には頻出するが(初出は33頁)、原典を数冊読んだけれど、「力の合成」に出会った記憶がまったくない。読み落としたのか、角田訳や永井訳では違う言葉があてられていたのか・・・。
「力の合成」という言葉は、感覚と情動から出発して政治体の形成を説くホッブズがいかにも使いそうな言葉ではあるが、「合成」のニュアンスは理解できない。「社会契約」は全人民の意志の一致といえば十分ではないのか。
社会契約は「力」の「合成」というよりは、「力」(=自分自身を自分で守る権利)の「放棄」(=主権者への譲渡)だったのではないか。
3つ。“commonwealth” という言葉の使い方も、本書を読んでもなお理解できなかった。
共通権力 “common power” と同じ意味なのか違うのか、“civil state” とは違うのか。 “Leviathan” とは違うのか。
“commonwealth”は一般的な言葉で、社会契約によって成立したか否かにかかわらず「政府」とか「国家」一般をさすようにも使っているが(ポリスや「聖書」中の国家など)、社会契約に基づく主権者国家だけが “commonwealth” のようにも読める。

※ 上の写真は水田・田中訳『リヴァイアサン』(河出書房<世界の大思想16巻>、1973年)に掲載されたホッブズの肖像画。本書ⅴ頁にも晩年の肖像画が掲載されているほか、中公バックス版や岩波文庫版『リヴァイアサン』にも肖像画が載っているが、本書に描かれたホッブズの生き様からは、この肖像が一番ふさわしいと思う。
ホッブズは、ピューリタン革命が進行中の1652年に亡命先のフランスからイギリスに帰国した。そのため、1651年に出版された『リヴァイアサン』は、クロムウェルに阿るために執筆されたという批判があるらしい。
本書によれば、ホッブズが帰国を決意したのは、1649年に国王チャールズ1世が処刑され、息子の(後の)チャールズ2世のパリの亡命宮廷に出入りしていたホッブズも身の危険を感じて、新政府(クロムウェル政権)への帰順を考えたのではないかと推測する(63頁)。
宗教的「寛容」を認めない長老派議員130余名を、クロムウェルの部下が追放し、議会(残部議会)が宗教的に「寛容」な独立派議員だけになったことも帰国をうながす要因となったようだ(63頁)。
ホッブズは、クロムウェルの評議会に出頭してクロムウェル政権への服従を誓って帰国を許可されたという。この誓いを「エンゲージメント」というそうだが(65頁)、内心の自由を唱え、内心は最後の審判のときに神によってのみ裁かれる、法によって罰することはできないと書いているホッブズのことだから、「誓い」ながら内心でペロリと舌を出していたことだろう。
スチュアート朝に忠誠を尽くすという心情に固執することなく、「生命の安全」を保障する主権者(現実の政権)に従うことは、ホッブズにとって自然な態度だったと田中氏はいう(63~4頁)。
ホッブズは自然権論者、社会契約論者としての側面ばかりが強調されてきたが、彼の主戦場が「国家と宗教」の問題、信仰の自由の問題だったことも、本書で強調される。
『リヴァイアサン』第3部、第4部は、ローマ・カトリック教会と教会およびローマ教皇との全面的対決であるという(91頁)。
ホッブズの信仰の自由、内心の自由に対する信念は随所からうかがうことができたが、ローマ・カトリックとの対決は、抄訳ですませてしまったためか、あるいはまだ『リヴァイアサン』第4部を読んでいないせいか、十分には伝わってこなかった。
ただし、オックスフォード大学やそこで教授されるスコラ哲学、アリストテレスに対する彼の反感、嫌悪感は、原典のあちらこちらで述べられていた。
映画『クロムウェル』でも、ピューリタン革命当時のイギリス人の反カトリック(反フランス、反アイルランド)の心情は伝わってきた。ホッブズの約100年前のヘンリー8世治世初期を描いた映画『わが命つきるとも』では、大法官トマス・モアのカトリックの教義やローマ教皇に対する忠誠心はゆるぎないものだったのだが。
ホッブズが、マグナ・カルタ(1215年)以来のイギリス政治の伝統である(国王と議会との)混合政体、田中氏のことばでは「制限・混合王政論」(例えば32頁)に対して消極的態度だったことも印象的だが、真意は理解できなかった。混合政体=主権の分割を峻拒するホッブズの真意はどこにあったのか。
本書によれば、ホッブズにとって、議会は、ローマ教皇・カトリック教会や神授王権論と並ぶ「敵」だったという(メモには残っているのだが、ページ数を書きとめなかったためにどこかに書いてあったが、見つからない)。
国家の原理を人間の本性、理性から構築するホッブズにとって、伝統や慣習を重視する議会(制限王政論や混合政体論)は受け入れがたいものだったのか、あるいは、クロムウェルが絶望したように、ホッブズもイギリス議会の現実に絶望して、君主制支持とも読める主権者権力の絶対性を唱えるに至ったのか。
ただし、ぼくが理解した限りでは、ホッブズの絶対的主権者は必ずしも一人の人格(君主)を意味するものではなく、議会(議員団)を主権者とすることも理論的には排除されていないように思う。したがって、ここからロックの議会主権論に至る道が拓かれることもあるのではないか。
などなど、今回もまとまりのないことを書いてしまった。理解が不十分であることの証明だろう。
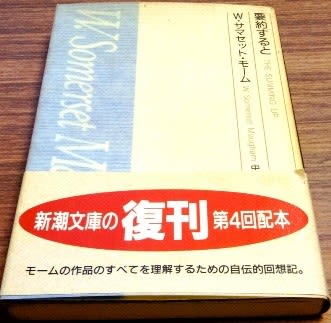
思い出したが、ホッブズの英語が明快であるという指摘も本書のどこかにあった。
サマセット・モームも『要約すると』(中村能三訳、新潮文庫)のなかで、文章を研究するものがまず最初に研究すべきイギリス語として、ホッブズやロックの文章をあげている(228頁)。さらにモームは、『リヴァイアサン』に現われたホッブズの本質をジョンブル気質と書いているが(同頁)、本書によってホッブズの91年の波乱の生涯をたどってみれば、「ジョンブル」というのはこういう人物なのかと、納得がいく。
2021年9月23日 記